four o'clock 夜咲月の花

真っ暗な中天にぽっかりと浮かぶ月を見上げる。
けれど、煌々と輝くという秋の月はなんだか白くぼやけていた。
薄暗い視界の隅、見慣れた顔がこちらに近づいて来るのに気付き、呆れて溜息をついた。
「……ラスリー、また部屋を抜け出したのですか?」
普段の正装ではなく、ゆったりとした衣の上、肩に上着を掛けただけの姿で現れた赤毛に橙の瞳の持ち主は苦笑しながら言った。
「リシェルこそまた一人で庭園に出て何をしている? ここに来たってアイカはいないぞ?」
「―――分かってます。それに質問をしているのはこちらです」
アイカが帰ってから一か月。
もうそんなに経ってしまったのか、というくらいには確かに過ぎ去った時。
けれど、庭園を歩いていたら、ふと彼女が顔を覗かせるのではないかというほど時は経っていない。
そして一か月前に負った彼の傷もまた、まだ癒えてはいない。
「医者から部屋を出るなと何度も言われているでしょう。そんなに動いては治るものも治りませんよ?」
少し動けるようになったからと言って、以前と同じようにお茶を飲みに来る彼。
もちろん、その場で追い返すが、何度追い返しても止めようとしない。
それどころか、庭園まで出てくるとは…………
本当にこの男、どうにかして欲しい。
世話をしなくてはならない医者の苦労は測りきれないだろう。
「それなら、部屋に仕事を持ってくるなと周りの者に言ってくれないか? あれだけ大量に持って来られれば抜け出したくなる気持ちも分かるだろう?」
肩をすくめながら言うラスリーに呆れた目を向ける。
「どうせ貴方が確認を頼まれた書類にいちいち文句でもつけたのでしょう……?」
「けちをつけられるようなものを持ってくるから悪い。大体あんなものじゃ使えないだろう。俺がやってしまった方が手っ取り早い」
「……そうやって、結局自分で仕事を持ちこんでしまった訳ですか」
本来は病室であるはずの部屋が大量の書類に埋もれてしまった本当の理由を知り、頭を抱えた。
「自業自得です」
「やはり、アトラスに回すべきか」
「陛下の手をこれ以上煩わせるのはやめてください!! そんなことになるぐらいなら私が手伝います」
ただでさえ、陛下の仕事は多いのだ。
この男のせいで心労を増やすわけにはいかない。
庭園につながる回廊の柱に体を預け、溜息をつく。
「はぁ~、もう、貴方と話していると疲れます」
「俺は楽しいけどな」
くつくつと笑うラスリーを横目で睨みながら、再び夜空に浮かぶ月へと視線を戻す。
やはり、ぼんやりとした光しか放っていない月はそれでも円を描くように辺りの暗闇を照らしている。
そのまま、しばらく眺めていると隣で「ああ」という納得したような呟きが漏れ、再びラスリーが口を開いた。
「月を見ていたのか」
その言葉に「ええ」と頷く。
「アイカの国では十五夜といって秋の月を眺める風習があるのだそうです。なんでも、その時期の月が一年の中で最も綺麗なんだとか」
「だが、今夜の月は、ぼやけているな。大体フィラディアルで月が一番綺麗に見えるのは冬だろう。空気が澄んでいる分はっきりと見える」
「そうですが……。貴方には趣というものがないのですか?」
「綺麗というなら月に照らされたリシェルの方が綺麗ですよ。髪が月の光を宿したようで」
急に前に立ち、その口に笑みを浮かべながらラスリーが私の髪を一房手に取る。そんなラスリーに冷たい目線を送りつつ一言。
「邪魔です。月が見えません」
そう言ってやると彼は可笑しそうに声を立てて笑いながら素直に私の前から退き、柱に手をあてた。
「それは無いだろう?」
「貴方の世辞に付き合っているほど私は暇ではないのです」
「別に世辞では無いのに」
「なら、その笑いは何ですか。わざわざ貴方がそのようなことを言う度に反応していてはきりがありません。もう、いい加減慣れました」
「リシェルらしい」
尚も笑い続けるラスリーを無視して月をじっと眺め続ける。
その姿がどうやら相当必死に見えたらしい。
ようやく笑いを収めたラスリーが不思議そうに私を見ながら首を傾げた。
「そんなに真剣に月を見て何かあるのか?」
私は、ちら、と彼を見てその問いに答える。
「アイカが言っていたのです。月の影の形がウサギに見えると。他にはカニや女性にも見えるそうです」
ラスリーもまた隣で月を見上げ目を凝らしているのが分かった。
「……あれが、ウサギに見えるのか? 俺には全く分からないんだが」
「―――見えません」
私は小さく溜息を洩らした。
「だから、どうやったら見えるのかさっきからずっとここでこうして月を見上げていたのです。……ですが、やはり、私には無理のようですね」
諦めて月から目線を外し、代わりに隣に居るラスリーを見上げて苦笑する。
その瞬間、彼の橙の目が細まり、大きな手が頬に触れた。
「口付けてもいいか?」
「―――どうしてさっきの会話の流れからそうなるのですか? 嫌ですよ」
見降ろしてくる橙の瞳を軽く睨むとラスリーは苦笑しながら私の頬から手を離した。
温もりが離れて頬に夜風の冷たさが戻る。
「昔から口が達者だとは思っていましたが、最近は前にも増して言うことが大胆になってきましたね」
「もう、隠す必要がなくなったからな」
呆れた口調で言ってやったのに返って来たのは穏やかな笑みだった。
予想外の反応にじっと彼を見上げてしまうと「どうした?」と問いかけられて慌てて視線をそらす。
「何でもありませんよ」
けれど、再びちらとラスリーの横顔を見てしまい、溜息を洩らしてしまった。
「―――ラスリー、髪に葉が付いてますよ」
「こっちか?」
そう尋ねながら赤毛の髪に手を当て、払い始めたラスリーに向かって首を振る。
「そっちじゃありません。取ってあげますから少し屈んで下さい」
ラスリーの赤毛の髪に手を伸ばしながら、顔を近づけ一瞬だけ掠める様に触れる。
「…………今のは?」
驚いたように橙の瞳を見開くラスリーが少し可笑しい。
いつも飄々と澄ましている分、少し。
「 まだ、礼を差し上げてなかったのでその代わりです。別に他意はありませんよ」
未だ呆然と立ち尽くすラスリーを下から見上げる。
「……こんなことをして襲われても知りませんよ」
「ラスリーが守ってくれるのでしょう?」
「俺に襲われたらどうする?」
「ラスリーはそんなことしないでしょう」
「なんだかすごく信用されてるな、俺……」
苦笑するラスリーにクスクスと笑いを洩らす。
「だって、そんなことされたら私はラスリーを嫌いになりますよ?」
「それは……困る、な」
「でしょう?」
冗談めかして言ってみたが、実際のところでは感謝しているのだ。
この一か月、思ったより苦しくないのは少なからずラスリーの御蔭だと思うから。
ラスリーの顔を見上げ、あまりにも不自然に笑いを止めてしまった私に、彼が再び「どうした?」と尋ねてくる。
「そんな風に…………。い、いえ、何でも。さぁ、そんな姿でいたら風邪をひきますよ。いい加減、部屋に戻りましょう」
それだけ言ってしまうと、私は庭園に背を向け回廊へと歩き出す。
「部屋まで送ろう」
「……い、いいですよ。むしろ私がラスリーを部屋まで送ります。傷に障りますよ?」
「もうほとんど治った。礼の礼だ」
「意味が分からないのですけど……」
笑みを向けながら隣を歩くラスリーに苦笑したが、目が合ってしまい、慌ててその橙の瞳から目をそらした。
全く、なんだか今日は調子が狂ってしまいます。
貴方がそんな風に嬉しそうに笑うから。
月が照らす回廊を歩きながら、なんだか不思議な気持ちで私はひっそりと溜息をついたのだった。
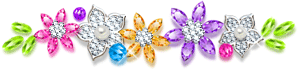

(c)aruhi 2008