four o'clock アイカの日常

大学の講義中、ふと思った。
これって意味あるのかなって。
だって、私が目の前で受けている授業は美術史だ。
美術史の授業を受けているからといって私が描く美術を専攻しているわけじゃない。私が属しているのは国際文化学部という、いわゆる、あらゆる世界の文化を中心とした社会科系の学部で、その中で私が専攻しているゼミが西洋美術史なのだ。だから、自然と美術に関した授業が多くなる。私自身、多少の興味があって選んだ大学とゼミだから授業は楽しい。
楽しいんだけど…………これって役に立つ?
だって考えてみて?
もしよ? もし、私がフィラディアルにもう一度行けたとしたら……
ううん、“もし”何て言ったらきっとリシェルに怒られちゃうね。
―――言い直します。私が今度フィラディアルに行った時この知識って役に立つのかな?
そりゃあ、正直言うと、すっごく楽しかったよ。
やっぱり、フィラディアルってこっちでいう中世ヨーロッパが一番近いせいか絵画や彫刻も似てる部分がたくさんあったし。私が住んでる町はそんなに大きくないから美術館なんてものないし、大学がある市内の美術館にも有名な画家の絵なんてほとんど来ない。
だから、フィラディアルで巨大な宮廷画を見た時、本物ってこんなに色彩が鮮やかなんだって、筆の木目細かな質感に、輪郭線が一切無いスフマート(ぼかしの技法の一つね)、授業で習ってきた技法や要素が実際に取り入れられてるのを発見していちいち感動してた。
王様がこの絵はどういう時に描かれたものだとか、これは神話の場面のどういう場面だとか、一つ一つ説明してくれて、そのどれもが面白かった。
だけど、思うんだ。
このままじゃ私、役に立てない。
襲われそうになってリシェルが庇ってくれた時も私は足がすくんで何もできなかった。
ランスリーフェン侯爵が刺されて倒れた時だって何もすることができなかった。
それどころか、あの直後は恐くて王様にすがってしまった。
何とか立ち直れたのはリシェルを励まさないと、と怯える自分を叱咤したから。
だけど結局あの時私にできたのは何一つない。
「私、医学生だったらよかったなぁ~」
そしたら、誰かが病気になった時、怪我をした時に役に立てるでしょう?
そんなこと起こって欲しくはないけど、もし起こってしまった時、対処できる方法があったらどんなに心強いだろうか。
けれど、私がこんなことを考えているなんて知る由もない友達の夕菜が隣でぷっと吹き出した。
ちょっと、夕菜なによぉ! こっちは真剣に悩んでるのに。
睨んでやったら夕菜が「ごめん、ごめん」と謝って来た。
「でも、愛花が医学生で将来医者なんて有り得ないから。むしろ、なったら恐いから。絶対注射とかされたくないし。よかったね、医学生じゃなくて」
「…………」
よかったの、か?
確かに夕菜が言う意味も分かるけど。自分でもちょっとそうかもって思わず納得しかけちゃったけど。
「何よ? いきなりどうしたの?」
夕菜が肘をつき、顎を手に乗せて私の方を見る。
なんだか、悩んでる私を見て楽しんでない? 心なしかニヤニヤしてるよ?
はふー、と息をつく。
「なんかさぁ、こんな授業受けてて役に立つのかなぁって思って」
夕菜が一瞬固まった。ちょっと、その反応どういう意味ですか、夕菜さん。
「……まぁ、私達も今年から就活だもんね。ボケっとしてると思ってたけど、愛花もちゃんと考えて悩んでたんだ」
う~ん、なんだかちょっと違うし、失礼なこと言われてるけど一応伝わった?
―――というか私、就活のこと、すっかり忘れてたよ。どうしよう。こっちも問題だ。
「けどさぁ、将来何が役に立つかなんてその場に立たないと分からないじゃない? もし仮に医学を習ってたってそれが役に立たない場所なら役に立たないし、逆に美術史だって役に立つ場所でならきちんと役に立つでしょう。要は、自分がその場に立った時どうすれば一番いいのかを考えて、ちゃんと行動に移せるかでしょう」
夕菜がすらすらと言い放った言葉にぽかんと口を開く。
何だか目から鱗なんですけど。この言葉って、こういう時のことを指してた言葉だったんだ。
「愛花、何その顔。変なの~」
夕菜がこちらを指差してケラケラと笑う。授業中だから小さな声ではあったけど。
「夕菜」
「ん? どうした?」
「ありがとう」
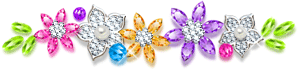

(c)aruhi 2008