four o'clcok 帰ってきたアイカ

「―――――うっわ……!」
これが目を覚ました瞬間、私が一番初めに発した言葉。
服の下には固い土の感触。
不思議なものでも見るように私を取り囲んでいる堀の深い顔立ちの人々。
立ち並ぶのはヨーロッパの街のような美しいレンガ造りの建物。
―――そして、真っ直ぐと伸びるこの道の先に見えるのは日本では絶対に見ることのできない西洋のお城。
フィラディアルだ――――!!
確信した瞬間私は立ち上がって目指す方へと真っ直ぐに駆けだした。
私を囲む奇異の視線なんて気にしてられない。スカートに着いた泥なんてもっと気にしてられない!
早く、早く、と急かす心に任せて足を走らせる。
だけどさ、やっぱり、私は物語に出てくる主人公にはなれないみたい。数百メートル進んだところで早くも息が切れ始めた。
きっつい! とにかく、きっつくて、どんどん速度が落ちてく。そういえば、私、走るの苦手な方なんだよ。うぅ、こんなことなら、陸上部にでも入ってきちんと練習しとくんだった……
しかも、お城全然近くなった気がしないんですけど……。やっぱ、元々おっきいから大きく見えたんだね。遠近法か? 遠近法だったのか!?
あー、でも良かった。一本道じゃなかったら絶対、私、迷子になってたよ。それでまた怪しいおじさん達に連れていかれそうになっちゃたりなんかして。あはは……って笑えないよ! 私!
なんだか自分で自分に突っ込みを入れてしまうほど疲れすぎているのか、思考回路がおかしくなってきた。
それでも、足を止めることなんてできない。体はもう限界だって叫んでるけど、心が足を止めさせてくれないの。一歩でも前へ、一歩でも早くって。
あと少しで、ようやくお城に付くというところ。私は表情を苦痛から喜びへと変えた。
だって、目の前に居るのはずっと会いたかった人たち。馬に乗っていた三人は私の姿を見るなり、飛び降りてくれた。息苦しさなんて一気に吹っ飛ぶ。
「王様!」
地面を蹴って勢いよく目の前の人物の胸へと飛び込む。
それが誰かはもちろん決まってる。
「リシェル!!」
思いっきり抱き付いた私に、リシェルは驚いたように若草色の瞳を見開いていたけど、結局しっかりと抱き返してくれて微笑んだのだ。
「お帰りなさい、アイカ」と。
黄昏時のバルコニー。眼下に広がる家々の屋根の瓦は夕日色に光り輝く。
移り変わる色の世界をうっとりと眺めていた私は、けれども、さっきから隣で聞こえ続けるくつくつという笑い声に眉根を寄せた。
「ちょっと、王様! いつまで笑ってるの?」
「いや、悪い」 と言いながらも、私の方を向いた王様は、また吹き出した。
なんて失礼な!
「だって、普通あそこでリシェルの方に抱きつくか? かなり驚いてたぞ?」
「う……だってさぁ」
だってね。
「王様に抱きついたらキスされそうだったから。私は純日本人だから、人前でなんて絶対無理! そんな習慣はありませんし、慣れません!」
「まあ、それは否定できないが……。なら、抱きつくのはいいのか?」
「いや、それもあんまりしないけど……ん~でも、私の場合、久しぶりに会った友達には抱きつくかなぁ?」
「そうなのか?」
「うん、そうなの」
王様を見上げる。
私を見下ろす青い目は穏やかで、とても優しい。それが分かるからすごく嬉しくて、少し泣きそうになる。
本当はずっと不安だったから。また、会えるかなんて保障はどこにもなかったから。『もしかしたら夢かもしれない』 なんてありきたりな言葉だけど、本当にそう思ってしまうから。
だから、確かめるように王様に触れる。引き寄せられて感じたのは確かな温かみで、王様がここにきちんと存在する証。
瞳を閉じて、心地よい温かさにずっと浸っていたかったけど、やっぱり泣きそうになっちゃったから、私は顔を上げた。
「ねぇ、王様? リシェルとランスリーフェン侯爵はあれからどうなったの?」
「あーーー」 と王様が苦笑する。
「全く進展はないな」
「全く!?」
「ああ、全く」
「ちっとも?」
「ああ、ちっとも、これっぽちもない」
断言する王様の言葉に少しがっかりする。楽しみにしてたのに。
「王様が邪魔してるんじゃないでしょうね」
「するわけないだろう」
「けど、ちょっと顔が嬉しそう……」
「そんなことはない」
否定したけどやっぱりどこか嬉しそう。この前もどこか寂しそうだったもんね。
「王様、シスコンは嫌われるんだよ?」
「何だそれは?」
怪訝そうな顔をする王様に思わず吹き出す。
まあ、リシェルは王様の妹では無いけど。それでも、王様にとっても大切なお姫様だったってこときちんと分かってるから。
ランスリーフェン侯爵のことを応援してるってことももちろん知ってる。だけど、やっぱりどこか寂しいんだろうね。その気持ちは分からないでもない。
「そういえば」と彼は口を開く。
どこか悪戯そうな笑みを浮かべて。
「アイカはラスリーを敵に回したかもしれないぞ?」
「へ!?」
な、なんで? 私何もしてないよ!? 多分……
焦る私に王様は続けた。
「今日、リシェルに抱きついただろう?」
「えーーー!?」
「嫌がらせがアイカに回るかもしれないな。お陰で助かった」
嬉しそうにウンウンと頷く王様は性格が悪いと思う。
「ちょっと、それは勘弁!!」
叫んだ私の後ろで、けれど、淡々とした声が響いた。
「大丈夫だ。それは無い」
「ランスリーフェン侯爵!?」
ぎょっとして部屋の方へと振り向いた私達の前に立っていたのは長身で赤毛の持ち主。橙色の瞳を光らせて、彼は口の端を上げた。
「アイカにはいろいろ感謝してるからな。さすがの俺もアイカには手は出さないさ」
今、心の中で、「多分な」 て付け加えたような気がしたのは私だけでしょうか?
「どうした、ラスリー? 今日の仕事はもう終わりのはずだろう?」
「何を言っているのです、陛下。アイカが来たことで貴方の仕事は増えましたよ。色々準備をしなくてはならないことがあるでしょう?」
丁寧に貴族様風の笑みを浮かべてそう言い放ったランスリーフェン侯爵に、王様は、「やっぱり俺にはとばっちりがあるのか」 とものすごく嫌そうに顔を歪めた。
それでも王様は別段文句も言わずに、「分かった」 と手を振る。
「それから、アトラス。前にも言っただろう。もう少し人目をはばかれ、と。気を付けないなら俺は知らないぞ」
「悪い」
「まあ、いいが。とにかく中に入った方がいいだろう」
溜息を吐きだしたランスリーフェン侯爵に、王様は苦笑を洩らした。
「そうだな。有難う」
「別にいい。それじゃあ、また後で」
それだけ言ってしまうと、ランスリーフェン侯爵はさっさと部屋を出て行ってしまった。
なんだか、私にはよく分からない会話。
一瞬空気が張り詰めたような気がしたのは気のせいだろうか?
「どうした?」
王様の青い目が私を見下ろす。
なんだかよく分からないこの気持ちは何と言葉にしたらよいのだろう?
結局私は、「何でもない」 と首を振ってしまった。
「―――うひゃあ!」
瞼の上に柔らかな口付けが降る。
私が出した変な声に王様は可笑しそうに笑った。
うぅ、だっていきなりだったからびっくりしたんだよ……
「やはり純ニホンジンのアイカには駄目か」
くつくつと鳴る声には優しさが滲む。
だから、私は恐る恐る顔を上げてはにかんだのだ。
「いいよ、しても。ここには人がいないからね」
やっと会えた、愛しき私の王様へ。
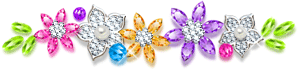

(c)aruhi 2008