four o'clcok 落ち葉の行方

「兄上!」
勢いよく開きすぎて、壁にまでぶち当たって大きな音をたてた扉。
顔を上げると、そこに立っていたのはやはり予想道理の人物、六歳下の弟のグランベルだった。
肩下まで伸びた父譲りの茶の髪をゆるく三編みにし、涼やかな母譲りの紺の双眸を持つグランベルとは一滴の血さえ繋がってはいない。にもかかわらず、父と母がそうであるように、この弟もまた俺に対して、わずかなわだかまりすら持っていないらしい。
むしろ、毎日飽きもせずにやって来てはその日あったことをわざわざ報告するほどに懐かれているのだから、この家に連れてこられた俺は本当に運が良かったのだろう。
「なんだ、グラン。何かいいことがあったのか?」
いつも嬉々として報告にやっては来るが、今日は一段と嬉しそうな顔をしている。にんまりと際限まで引き延ばされた彼の口からは、今にも歯が覗きそうなほどだ。
部屋の入口から、すたすたと大股でやって来たグランベルは、俺の前に立つと「聞きましたよ」と言って笑った。
「もう兄上、水臭いじゃないですか! もうすぐで三か月も経とうとしてるのに、ちっとも知りませんでした」
「何を」
「学友から聞いたんですよ。結構有名だったらしいのに、僕のところまで回ってくるにはずいぶん時間が経ってしまったようですね。やっぱり、学生の身じゃ王宮の事を知るには不利ですよね~」
「だから、何の話だ」
「だから、何の話だ」
「エリィシエル姫の首飾りのことですよ!」
グランベルの紺の瞳が期待に充ち溢れて、キラリと輝いたように俺には見えた。
「―――その話か……」
座っていた椅子に姿勢を崩して体を沈める。グランベルは自ら適当な椅子を運んでくると、姿勢を正してちょこんと座った。じっと俺が話し出すのを待つ姿も、彼の幼い頃とちっとも変らず、微笑ましいのは微笑ましいのだが、話題が話題だけに、なんだか気が重かった。
「グラン、悪いが、お前が期待しているようなことは何もないぞ」
「え? とうとうエリィシエル姫が僕の義姉になってくれるのではないのですか?」
元となる噂を作ったのは自分自身だが、弟から面と向かって問われると、なんだか無性に溜息をつきたくなる。だが、とりあえず否定しておかなければ、リシェルに迷惑がかかるだろう。なんだかんだで、グランベルはリシェルと仲がいいから、彼は直接聞きかねない。
「ならない」
「でも、とうとう想いを伝えたのですよね」
「だな」
「兄上の首飾りを受け取ってくれたのでしょう?」
「騙したからな」
「でも、姫は今も首飾りを付けているのでしょう? ばれてないんですか?」
「ばれてはいるが……ただ、アイカがいるから付けてくれてるだけだろう」
「黒髪の姫君がいるから、ですか?」
みなまでは答えず、ただ頷きだけ返す。
恐らくグランベルにも分かるだろう。
リシェルは元々アトラスの正妃に最も近い人物だったのだ。その座を離れたことを示す為にも、新たな妃候補としてのアイカを周囲に認めさせる為にも、この切り札は誰の目にも明確で、重要だ。
「そうなのですか。エリィシエル姫が義姉になってくださったら自慢できたのになぁ」
何とも残念そうに嘆息するグランベルに苦笑する。
「今のところは本来の目的を果たせているからいいんだ。期待させて悪かったな」
「いいえ。僕も噂を鵜呑みにしてしまって申し訳ありませんでした」
「気にするな。根源を流したのは俺だからな。むしろ、そうやって広がってくれないと困る」
グランベルはちらりと視線を上げて微笑した。
「兄上、星夜祭はどうされるのですか?」
「いつも通りだ。最後の仕上げ中」
「ああ、大変そうですね。……それに他のことも。これだけが、兄上の唯一の弱みですからね」
「…………」
グランベルは面白そうに笑った。星夜祭も含め、本当にこれだけは毎回頭の痛い問題だ。
「端にいれば問題ないだろう」
「あしらうのも大変そうですがね」
「毎度のことだ。なんてことないさ。
グランはマルシアローズ譲と、だろう? 良かったな」
驚いて目を丸くする弟は素直に可愛いと思う。グランベルはほんの少しだけ頬を紅潮させると、はにかんだ。
「なんだ、知ってたんですか。せっかく報告しに来たのに」
「知ってたというか、こうなると分かってた」
前にマルシアローズ嬢に会った時、すでに彼女はグランベルのことを目で追っていた。グランとマリアも、また、小さい頃からの幼馴染だ。名称的には同じ立ち位置にもかかわらず、どうしてこうも違うものか。
「グランの器用さが心底羨ましい」
ぼそりと零すと、グランベルは嬉しそうに声をたてて笑った。
「兄上と違って僕は自分の身の丈に合った人を好きになれましたからね。それでも、兄上は強敵でしたよ。マリアの目を兄上からそらすのは大変でした」
「言うようになったな。だが、ホントに手を出さなくて良かったよ」
「手を出そうなどと、ちらとも思っていなかったくせに」
ちっとも疑っている様子を見せずグランベルは断言する。だから、片眉を上げてみせた。「さあ、どうかな」と。
「嘘かもしれないぞ?」
「―――う、嘘じゃないですよね!?」
慌てだしたグランベルに、口の端を上げてにやりと笑ってやると、弟は安堵したように息を吐いた。
ぶすっとした表情で、グランベルは再び口を開く。
「いいですよ。僕もエリィシエル姫を昔からよく抱きしめてますからね」
「抱きついてるの間違いだろう」
「でも、姫はその後抱きしめ返してくれますよ。笑顔で」
「…………」
なんだか負けた気がするのは気のせいではないと思う。現にグランベルは勝ち誇ったように笑みを取り戻しているのだから。
「どうして兄上はこういう点に関しては不器用なんですかね。エリィシエル姫じゃなかったら、選り取り見取りでしょうに」
その表現はどうかと思う。なんかすごく語弊を生みそうだ。
「とりあえず、もう一度エリィシエル姫に想いを告げてみたらどうですか?」
「あれだけ言うのに、何年かかったと思ってるんだ」
「十年以上はかかってますよね。ですが、そもそもは兄上が悪いんですよ」
普通に答えるのはやめて欲しい。過去の所業がばれている分、グランベルの言っていることは大抵的を射ているのだから。
「でも、まあ、良かったではないですか。今度の星夜祭に関しては、いつもよりかは不機嫌にはならないでしょうからね」
「どうしてだ?」
「おや、兄上でも分からないことがあるのですね」
グランベルはクスクスと笑いながら、立ち上がった。
「今日の報告はこれで終わりです。では、また夕食時に」
「ああ」
部屋を出ていく弟を見送りながら、グランベルが言った言葉の意味を咀嚼する。
その意味が分かった瞬間、思わずふっと笑みが零れてしまったのは仕方がないことだと思うのだ。
窓の外に目をやる。
季節は足早に冬へと向かい、赤や黄に色づいた葉が次々と冷たい風に舞った。
地へと落ちた枯れ葉は夕日に照らされ、木の根元で橙に輝く。
もうすぐ、ここにある木はどれも一枚の葉すら残さなくなるのだろう。
やがて春が来て若草が芽吹くのは当分先のこと。
柔らかな陽光を浴びて若草が無事に輝けるように、今はただ、木の根の上に降り積もり、凍えぬように温めることができれば、きっとそれでいいのだと思うことにした。
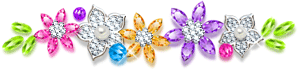

(c)aruhi 2008