four o'clock 紙袋

「ご機嫌麗しゅう、エリィシエル姫」
幾分かひんやりとした冷たさを宿す白い手を取り、口付けを落とす。
咲きかけの白いバラのような彼女の手は、いつも予想と違わず滑らかで瑞々しい。朝露に触れるがごとく、そっと。だが、輝く露も及ばぬほどの至高の甘さ。
挨拶と言えども、彼女に触れることができるのだ。
愛しき人に触れる。
これに勝る幸福などなかなか見つけられはしないだろう。
「ええ、御機嫌よう」
惜しみつつも、花びらさえ及ばぬきめ細かな白い手から唇を離す。顔を上げると、そこには大輪のバラを想わせる、優雅で崇高な笑みがあった。
それは、庭園の鮮やかな花々を霞ませるほど。どれほどに美しいと褒め称えられる花でさえも、きっと……
「―――あいてっ」
「どうしたのですか、オランリ伯」
「いえ、今、何かが突然……いえ、やはり何でもないです」
ズキズキと痛む頭に手をやる。そこには、早くもたんこぶが出来始めていた。絶対に何かが当たったのだ。
「ご機嫌麗しゅう、エリィシエル姫」
手の上に置かれていたエリィシエル姫の手が横からさっとさらわれた。
「おまえの仕業か、ランスリーフェン!!」
「いったい何の事ですか」と口上ではとぼけつつも、こちらに向けられた奴の口の端だけは確信犯的に上がっていた。
「リシェルをいくら脳内で褒め讃えようが勝手だがいつまでも手を握られているのは腹が立つ」
ぼそりと小さく零した奴の手は、しっかりとエリィシエル姫の手を取ったままだ。
「全くお前はどこまで独占欲が強いんだよ、ランスリーフェン」
「リシェルに関してはどこまででも」
「首飾りだけで足らないのか!」
「お前には全く効き目が無いようだからな」
「当り前だ。そんな物ただの飾りだろう」
「そこまで知られてると本当に厄介だよな」
ランスリーフェンはちっと舌打ちを鳴らした。
誰だこいつのことを物腰が柔らかで、微笑まれると卒倒しそうになるとか抜かした令嬢様方は。絶対に騙されてる。
「いい加減手を離していただけませんか、ランスリーフェン侯爵」
「ああ、すみません」
ランスリーフェンが手を広げて解放する。私達の応酬にちっとも気付いた様子の無いエリィシエル姫は素早く自身の手を引き抜いた。
気付くはずもない。応酬は全て聞こえぬほど密やかな囁きで行われたのだから。ランスリーフェンも馬鹿ではないし、もちろん、この私に関してはエリィシエル姫に見苦しい姿を見せぬ礼儀というものを当然わきまえている。当り前だ。
「ラスリー、執務はどうしたのですか?」
「大体のところは終った。今は休憩中だ」
苦言を呈すエリィシエル姫に対して、ランスリーフェンはさらり用意していたらしい答えを返す。
「絶対嘘だろ」
「そうだな、そういえば財務部に仕事を引き渡さなければならなかった。オランリ、後で取りに来い」
「―――っく!」
権力的には圧倒的に宰相である奴の方が上だ。実際に仕事は有りそうでもある為、言い返すこともできない。
「ラスリー、失礼ですよ。言い方というものがあるでしょう」
エリィシエル姫は眉を寄せて、極悪宰相をたしなめてくださった。全く以って彼女の意見には大賛成だ。
「だが、オランリとは昔馴染みだからな。気が知れてる分、つい」
ランスリーフェンは爽やかに笑んだ。例えたくもないが、例えるならば初夏の風のようだ。いや、いや、やはり、そんな風が初夏に吹いてきたら心底嫌だ。嫌すぎる。そんな風が吹いた日には一歩も外に出たくない。窓すら、けし粒ほどの隙間も開けたくはない。
大体、見え透いた嘘を付くな。こっちは寒気がするんだ。
一度奴を思いっきり睨みつけてから、当初の目的を果たすべく、エリィシエル姫に持ってきていた紙袋を差し出した。
「エリィシエル姫、約束の品です」
「有難うございます、オランリ伯」
私の手から紙袋を受け取ったエリィシエル姫は微笑した。春風の女神サンテリニアもまるで叶わぬほど、むしろ、彼の女神も喜んで夏の季節まで吹いて行ってしまうのではと思うほどに素晴らしい微笑みだ。いつ見ても、いつまでも、飽きることなど有り得ないだろう。
かさこそと音をたてながら紙袋の中身を確認しだしたエリィシエル姫。彼女の芽吹いたばかりの若草のような瞳が、驚きに見開かれてより一層大きく丸くなる。
「こんなにたくさん! 頼んでいた量を遥かに超えていますよ」
「いいのです。真に望んでくださる方にはより良く、より多くのものを。喜んでくださる顔を見れば、それは私達の糧となって、また新たなより良いものを作ろうという原動力にもなりますから。どうか遠慮などせず受け取って下さい」
「よろしいのですか?」
「ええ、受け取ってくださると私も嬉しいです」
エリィシエル姫は、少し躊躇いを浮かべたものの、結局最後には、はにかんで礼の言葉を下さった。その笑みは、水辺に彩りを加える菫の花のような可憐さを含んでいる。
ちっとも面白くなさそうな顔をしているのは、ランスリーフェンだ。表面上は穏やかな笑みを刻んではいるものの、橙の瞳は不機嫌さで早くも据わり始めている。
過去に奴に仕出かされた報復を未だに忘れられない私は、そっと奴と距離を取ることにした。
だが、それも無駄な努力だとすぐに知れた。開いた距離は、ほぼ同時に奴によって詰められたのだ。
「リシェル、こんな人を虐めていたような奴から不用心に物を受け取るのはあまり感心しませんよ。まあ、あのルブラン家子息の取り巻き集団から早々に離れた所だけは、なかなか賢かったと認めていますが……」
後ろ半分はこちらに目をやりながら、ランスリーフェンは言った。
いや、あれは離れたというか、離れないといろんな意味でこっちが危なかったのだ。
ただ、他の皆の頭が回らなすぎて、ランスリーフェンの危険さに気付かなかっただけにすぎない。あいつらは本当に阿呆だった。
元々小さな仕返しは結構陰で受けてきたのだ。だが、子供だった為に、今考えると、それはまだ可愛らしかったと言える。
問題はその後だ。権力を付けてから、さらに仕返しをしてくるなど性質が悪いにも程があるだろう。かつての友がどうなったかは知らないということにしておく。
「もう随分と昔のことでしょう。大体、貴方がそれを言いますか」
エリィシエル姫は渋い顔で言う。ランスリーフェンは当然言葉に詰まった。溜息を吐くことさえできずに、奴は口を噤む。
「オランリ伯、お忙しい中、本当に有難うございました。お引き留めするのも悪いので、もうそろそろお暇させていただきますね」
見惚れるほど優雅に腰を折って、エリィシエル姫は礼をする。私はエリィシエル姫に「いえいえ」と手を振って、彼女を見送った。
「―――で、リシェルに何を渡してたんだ?」
エリィシエル姫が少し離れた瞬間、ランスリーフェンは私に詰め寄って来た。もちろん張り付いていた笑みは疾うになりを潜めている。
けれど、エリィシエル姫が居ない今、私の方も、もう取り繕う必要は無い。だから、思いっきり溜息をついてやった。
「お前なら考えれば分かるだろう。紅茶だ、紅茶。このくらいでいちいち突っかかって来るなよ」
私の家は紅茶に関して秀でている。はっきり言ってフィラディアル宮廷においては右にも左にも出る者はいない。茶園を有し、独自に改良開発を行っているくらい本格的に取り組んでいる事業でもあるのだ。
「紅茶か? 紅茶ぐらいなら俺が持って行くのに」
「ランスリーフェン……お前、ほんっと面倒くさい奴だな。頭がいいのか、それとも至極悪いのか……私には分からん」
ランスリーフェンが顔を顰める。私はすぐに顔を逸らした。だけど、嘘ではない。事実なのだ。
「早く行け。エリィシエル姫が、待ってるだろう?」
ランスリーフェンが訝しげに首を捻る。
その顔は奇妙なもので、本当にこいつはあの宰相なのかと疑わしい。
だが、とりあえずランスリーフェンは私の言葉に従い、彼女の方に目を向けた。
大分先まで歩いて行っていたエリィシエル姫は、振り返ると呆れた顔をして、再びこちらの方へと向かって来る。
目の前までやって来ると、エリィシエル姫はランスリーフェンを見上げた。
「ラスリーが引き止めてしまってはオランリ伯がいつまでも戻れはしないでしょう? 貴方も早く行きますよ。休憩中なのでしょう? せっかくですから新しく頂いた紅茶を淹れて差し上げます」
本当に呆れた様子で、エリィシエル姫は告げた。
ようやく合点のいったらしいランスリーフェンはただ苦笑する。
「このことか……」
「ここ最近の紅茶の消費量が激しいとエリィシエル姫が嘆いておられましたよ」
「ええ、全くですよ。本当に少し困っています。オランリ伯の御蔭で、随分と助かりました」
「ああ、うん、有難う」
ランスリーフェンは口に手を当てて、くつくつと笑い声をたてた。どうやら、どうしても堪え切れなかったらしい。
エリィシエル姫はその様子をしばらく見上げていたが、ふと顔を逸らした。
「……先に行きますね」
「俺も行く」
歩を進め出したエリィシエル姫の後を追って、ランスリーフェンは彼女の隣に並んだ。
奴は「ああ、そうだ」と言って、こちらを振り返る。
「前に庇ってくれたことは、ちゃんと感謝してる」
いつの話だ。大体あれは自分と周りの奴らがやっていることの馬鹿さ加減に付き合ってられなくなったからにすぎない。それに、素直に謝辞を述べられると裏がありそうで恐ろしい。
答えずにいると、ランスリーフェンは、やはり、にやりと笑った。
「後で仕事を取りに来るの忘れるなよ。後、脳内で繰り出される美辞麗句は自分の婚約者殿に向けろ」
「何故私があの女を……」
褒めた讃えねばならないのだ、と続けようとして、慌てて口を噤んだ。濃い赤の瞳の女が頭に浮かんできたからだ。慌てて打ち消し、冷静を取り戻すことを第一とする。
全く以って心臓に悪い。
呼吸を整え、ランスリーフェンを見ると、奴はもうこっちを見てはいなかった。
悪態をついて、私もまた踵を返す。途中で抜けてきたから、また、仕事の続きをしなければならない。もう一度、仕事を取りに行く為に奴と顔を合わせなければならないと思うと、少々うんざりする。
けど、まあ、これ以上突っかかられることは無いだろう。
エリィシエル姫の美しい手には、当家自慢の最高級茶葉が入った紙袋がしっかりと握られていたのだから。
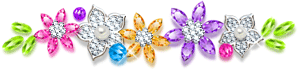

(c)aruhi 2008