four o'clock もう一つの込められしもの

「カザリアさんはロウリエさんに、何かあげないんですか?」
アイカの手にあるのはナズナの花。もしも、アイカが花言葉にさとかったのなら全力で突き返されただろう。だからこそ、零れそうな笑みを隠すことなんてできやしない。
そんなアイカが首を傾げて問いかけてきた。
「なんで私が! ロウリィとは政略結婚であって、そこに愛はないのよ!?」
「でもなんだか、ずるい気がします。私だって王様に花を渡しに行くなんて気恥かしいんですよ。はさみ貸して下さい、先生。今日の授業の成果に私が花を選んで差し上げます」
アイカの口が、ふふふと人の悪い笑みに変わる。絶対今日の仕返しにしか見えない笑みに。
そもそも、アイカに選ばれたらたまったものじゃない。なぜなら、彼女はまだほとんど花言葉を覚えてはいないのだから。そこらにあるのは、秋の代表的な花々で、つまりは、選ばれてしまったのなら非常に困る代物ばかりなのだ。
「わ、分かったわよ! 何か選べばいいんでしょう!?」
アイカの満足そうな笑みを横目に、私は再び座り込んで、ちょきんとはさみで切る。
「ほら、これでいいでしょう?」
「え……クローバーですか? しかも、花すらついてないし……四つ葉じゃなくて、普通の三つ葉?」
「ええ」
「え、でも、それって、やっぱり、それも、雑草……?」
「ロウリィにはこれで充分すぎるくらいよ。いいから、アイカはそのナズナをちゃんとアトラウス陛下に渡すのよ!」
アイカはどこか不服そうな、残念そうな顔。
でも、ロウリィにはどの花を持って行ったって同じだ。どうせあの人は毒の話をしようとするのだから。
「あれ、カザリアさん、クローバーですか? クローバーには―――」
「―――毒は無いでしょう?」
「はい、ありません」
私の手にしている草を見て、案の定ロウリィはぽやぽやと笑う。
「でも、良い薬草になりますよ」
「そう」
「どうしたんですか、それ」
ロウリィの机の前にちょこんと座る。どう見ても、周りの人たちより仕事は少なく見えるけれど、それでもあるにはあるようだ。
「庭園に生えてたのよ」
「ああ、クローバーは良い肥やしにもなりますからね。肥料として混ざっていたものが芽生えたのでしょう」
お茶いりますか? と聞いて来るロウリィに頷きを返しながら、なんとなく落ち着かなくて足をぶらぶらさせてしまう。
「アイカ姫の所には今のところ何も仕掛けられてはいませんでしたよ」
「そう。良かったわ」
ティーカップに茶が注がれる先から甘やかな香気が立ち上って、くゆる。手の中のクローバーはだんだんしおれ始めてきた。
「あげる」
差しだされたティーカップの代わりに、私が机の上に載せたのはくったりとした三つ葉のクローバー。それも、たったの一つだけ。
「僕にですか?」
「そうよ」
「カザリアさんは花言葉の先生でしたよね?」
「ええ」
ロウリィがクローバーを指で摘まんで、目の前に掲げた。彼の手の中で、三つ葉の重さに耐えきれなかったらしいクローバーの細い茎が曲がる。それは、まるでロウリィに向かってお辞儀をしているようにも見えて。
「僕はあんまり花言葉は得意な方ではないんですけどね~。どれで取ればいいのか教えていただけませんか?」
「―――別に深い意味なんてないわよ! アイカが何かあげないとって言うからっ!」
「じゃあ、“愛情”でとっても構いませんか?」
「―――っ!? しゅ、“守護”よ! “守護”!! また毒に関してるから危ないんじゃないかと思ったのよ!」
「そうですか、“守護”ですか」
ロウリィが珍しくクスクスと笑った。笑うと彼の蒼色の瞳は細くなりすぎて、見えなくなってしまうのだ。
「カザリアさんは前に四つ葉よりも、三つ葉の方が好きと仰ってましたね。懐かしいなぁ。星夜祭が終わったら、またピクニックに行きましょうね」
「…………完っ全に覚えてるじゃないの。やな奴ね」
ぼそりと不平を零して、そっぽを向く。「ありがとうございます」と横から聞こえてきたけれど、ロウリィの顔を見た瞬間に負けてしまうような気がして、顔を逸らしたまま頷いた。
ふと横にある窓を見たら、ロウリィの姿が映っていて、彼の指の中では三つ葉のクローバーがくるくると踊っていたのだ。
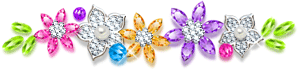

(c)aruhi 2008