four o'clock そらごとを編む

リシェル、とその日は彼の声がどこか重々しく部屋に響いた。
名を呼ばれたので、紅茶から顔を上げてみれば、呼んだ当人であるはずの赤毛の男は菓子を片手にどこか別の方を向いていた。ここ数カ月ですっかり慣れてしまったランスリーフェン侯爵の来訪とお茶会は違和感さえもどこかへ消え去ってしまって―――病室から抜け出しては姿を現す彼に「またですか」と問うのさえただの決められた挨拶のようになってしまって、なんだか酷く変だとは自分でも思ってはいるのだけれど。
未だ彷徨って定まらない橙の双眸を不思議に思い、「どうしたのですか?」と尋ねる。
ラスリーはぴくりと反応して、「ああー……」と言い淀んだ。なぜか深呼吸をして、居座まいまで正して、私の方を注視する。
「リシェル……落ち着いて聞いて下さいね……?」
一言一言をかみしめるようにゆっくりとラスリーは口を開いた。どこか緊張して見える彼の姿はとても珍しい。いえ、きっと、ここまでのものは見たことなどない。ラスリーは至極真面目な顔で、「決して私ではありませんからね」と丁寧に念押しまでして言った。
「リシェル……今日庭園に降りましたか?」
「え、あ……はい、降りましたけど」
それが一体何だというのだろう。意図がまったく掴めないのに、ラスリーがあまりにも恐る恐る尋ねてくるから、こちらまで緊張が伝染してしまいそうだ。
「あの、です、ねぇ……」
そこで再びラスリーは言葉を切り、口元を片手で覆い隠すと、思案気に視線を逸らしだす。
「ラスリー。何か知りませんが、はっきりと仰ってください。貴方らしくもない。こっちまで不安になります」
「いや、あの、テントウムシが……」
「テントウムシ?」
なぜ急にテントウムシ。首を傾げると、ラスリーは首肯すらせずに右の方へと目を彷徨わせる。右……、に何かあるのだろうかと目をちらとやれば、なるほど、確かにそこには小さな黒点を伴った赤の彩りがあった。
「ああ……テントウムシですね」
いつからそこにとまっていたのか、服の右腕部にいたテントウムシへそっと人差し指を伸ばす。ためらうように後ずさりながら、けれど指先にのってきたテントウムシがとてもくすぐったい。
「貴方の言う通り、きっと庭園から連れてきてしまったのでしょうね」
ユージアに押し開いて貰った窓へと立ち上がって寄る。ほんの少し、窓の外の世界に手を伸ばせば、風を感じたのか、テントウムシはすぐに飛び立って行ってしまった。
「……どうしたのですか?」
振り返ってみればラスリーがこちらを見たまま驚愕しているのが目に入る。けれど、驚いてしまうのは私の方だ。全くさっきから何だというのだ。
「だって、リシェル。テントウムシですよ?」
「ええ、確かにテントウムシでしたが、それがどうかしたのですか?」
「だって虫だぞ!?」
「は……い……!?」
思わず問い返してしまえば、ラスリーは我に返ったのか、気を鎮ませようとでもするかのようにティーカップに手を伸ばし、そのまま口へ運んだ。
「……昔はあんなに嫌がって逃げてたくせに……」
不服げに、恨めしげに、紅茶を睨んでぼやいてくる。彼が何のことを指しているのかはさすがに明白となった。
「あ……貴方が持ってきた虫とテントウムシは全く違うでしょう」
「どこが違う」
「まず大きさからして違います!」
きっぱりと断じてやれば、ラスリーは、ふむと何かを思考し始める。だが、しばらくして「いや」と一度首を振ると「ダンゴムシでも逃げてた」と言ってきた。
「ダンゴムシとテントウムシを一緒にしないで下さいよ!」
「そんなに変わらないだろう」
「私には変わるんです!」
丸まっている時はまだいいのだけれど、私にとってはあの蠢く無数の足が恐くて気味が悪い。それでも、初めてダンゴムシを目にした時はそこまでの恐怖など抱いてなかったはずなのだ。
「虫というよりも、虫を持って追いかけてくる貴方の方がきっとよっぽど恐かったのですよ」
「けど、最初に逃げたのは、リシェルだったじゃないか」
「貴方……最初に持って来たのが、なんだったのか覚えてないんですか!? 蛙ですよ? 蛙!」
「だってあの時は喜んでもらえると思ってたんですよ。捕まえたばっかりだったし。あの蛙の緑はリシェルの瞳の色と似てた」
「う、れしくないです、そんなの」
「どっちも同じくらい鮮やかなのに」
むっとした顔を向けられても困る。悪い意味で言われているわけじゃないと、そのくらい分かっているけれど。陛下から一連の行動の意味を教えてもらった今では、ラスリーが嘘をついているわけじゃないと分かっているのだけれど。
「どうして今日はそんなに突っかかってくるんですか……」
「別に」
いや、いつも突っかかってくるのは、突っかかってきていたけど、今日はなんだか妙におかしい。変だ。それでも、これは、とても覚えがあった。
「ラスリー……手を貸して下さい」
はい、と彼の前に自分の手を差し出す。奇妙な顔をしつつも、ラスリーはテーブル越しに手を前に出して私の掌の上に重ねた。
「―――やっぱり……」
ぽむと置かれた手はいつもよりも温かすぎる。
「だから、まだ歩きまわるなといつも言っているでしょう。傷が完全には治ってないのですよ。だから、病室にいるのでしょう? どうして熱があるのに来たんですか! 余計に悪くなったらどうするのですか!」
「別に、熱はなかった」
「なら、今はあります。具合が悪くなったのなら、ちゃんと言いなさい。ただでさえ、ラスリーは昔から分かりにくいんですから」
熱が出たって、赤くなりもしなければ、青くなりもしない。普通に喋るし、食べるし、振る舞う。昔、倒れた時も、突然過ぎてアトラスと一緒に酷く驚いた。なぜなら、その少年は直前まで話をしながら私達の隣を普段通り歩いていたのだから。
「戻りますよ」
バツが悪そうに目をそらしたかと思えば、手まで引き抜こうとするから、置かれただけだった彼の手を握ってそれを妨げる。
「陛下に……いえ、アトラスに言いつけますよ!」
睨みつけて、握る手に力を込める。ここで見逃がすわけにはいかない。ラスリーが倒れて困るのは、いつも私達二人なのだから。
ようやく観念したのか、部屋の中には溜息が落ちた。
「全く……」
白を基調とした病室の中、ようやく眠りについたらしい病人に目を落とす。病室にはやはり前と変わらず書類がいくつかあって、これなら自宅で療養させた方がいいのではないかと思うのだけれど、そうしたら、宮廷まで出てきかねないとも思う。
「どうして貴方はいつもそうなのですか。私も陛下も、いい加減怒りますよ」
眠っているのだから話しかけても意味はないのだが、腹が立って仕方がない。正直すごくこの男を叩いてやりたかった。さすがにそれはできなくて、代わりにベッドの横にある椅子に腰かけて何とか衝動をやり過ごす。
横になっているのに、結ばれている髪のせいで寝心地が悪そうだったから、紐を抜き取って、そっと解いてやる。だけど、広がったままなのも、やはり、邪魔そうに見えたから、前に流せるようにゆるく編んでみることにした。
「大体、……」とラスリーの髪の毛を三編みにしながら、また一人呟いてしまう。
「どうして自分から虫のことを言い出すんですか。せっかく人が忘れてあげようとしているのに」
絶対に忘れられないことだとも分かってはいるけど。
それでも、別に私だって虫以外のことだって覚えているのに。
前にもラスリーの髪の毛を編ませてもらって、遊んだ。アトラスがしていることと同じことをしてみたかった私に勉強を教えてくれたことだってある。私もラスリーがいじめられているのを止めたことがあるけれど、私がいじめられた時もこっそりやり返してくれていたのを知ってる。
嫌な記憶以外でだって、きちんと覚えているのに。
「だって、なんだかんだ言って、いつも貴方はアトラスの隣にいたじゃないですか」
だから、結局あの後だって三人でいることの方が多かったじゃないですか。
「本当に貴方を見ていると、ときどきすごく腹が立ってしまいます」
ときどきものすごく悲しくなります。
あの時きちんと断ることが出来ていれば良かった。首飾りなど受け取らなければ良かった。
それでも、部屋にやって来るラスリーをちゃんと追い返すことができなくて。私は、今でも絶対にアイカが帰って来ると信じているから。
だから、言えない。動けない。
ずるいと分かっているのに、またここに留まろうとして、また見ないふりをしようとして。
同じことの繰り返し。巻き込んでしまっては、いけなかったのに。
編み終わった赤みがかった髪の束を解けないように紐で結んで、肩の上に流し置く。
「ごめん、な、さい……」
口にした贖罪は自分でも聞き取りにくい程に小さすぎて、今告げても仕方がないとも理解はしていて―――だけど、もっと早く口にしておくべきだったものなのだ。
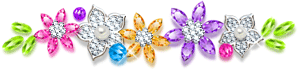

(c)aruhi 2009