飾り翅

その箱を発見してしまったのは、司祭様のところにやってきた客人に出す冷茶と茶菓子を盆に載せて運んでいる時だった。
きしきしと唸る廊下を歩いて客間へ向かっている途中、どこからか風が入ってくるのを感じた。ふと辺りを見渡してみると、普段は閉まっている資料部屋の扉が珍しく開いていたので、覗き込んだら見知らぬ箱が机の上に載っていたのだ。ただ四角いだけの白い箱。一体何が入っているのだろう、と疑問が頭によぎった時には、盆を床に置いて、よじ登るための椅子を机の前に引きずっていた。
椅子の上に立ち、充分に机の上が見下ろせることを確認して満足する。それから、俺は目的を果たすべく早速、白い箱の中を覗き込んだ。
蓋のない真っ白な箱。
底の浅い箱の中で、蝶がじたばたと翅を動かして窮屈そうに蠢いていた。何本ものピンで縫いとめられた蝶は、あがけばあがくほど徐々に力を失くしてゆく。
感嘆の息を零すことも、息を呑むこともでないことがあることを知った。それくらい圧巻された。
今まで見た中で、一番綺麗な蝶だった。
教会にあるステンドグラスにも似ている極彩色の翅。光を受けるごとにささやかに色を変える。
薄く繊細な翅から鱗紛が舞った。白い箱の底面がわずかに色づく。
けれど、それだけだった。
だから、ピンを外した。
蝶の体を縫いとめている楔を一本一本外してゆく。そうすれば、美しい鱗紛を散らすことなく、この蝶は翅を動かすことができるのではないかと思ったのだ。
「何をしている」
低い静かな咎めが背後から響いたのは、その時だった。驚いて、抜いたばかりのピンを手に持ったまま振り向くと、恰幅のよい紳士が眉間にしわを刻んでいた。何度か見たことのある顔だった。教会に支援をしてくれている人物だ。彼は礼拝堂だけでなく、孤児院の役割を持つ俺たちの居場所まで、定期的にわざわざ自らの足を運ぶ。
そんな人だから子どもたちが顔を出した方が喜ぶだろうと、言う大人たちは、彼が来訪した際には毎度、俺たちに盆を運ばせるのだ。ただし粗相のないようにとしっかりと念を押して。
だから初めに胸を占めたのはどうしようという思いで、口を開いてみたのはいいがどもってしまった。
「ピンを……」
「ピンを外して、蝶を自分のものにしようと思っていたのかい? これは君だけのものじゃないんだよ? ここにいる子どもたち、みんなの為に持ってきたんだ。独り占めしようなどと考えてはいけない」
「ち、違うよ。だって蝶が動いてたから逃げたいんじゃないかなって。逃がしてあげようと思って」
「蝶が……?」
紳士が片眉を吊り上げる。けれども嘘はついていない。蝶は固定された翅を動かそうとしていたんだ。びくびくしながらも、紳士の方を見上げ、こっくりと頷いた。
彼は蝶の入っている箱と俺を交互に見比べた。しばらく黙考した後、紳士は二度かぶりを振った。
「いや、まさか。この蝶が動くはずはないよ。これは始めから死んでいるのだから」
「嘘!」
紳士の言った言葉は信じられなかった。
「死んでなかったよ! だって俺、動いてるの見たもん」
「嘘ではないよ。きっと風で揺れたのをそう思ったのだろう」
紳士は目で開かれた窓を示す。確かに、この部屋は風通しがよい。風は絶え間なくそよそよと吹いていた。
「標本にする前に蝶は殺しておくんだよ。綺麗な形でとどめておかないとよい資料にはならないからね。生きたままだと君の言う通り動いてしまう。翅が傷んでしまったら標本としては何の意味もない」
「殺す? どうやって殺すの?」
「簡単だよ。蝶の胸を押すんだ」
そう言って彼は、自身の人差し指と親指で空気を押しつぶす仕草をしてみせた。
「それだけ?」
「そう、これだけ」
虚無とも言える空間を見つめる。向かい合う紳士は何も言わなかった。
「だ、だけど、でも! 鱗紛が箱の底に落ちたんだよ?」
「鱗紛が?」
問い返してきた紳士はそこで、ふむ、と自身の顎を手でさすった。それから、標本箱に閉じ込められ蝶を見やって、確認し始める。極彩色の翅を形成していた粒子は、変わらず白箱の底にわずかに色を落としていた。
「ああ、本当だね。虫がついているのかもしれない。早く取ってしまわないと」
それはどこか奇妙で現実味のない言葉に思えてならなかった。
あの人が言っていたことは本当のことなのだろうか。教会の裏手にある畑の葉の上を、行き交う無数の黄色い蝶を眺めながら考えてみる。整列するキャベツの一つに、一匹の蝶が翅を休めた。そっと、蝶に息をかけないように近づいて、両手で包みこむ。教会にある虫採り網なんてものが、俺たち子ども全員にいき渡るほど数があるはずもない。少なからずある網に関しても虫を採るためではなく、木の上に実る果実を採るために用意されているくらいだ。だから、網なしで虫を捕まえることには慣れていたし、誰にとっても造作のないことだ。
閉じ込めた手中で暴れる蝶を逃がさないようにと、手を開かぬまま指と指の隙間で蝶の翅を掴む。そのまま、ゆっくりと手を解いていってから翅を掴みなおした。薄い翅は破れそうに見えて、意外と頑丈でもある。翅を掴まれた蝶は、体をくねらせて抵抗を示し続けた。
動く蝶の体の中心、紳士の言っていた蝶の胸を人差し指と親指で押してみる。
すると、あれだけ暴れていた蝶は、本当に呆気ないほどぴたりと動かなくなってしまった。
***
「見て見て、アトラス、ちょうちょ!」
手をめいいっぱい伸ばして、リシェルは碧い蝶の後を追った。
ひらひらと、蝶に合わせて動くリシェルの手の方がよっぽど蝶のように見える。
小さな少女が庭園を走り回る姿を目で追っていたアトラスは「うん」と頷いて苦笑した。
とても暑い日だった。風も吹かない真夏の晴天日。あの日のことは十数年たった今でもはっきりとよく覚えている。
その日組まれていた授業の一切が前触れもなく急に取りやめとなった。一課が他の科目と入れ替わったり、休講となったりするのはまれではあるがたまにある。アトラスと授業をさぼって自主休講とするのも幾度かはあった。だが、全科休講になることなど、そんなことは初めてだった。
何かあったのか、とアトラスに聞こうと思っていたのだ。しかし、尋ねるよりも先にアトラスから「リシェルを誘って庭園に降りよう」と提案されてしまった。だから、結局尋ねる機を逃したまま庭園に赴くこととなったのだ。
碧い蝶は、音もなく一輪の花に止まった。ただ、蝶が降り立ったというその証拠を示すように、薄桃の花びらがかすかに揺れた。
蝶はくるくると巻いていた管を、黄色い花芯に差し入れて蜜を吸う。外側の地味な翅色に対比され、内側の碧色はより一層艶めかしく映える。
「すごくすごく綺麗ね。サファイアみたい」
リシェルはうっとりと蝶が蜜を吸う様を見つめていた。
「そんなに綺麗?」とリシェルに問いかけると「はい」と元気よく頷かれる。そういうものだろうか。カナブンの翅の方が虹色に見えてよっぽど綺麗なのに。けれども、瞬きすらせずに、蝶の一挙一動を見守っているリシェルにしてみれば、この蝶の方がはるかに綺麗に見えるのだろう。
「お部屋に飾っておけたらいいのに」
「なら、とってあげようか?」
尋ねてみると、リシェルの顔がぱっと輝いた。「本当に!?」と期待に満ちた表情でこちらを見てくる。
「うん、だって飾るのなら標本にした方がいいだろう?」
「ひょうほん?」
リシェルは首を傾げた。
「けど、ラスリー。網なんかないぞ?」と、アトラスが言う。
「別に。今だったら、楽勝だよ」
蝶は甘い蜜にばっかり気をとられているのだから、ただ花にとまっているだけよりも断然捕まえやすい。蝶を両手で包みこんで捕える。逃げないようにと胸を潰して、「はい」とリシェルの前に差し出した。
「うまいな」
掌に載っている蝶を見て、アトラスが感心したように呟く。
「そうやったら止まるのか。初めて知った。どこで習ったんだ?」
「えーっと……?」
問われて気付いた。記憶を探ってみるが、どこで習ったのかまでは覚えがない。知らぬ間に知識として入っていた。
「たぶん教会じゃないかな? 蝶もよく捕まえていたはずだし」
あの場所で過ごした思い出は希薄そのものだ。やけにはっきりと記憶に焼き付いているのは、ステンドグラスの光の加減くらい。だから、思い出せぬ記憶は大抵あの場所から持って来たものなのだろうと思う。
「司祭あたりが教えてくれたんじゃないか?」
「まさか」とアトラスは一笑する。その隣で、未だきょとんとした顔で掌上の碧い蝶を見ていたリシェルは不思議そうに言った。
「ラスリー? このちょうちょどうしちゃったの? さっきまではあんなに翅を動かしていて綺麗だったのに」
「え? だって、もうこの蝶は動かないよ?」
「え?」と、リシェルは蝶から目を離して顔を上げる。大きく開かれた若草の瞳は、理解が伴っていない驚きに占められていた。
「どうして? どうして動かなくしちゃったの?」
「え、どうしてって……」
食いかかってくるリシェルをどうすればいいのか分からなくなり、アトラスに助けを求めようと目線をやる。と、同時にリシェルは、わぁっと泣き出してしまった。
「え、どうしよう、どうすればいいの、アトラス」
泣きじゃくるリシェルの目からは大粒の涙が面白いくらいぼろぼろと零れ落ちる。だから、余計にどうすればいいのか分からなくなって、あたふたと慌てるしかなかった。
「あー……」とアトラスは、困ったような苦笑を口元に浮かべ、リシェルの前に膝をつくと彼女の両手をとった。
「そうか。リシェルは翅を動かして蜜を吸っている蝶が好きだったんだな」
アトラスが確かめるように問いかけると、リシェルはひっくと大きな嗚咽を漏らして、こくりと頷いた。
「部屋に蝶を飾った後も、時々部屋の中を飛ばしてそれを見たかったんだろう」
再度の問いかけに、リシェルはこくこくと頷く。だから、拍子に彼女の顎からも涙がぼたぼたと落ちた。
「だが、ラスリーは何も悪くないんだぞ、リシェル。リシェルが“飾りたい”と言ったのがいけなかったんだ。こうでもしないと、蝶は部屋には飾れないんだよ? 生きたまま連れて帰ったって、きっと蝶は窓の隙間から逃げて行ってしまうだろうし、そうでなくても衰弱して結局最後は今みたいに動かなくなるだろうな」
分かるか、リシェル? と、アトラスは落ち着いた声で問う。リシェルはやはりアトラスの問いかけに頷いた。「なら泣くのはもうやめだ」と、アトラスは掌で、リシェルの頬についた涙を拭った。それから、俺の方を見て「だから、ラスリーもそんな顔するなよ」と言う。
「俺がきちんとリシェルに確認しなかったのが悪かった。ラスリーはこれっぽっちも悪くない」
「いや、でも……アトラス」
「ラスリー。それ、くれないか?」
「へ?」
珍しく突拍子のないことを言う。だから、“それ”が指しているものが、俺が思っているものとは違うものなのだろうと思った。だが、アトラスが指差したのは蝶以外の何物でもなかった。
「だから、その蝶。きっと母上のところへ持っていったら喜ぶ」
「ああ……」
アトラスの母――フィラディアルの王妃は数カ月前から床についている。朗らかな微笑と共に宮廷を渡り歩いていた彼女が、大病を受けて床から起き上がれなくなるまでそう時間は要さなかった。王妃殿下もまた庭園に出ることが好きだったのだ。
「それなら、俺が持って行くよ。今から王妃様のところに行くんだろう?」
「……そうだな。もうそろそろ行かなければならないよな」
「王妃様のところへ行くの? なら私も行く!」
まだ目の端に涙を残してはいるものの、リシェルはさっきと打って変わって嬉しそうに笑みを零した。早く早く、とアトラスの手を引っ張る。宮廷とは逆の庭園の奥隅へとリシェルは足を向けた。少女が一体どこに向かおうとしているのかに気付いたアトラスは、「今日はこっちからじゃ入れないんだ」と、逆に小さな手を引いて、宮廷に続く道へと進んだ。
複雑に絡み合った蔦の上に、幾羽もの小鳥が足をかけて羽を休める。蔦の至る所には小粒の実が実っていたが、ついばもうとしている小鳥は一羽もいない。丁寧な彫が施された滑らかな白い扉――王妃の寝室に通じる扉を三人でくぐる。
普段なら声を掛けてきては、菓子の用意をし始める大人たちは、今日は静かに目を伏せ、王太子であるアトラスに辞儀をした。
「――父上は?」
「先ほどお戻りになりました」
「そう」
貸して、とアトラスは碧い蝶をとった。陽光のない部屋の中で、翳りを帯びた翅は黒に見える。それでも、わずかな光を受け微細に色をかえるのは変わらない。けれども、綺麗なはずの蝶の翅はなぜか底のなし沼を彷彿させた。
王妃様は常と変らず、寝台に眠っていた。この頃は、目を覚ましていることすら少なかったから、別に驚くことでもない。だが、背筋を走ったものにぞわりと信じられない思いを抱く。
アトラスは、自分よりも色素の淡い母の亜麻色の髪に、そっと蝶を止まらせた。碧色の蝶は翅を開いたまま沈黙をもたらす。
ただ一人、リシェルだけが寝台の淵に身を乗り出して、「王妃様、綺麗!」と無邪気に顔をほころばせた。
リシェルの言う通り、それは、子どもの俺から見ても本当に美しすぎる姿だった。
窓から入ってきた生ぬるい風が、室内のひんやりとした空気と混ざる。
「アトラス……王妃様……」
「ああ、今日の早朝に」
先を引き取って、答えたアトラスの声は驚くほど静かだった。
隣に立つ友人は微笑をしているのに、彼が持つ青い双眸は悲哀に満つ。それでも、アトラスは落ち着きを保って、穏やかにリシェルの姿を見ていたから、また何も聞けなくなった。
やっぱり、とだけ思う。できれば当たってなど欲しくはなかった。今日の授業が全科取りやめとなったのが、この為だったらしいことは明白だった。
なぜか怖いと思ってしまったのだ。王妃様の姿を見た瞬間に。
目の前にいるのは、周りにいる誰をも愛して、誰からも愛された女性。とても優しかった人。俺がこの場所に招かれるきっかけを、アトラスと出会うきっかけをくれた人。そして、リシェルを俺たちの前に連れてきてくれた人。
なのに、怖いと思ってしまった。温かな笑みが向けられることはもうないのだと気づいてしまった。作り物めいて見える肌は触れてもいないのに、ぞっとするほど冷たいのが見て取れてしまった。これは、王妃様なんかではない。まるで蝋人形のような姿に恐怖している自分がいた。とても大好きだった人のはずなのに。
髪の色と同じ王妃様の睫毛が一度だけ風に揺れた。同じ風を受けて、髪に飾られた碧い蝶も翅をそっと揺らす。
「アトラス……」と、横に立つ友人に呼びかける。声はほとんどかすれてしまったけれど、なんとか絞りだせたことにほっとした。
「どこか……フィラディアルとは違う遠い国では、蝶が魂を運んでくれるんだって、前に聞いた。だから……」
きっと大丈夫だよ、と言おうとして、何が大丈夫なんだろうと思った。だけど、アトラスは「ありがとう」と言ってくれたから、泣かないように奥歯を噛み締めた。
リシェルはまた大声で泣いた。
葬儀の場で、途中で外に連れだされてしまうくらい、小さな体全部を使って泣いていた。
彼女もまた彼女なりに、王妃様が蝶と同じように動けなくなってしまったことを理解したのだ。
侍女たちに手をひかれて、聖堂を去るリシェルをアトラスは目を細めて追っていた。だから、きっとリシェルはアトラスの分も泣いてくれたのだろう。俺には、それができなかったから。
棺も衣装も、何もが白いものに満たされた中で、王妃様の髪に飾られた蝶の翅色だけが鮮やかだった。
***
秋の庭園は、深みが増す。
秋の終りには葉を落とす落葉樹が一斉に色を塗り替え、色とりどりの木の実がたわわに実る分、もしかすると春よりも庭園に映る色は鮮明なのかもしれない。
「ねぇ、ねぇ、王様」と、一見普通の少女にしか見えない異国の女は、アトラスに声をかける。
瞳と同じ、黒い髪に碧い蝶が音もなくふわりと舞い降りた。「どうした?」と答えつつ、アトラスは手で軽く黒髪から蝶を払う。
一連の動作に不自然なところは何もなく、アイカは「あのね」と目元を和らげてアトラスに再び話しかけた。と、彼女はひらひらと舞う蝶に気付いて、歓声を上げる。
「わっ! 見て、王様。ちょうちょ!! すごい! こんなに鮮やかな蝶なんて初めて見た」
「ああ、綺麗だな」
アイカは子どものように両手を空へと伸ばす。蝶に触りたいのか、上げた両手をばたばたと動かした。真剣に蝶に手を伸ばしている彼女を見て、アトラスは眩しそうに笑って噴出した。
「――リシェルも見ていたのか?」
すぐに庭園に降りることのできる一階の回廊。アトラスたちから目をそらして、向かい側へと歩いていたら行きあったのはリシェルだった。固く口をつぐんだまま、庭園にいる二人を眺めていたリシェルは、こちらに気付いて振り返る。
「それなら、ラスリーも見ていたのですか」
是、とは答えずただ微笑むことを試みる。すると、彼女は苦笑を閃かせた。「そうですか」とリシェルは、呟いて再び庭園にいる二人に目を向ける。
「蝶は綺麗ですが、あまり好きにはなれませんね。アトラスが悲しそうに見えてしまう時は昔から嫌いです」
「特に碧いのはな」
「ええ」
リシェルは、目を伏せずに二人を見据える。どこか決然として見える横顔は、彼女が幼かった頃にはほとんど見られなかったものだった。
「……時々、アトラスよりも歳が上だったら何か違っただろうかと思ったことがある」
「ラスリーの方が、ですか?」
「そう。そうしたら、アトラスももっと楽だっただろう」
今はともかくとして、昔はアトラスを頼ってばかりだったような気がする。それは恐らく間違いではないのだろう。けれど、リシェルは「そうでしょうか」と首をひねった。
「きっとあまり変わらないと思いますよ。できることなど限られているという事実に変わりはありません。アトラスはアトラス。ラスリーはやっぱりラスリーです。むしろ、ラスリーが陛下よりも年上だった方が、陛下は大変な思いをしそうです」
子どもの頃の貴方は本当に酷かったですよ? と彼女は続ける。
「私に関すること以前に、ラスリーは他の子たちに泥団子を投げつけていたじゃないですか。アトラスが止めに入ったのを覚えていないのですか?」
「あー……忘れた、ということにしておいてくれ……」
「忘れるのは難しいですね。あんなに泥だらけになった人たちを見たのは初めてでしたから」
リシェルはクスクスと笑い声を洩らす。纏いつく空気が少し軽くなった気がした。
「ねぇ、ラスリー? 私たちにはあんな風に陛下を笑わせることはできませんね。それだけ、私たちはアトラスの傍にいたんです。きっと何も知らないアイカだからできることです。アイカだからできたことです。私たちはどうしても陛下と同じものを見てしまうから……」
リシェルは、ふっと言葉を切った。「そろそろ行きましょうか」と微笑む。
それでも、と言わずにいられなかったのは、あの日アトラスがリシェルに救われたはずだということも知っていたからなのだろう。
「ならば、俺たちにしかできないこともあるんだろう。アイカはアトラスが蝶を払ったことを知らない。だけど俺たちは知っている。アトラスがとまらせたくないと思うのなら、絶対にとまらせたりなどしない。だろう?」
リシェルは、若草の双眸を瞠らせた。だが、それも一瞬のこと。意味を咀嚼するまでもなく彼女は「もちろんです」と頷く。
それは、とても力強いもので、つい破顔せずにはいられなかったのだ。
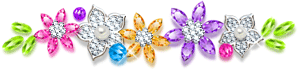

(c)aruhi 2009