four o'clock 1:そもそもの始まりは

彼女は突然現れた。
「陛下、その娘御は……?」
担ぎ上げられ、何とか逃れようと暴れる少女。
見たこともない奇妙な服装、縮れた黒い髪、恐怖に慄く黒の瞳。
逃れようもないのにじたばたと狂ったように手足を振りまわしている。
その少女を青色の目がちらりと見やる。
暴れ続ける少女が逃げないよう、がっちりと抱え上げたまま陛下は困ったように私に向き合った。
「街で拾って来た……」
「街で、ですか?」
聞きたい部分はそこではない。どうして拾って来たのかだ。なのに、口をついたのはどうでもいい方だった。
陛下が街へ視察に降りたことなど知っていたのに。拾うとしたらそこしかないのに。たぶん私も呆気にとられていたのだろう。
「黒髪黒眼なんて珍しいだろう、見世物屋に無理やり連れて行かれそうになった所を拾ったんだ」
「然様ですか……」
猫や犬を拾って来たかのように告げられた言葉にそれ以外どう反応すれば良いのか分からなかった。
曖昧に頷いたその時、埃で薄汚れた細い手が一層激しく揺れたかと思うと、振り下ろされた。
「―――陛下!」
歪められた青の瞳の下、頬に一筋の線が入り、赤いものがジワリと浮き出る。
それを見た黒の二つの瞳がひどく揺れていた。
「なんと無礼な」
一斉に少女へと向けられた剣。背後に控えていた護衛達を彼は空いていた右手で制した。
「大したことではない。あんなことがあった後だ。気が立っているのだろう」
陛下は抱えていた少女を抱き上げるとふわりと床へと降ろした。
焦点の定まらないほど辺りをさまよい揺れ動く瞳。光を映さない黒い瞳。
両頬を大きな手で包み込まれ、少女はびくりと体を震わせた。
彼は少女の瞳を、自分の瞳を、互いに映すように覗き込んでいた。
「大丈夫だ。もう、恐くはない。もう、何も起こらない。俺達はお前に危害など加えない。だから安心しろ」
静かに諭すように落とされた低い響きに黒の瞳は動きを止めた。
はじめて、目の前の人物を見たかのように青の瞳に焦点を定め、黒い二つの瞳には光が宿った。
少女の体の震えが止まる。
それを確認したかのように陛下は彼女の頬から手を離すと、今度は絡まった黒い髪を手で掻き梳きながら私へと少女を向き直らせたのだ。
「リシェル、彼女にとりあえず湯あみをさせてやってくれ」
「それなら、途中で会った侍女に頼んだ方が早かったでしょうに……」
「一番信用が置けるのはリシェルだ。リシェルが信用している侍女の方が信用できる」
向けられた笑みに頬が上気するのが自分でも解ってしまった。
気付かれないようにと慌てて視線をそらす。きっと気付かれているのだろうけれど。本当に陛下はずるい。
「……本当にお上手ですこと」
「事実だ」
「―――分かりました。このエリィシエル、責任を持って彼女を引き受けましょう」
軽く頭を垂れた私に彼は満足そうに笑むと、黒髪の少女を差し出した。
陛下から、今度は私へと引き渡され、黒の瞳がまた不安げに揺れ始める。
「大丈夫ですよ。貴女の体についた埃を落とすだけです。それから、新しい服も用意させましょう」
微笑むと、少女は少し安心したのか黒い瞳の揺れを止めた。
どうぞこちらへ、と前を歩く私の後ろを恐る恐る、しかし確実について来る。
彼女は二、三度、陛下の方を振り返っていたようだったが前を歩く人物との距離に気付くとパタパタと駆け寄ってきて、私の少し後ろへと付いて歩き出した。
これが、彼女、アイカとの初めての出会いだったのである。
第一印象は驚愕と珍しさが大きすぎて何だったのかよく分からない。
けれど、ちょこちょこと付かず離れず後ろを歩く黒髪の少女が親鳥を追いかける雛のようで愛らしかったのを覚えてる。
幼さの残るあどけない顔に不安をいっぱい詰め込んで、それでも必死に付いて来る彼女に思わず笑みを零してしまったのも覚えてる。
だからこそ、私は気付かなかったのだ。
いいえ、きっとその可能性には気付いてた。けれど、無意識のうちに気付かないふりをしたかったのかもしれない。
これから、彼女がもたらすことを。
当たり前だった王城での日常がすっかり崩れ去ってしまうということを。
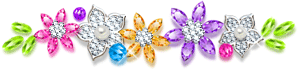

(c)aruhi 2008