four o'clock 2:黒髪の少女

「ギャーやめて! できる、できるから! 自分でするってばぁー!!」
さっきまで暴れるだけで口を開かなかった少女は侍女と共に湯浴みに向かわせた途端大声で叫び再び暴れ出した。
「エリィシエル様……」
侍女頭であるユージアは決して主人である私に逆らうことなどできない。けれども申し訳なさそうに呟かれた彼女の言葉は主人への訴えを切実に表していた。
普段は崩れることのない完璧な服装がヨレヨレになってしまっている。白い布で一つにまとめ上げられた金の髪にはほつれが覗いていた。
ユージアの姿そのものが湯殿での騒動の悲惨さをはっきりと物語っていた。
「―――分かりました。好きなようにさせてあげなさい」
ユージアはあからさまに安堵すると礼をして湯殿へと向かう。彼女の命に従い次々と侍女たちが出てきた。皆ユージアに負けず劣らず、ぼろぼろでぐったりとしていた。こんな姿の侍女たちなど初めて見る。
「エリィシエル様、笑い事じゃありません。一体あの少女は何者なのですか?」
「ふふっ、ご免なさい。でも可笑しくって。あの娘は陛下が拾ってきたのよ。なんでも売られそうになっていたとか。よほど恐ろしい目にあったのでしょう……。だから大目に見てあげて頂戴」
「エリィシエル様がそうおっしゃるのなら……」
そう言って壁に引き下がったユージアへと笑みを向ける。
「貴女たち本当にひどい格好よ? きっと、もう少ししたら陛下があの娘の様子を見にお寄りになるでしょうから今のうちに身なりを整えていらっしゃいな」
「そんなことはできません! 危険すぎます!」
一斉に抗議し始めた侍女たちに、彼女たちにここまでさせるほどの何が中で起こったのだろう、と浴場へとつながる扉の方へと目を向ける。
「大丈夫よ。湯浴みをしているのだから後一時間ほどは出てこないでしょう。だから、安心して着替えて来て頂戴。あ、タオルと下着だけは出しておいてあげて。ドレスは彼女が湯浴みを終えた後、私が見繕いましょう」
「しかし……」
尚も食い下がろうとする彼女達を追い出し、椅子へと座った。皆が戻ってくるのにも、まだ少し時間がかかるだろう。けれど、少したまっている書類の仕事はする気にはなれず、それは明日に回すことにして、久しぶりに本でも読もうかと立ち上がって書棚へと向かう。
「あのお……」
タオルを体に巻きつけたまま彼女が顔を浴場への扉から顔を出したのは、ようやく選びだした一冊の本を開こうとしたその時だった。
水分を含んだ肩下ほどまで伸びる黒い髪からは、雫がぽつぽつと床に零れ落ちている。
予想よりもずいぶんと早く出てきてしまった彼女に驚いていると、彼女が再び口を開いた。
「私の服は……?」
「―――あぁ、貴女の服は洗濯場へ持って行かせたわ」
「え? でも、あの……じゃあ、どうすれば……?」
「そこに、下着を置かせておいたはずなのだけど、無いかしら?」
私の言葉に彼女は浴室の方へと引っ込んだ。
「―――あ、これ、ですか?白い長いワンピースみたいなの」
―――ワンピース?
その言葉が何を指すのかはよくわからず、首を傾げる。
「えぇ、恐らく合っていると思うわ。それを着て出ていらっしゃいな」
出てきた黒髪の少女を、椅子に座らせる。
彼女からタオルを受け取り、濡れた髪を拭いてやっているところにユージアが戻ってきて、慌てて私からタオルを取り上げると後を引き継いだ。
黒い髪に櫛が通る。真っ直ぐに流れた髪。一見光とは無縁と思える真っ黒な髪は、しかし、光を受けて輝いていた。ユージアが施した香油によってその輝きがさらに増す。例えるならば黒真珠だろうか。
ユージアにすることを盗られ、手持無沙汰となった私は彼女の向かいに座って、彼女の髪が光を含んでいくその様を眺めていた。不躾に自分を見つめる私に戸惑ったのだろう。戸惑いを露わにしてちらちらと私の方へ黒い目を向ける少女に、私は微笑みかけた。
「貴女の髪は綺麗な色をしているのね。それに真っ直ぐで。羨ましいわ」
彼女はぽっと頬を赤らめ、首を振った。
「―――そんなことないです。だって、貴女の髪の方が綺麗。金色で、キラキラしてて」
「有難う」と礼を言うと、少女は小さくではあるが初めて微笑んだのだ。
「そうだわ。ドレスを取ってこないといけなかったわね。そうねぇ、貴女は何色がお好き?」
「水色、が好きです」
「だめよ、貴女、分かってないわね。貴女にはピンクの方が似合うわ。ユージア、メルアのピンクのドレスを」
「はい」と少女の髪を編む為の飾りを用意していたユージアが出ていく。取り残された彼女はどこか複雑そうな顔をしていた。
「……重い」
淡いピンクのドレスを着た彼女の第一声がこれだった。
「そうなのよね。メルアの生地は上質で丈夫だけど少し重いのが難点だわ。飾りも少し多すぎるのかもしれないわね。でも、よく似合ってるわ」
腰につけられたドレスと同じ色の大きなリボン。ドレスの裾はふわりと広げる為に布が重ねられている。
ドレスに施されていたどの飾りも少女の愛らしさを際立たせていたが、やはり何といっても最もその役目を担っているのは、ほんのり染まった花びらのような淡いピンクの色そのものだろう。彼女の白い肌、黒い髪とあいまって彼女の魅力を存分に引き立てていた。
そこへ身なりを整え終えて戻ってきた侍女たちが加わり、更に少女の髪を纏め上げていく。
最後に花の蕾を模した金色の簪を挿したのと同時に部屋の扉が叩かれた。
「これは、また愛らしくなったな。やはり、リシェルに任せて正解だった」
向けられた笑みに謝辞を述べ、軽く礼をする。
陛下を見上げ、呆けたままの黒髪の少女を軽く突く。
「ほら、貴女。陛下に礼を言いなさい。街で助けていただいたのでしょう?」
その言葉にハッとして慌てて彼女は頭を下げた。
「あ、有難うございました。……それから」
黒い瞳が再び陛下へと向けられた。
「それ、すみませんでした。傷、大丈夫ですか?」
「―――あぁ。」
陛下は今思い出したかのように頬に走る線に触れると笑った。
「問題ない。すぐ治るから気にするな」
「お前はどこから来たのか?その顔立ちはこの辺の国で見るものじゃない。大分遠くから来たのか?」
席に着き、三人それぞれが向かい合う形で座る。ユージアの入れた茶を一口飲んだ後、口にされた陛下の問いに少女は困ったような顔をした。
「遠いって、いったら遠いのかな……? どうなんでしょう?」
彼女の言葉に、私と陛下は顔を見合わせた。
もしかして――
「記憶喪失か?」
私達の懸念に、けれども、彼女は首を振った。
「いえ。そうじゃないんです。ただ、ここがどこかわからなくて……。ヨーロッパ、とかじゃないですよね?もし仮にそうだとして、いくらなんでも今の時代、こんな中世風ではないだろうし。時代超えちゃってるって事はないよね……?」
だんだん小さくなっていく声。それは私たちに尋ねるというよりも、どこか自分で確認しているように思われた。
そんな彼女に陛下がこの国の名を告げる。
「ここはフィラディアルだ」
「フィラディアル……」
やっぱり、と、半ば諦めを宿した呟き。視線を茶へと移した彼女は、カップを持つ手に力を込めて、泣き笑いのような顔をした。
「私は、たぶん、こことは別の世界から来ました」
―――別の世界
彼女の言っていることが理解できず、言葉を失った私たちに彼女は続けた。
「どうやって、ここに来たのかは解りません。だって、私は大学から帰って来て、家でちょっと昼寝してたはずなんですよね。なのに、起きたら道の真ん中に倒れてて、しかも訳もわからず、おじさんたちに連れて行かれそうになるし……。訳がわからなくて混乱してる所に、貴方に担ぎあげられて、でも、助けられたなんて、その時は分からなくって、貴方もおじさん達と同じだと思ってたので。……すみません」
「いや、それは悪かったな。確かにあまり説明せずに連れてきたからな。誤解するのも当り前か」
彼女は首を振った。
「いえ、助けていただいて本当に有難うございました。多分貴方に会えなかったら、もっと混乱していました」
別の世界から来たということ。それは容易に信じられるような出来事ではなかった。そんな話など一度も聞いたことがない。
けれど、認めれば多々説明がつく。見たことのない顔立ち、身につけていた奇妙な服、さっきから時々発せられる不可思議な言葉。そのどれもが、この世界には見受けられないものだった。
だけど――――
「貴女はずいぶんと落ち着いているのね」
確かにさっきまで彼女は狂乱していたと言っていい。けれど今は波が引いたように、驚くほど静かに、ただ、横たわる事実を、直面しなければならない現実を受け止めているように見えた。
もし、私がこことは違う全く別の世界へと落とされてしまったら、そんなことできるだろうか?
私の率直な疑問に彼女は苦笑しながら答えた。
「落ち着いている……といえば、そうかもしれませんね。実は自分でも冷静な自分にちょっと驚いてます。本とかで、ある日突然異世界に飛ばされるっていう話を読んだ時、よくすぐ適応できるなって突っ込みいれてたんですけどね。自分がその立場に立たされてみると、何が起こってるのか全く分からないし、これからのことも、やっぱりどうすればいいのかわからないし、これ以上悩んでも、苦しいだけで、実際には意味ないなって。どうしようもないか、って諦めちゃった自分がいるっていうのが本音です。寝たらここに来ちゃってたんで、もう一度寝たらあっちに戻れてると一番いいんですけどね。たぶん、それは難しいだろうなってことも分かってます。」
「そう。貴女はまだ小さいのに強いのね」
「―――ちょっと待って下さい!? 小さいって私もう20です。大人です。これでも」
「私と同じ年!?」
隣では同じく陛下も驚いていた。どう見ても少女にしか見えなかった彼女は20歳だという。別の世界からやって来たと聞いた時と同等の驚愕がそこにはあった。
彼女は少し不服そうに口を開いた。
「そこまで、驚かれると、さすがに傷つきます。私の国の人は確かに外国の人から見ると幼く見られがちですけど。その中でも私は童顔な方ですけど……」
「ごめんなさいね、悪気はなかったのよ」
「あ、はい、それは、分かってるので、大丈夫です」
彼女はそう言って微笑んだ。そこに不快感はもう感じられなかった。
「そうだ、お前、名は何と言う?」
「中村愛花です」
「ナカムラアイカ。ずいぶん変わった名前だな」
「いえ、私の国ではいたって普通のありふれた名前です」
「陛下、ナカムラアイカを城に置いてやってはいかがでしょうか? ナカムラアイカもどうすればわからないと言ってますし、何の知識もないまま外へ出すのは危険でしょう。なんなら、ナカムラアイカのことは私が責任を持って、このままいろいろとお世話をいたしますし」
「うん、そうだな。ナカムラアイカもその方が安心だろう」
案を出した私に、頷いた陛下に、彼女は変なものでも見るような目を向けた。
「あの、中村が名字で、名前は愛花です」
「短いな」
またもや驚く私たちに彼女は口を尖らせた。やはり、実年齢よりもずいぶんと幼く見える。
「私の国ではこのくらいが普通なんです」
「そうなのか?」
私は近くにあった紙にアイカと聞こえた通りの綴りで書きつけた。
「“アイカ”って、こう書くのかしら?」
けれどアイカは紙を覗き込むと首を振った。私からペンを受け取ると何やら不思議な文字を書きだした。
「“愛花”って書きます。母が花が好きなので、皆を、花を愛でるように愛して欲しいって意味で愛花。こっちのが、“愛”っていう意味で、こっちのが“花”という意味です」
紙に書かれているのは、不思議な記号のようなものだった。カクカクしていると思ったら、丸くなったり、短かったり、長かったりする線の組み合わせ。“アイカ”なのにたった二文字しかない不思議。
「変わった文字ね……」
「私には貴女方の文字の方がよっぽど不思議です。丸っこくて、可愛いけど」
「言葉は通じるのに、文字は全く違うんだな」
陛下は感心したように二つの文字を見比べていたが、「そういえばこちらの名前をまだ言ってなかったな」と、言葉を続けた。
「俺はアトラウス・デル・カリーア・フィラディアル。一応、この国の王だ」
「……長いですね。一体どれが名前かわかりません。というか王様って、普通街を歩いてるものなんですか?」
素直な感想に陛下は苦笑した。
「名はアトラウスだ。アトラスと呼ぶ者もいる。アイカの好きに呼ぶといい。街は月に一度は出てるし、珍しいことでも何ともない」
「陛下は街に降りられることで、実際に街の情勢を確かめてなさるのです。私の名前はエリィシエル・ノウラ・ディ・アリュフュラスです。名はエリィシエル。でも、リシェルと呼んでくださると嬉しいです。親しい方は皆そう呼んでくださるので。歳も同じことですし、仲良くしてくださいね、アイカ」
微笑むとアイカは嬉しそうに頷き返した。
「リシェルはこの国の大貴族アリュフュラス家の姫だ。リシェルが傍にいてくれるなら、何も心配することはないぞ。何かあったら、リシェルに何でも聞くといい。そうだな、リシェルがいいなら部屋も隣に用意させよう。その方が安心だからな」
「ええ、それで、構いませんわ。入用なものは私が手配いたしましょう」
私に向かって陛下は「頼んだ」と頷き、アイカの頭にポンっと手を置いた。
「アイカも今日は色々あって疲れただろう。何も気にしなくていいから、ここでゆっくりして、元の世界に戻る方法を見つければいい」
そう言って、席をたった陛下をアイカは呼びとめた。
「王様!」
「何だ?」
「本当に今日は色々有難うございました。リシェルもこれからも迷惑かけると思いますがよろしくお願いします」
陛下は微笑むと、もう一度アイカの頭をぽんぽんと叩き部屋を後にした。
その背を見送りながらアイカは手を自分の頭へと持っていった。
「なんか、やっぱり、子供って思われてる気がする……」
複雑そうな顔をするアイカを見て、私はクスクスと笑う。
「そういうわけじゃないのよ。陛下は私にもして下さるし、きっと、アイカのことを心配してくださったのよ。それよりも、まずはアイカのお部屋へ案内いたしますわ」
アイカは頷くと、席を立った私に続いて、立ち上がった。
出会った時と同じように、ちょこちょこと後を付いて来たアイカに私はまた笑ってしまったのだった。
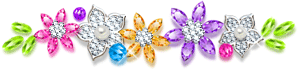

(c)aruhi 2008