four o'clock 8:今、あなたを想う

一つの扉の前に立ち、二度、コンコンと叩く。
中から「いいよ、私が出る」という、少し高めの声が聞こえ、アイカが顔を出した。
少し緊張を宿した彼女に向かって、微笑む。
「アイカ、ちょっと話せるかしら?」
すぐに快諾してくれたアイカを、私は庭園へと誘った。
こうして、彼女と一緒に庭園を歩くのはずいぶんと久しぶりだ。
咲き誇る花々は、初めて彼女とこの場所に降りたった時とはいくらか様変わりしている。
彼女が白い粉を顔につけて遊んでいた白粉花はとうに花の季節を終え、今はもう緑の草が生い茂るばかりである。
淡い緑をそのつぼみに宿していたバラも、満開に咲き乱れ、その純白さは他の色を宿していたことさえ嘘のようであった。
庭園の隅、空いているテラスを見つけて腰を下ろす。
対するアイカの漆黒の瞳を見ながら私は口を開いた。
「アイカ、この間は酷いことを言って御免なさい。それだけ、謝りたくて……」
そう言うと、アイカは慌てたようにぶんぶんと手を振った。
「そんな、リシェルは謝ることなんてないよ。私、知らなかったんだ。リシェルが王様の妃候補だってこと。でも、だからって、許されるようなことじゃないよね、だから私こそ、ごめ―――――」
「待って」
私はアイカの言葉を遮った。
その先を聞く必要はない。
「謝らないで。別にアイカは悪いことなどしてないわ。貴女が私に悪いと思っているとしても、それは悪いことではないでしょう? それとも、貴女は悪いことをしたの?」
アイカは一瞬押し黙った後、しっかりと私を見据えた。
「ううん、してない」
「そうでしょう? 貴女は私が陛下の妃候補であることを知っていたら、陛下のことを好きにはならなかった?」
「ううん。きっと知ってても、私は王様のこと好きになってたと思う。」
「ね、やっぱりそうでしょう?それなら、貴女は謝ることなんてない。陛下も言っていたことだけど、陛下が愛したのがアイカ、貴女だったというだけよ。それは、私にはどうしようもできない。仕方のないことだわ」
「王様、そんなこと言ってたの!?」
「ええ。それに陛下は、私が陛下のことを好きだと思っているはただの錯覚だなんて仰ったのよ」
「何それ!? 王様、酷すぎる!」
「ね、酷いでしょう? でも、それだけ陛下はアイカのことしか見えていなかったのね」
クスクスと笑いながら、そう言うとアイカは一瞬にしてその顔を真っ赤に染めた。
彼女のこんな表情を見るのも本当に久しぶりである。
「負け惜しみに聞こえるかもしれないけれど、私は陛下が愛したのが貴女でよかったわ、アイカ。だって、私もアイカのこと大好きだもの。嫌いになりたかった。そしたら、きっとすごく楽だったわ。だけど、やっぱり貴女のこと、私は大好きみたい」
これ以上ないくらい真っ赤になりながら、アイカは照れたように「有難う」と笑った。
自然と言えたことに、彼女の言葉に、私も満足して微笑む。
そこにわだかまりなど、一つもない。
これが私の本心のだと、今ならはっきりと言うことができた。
それくらい、私の心は晴れ晴れとしたものだった。
「私、あの時リシェルが私のこと庇ってくれて本当に嬉しかった。嫌われてるって思ってたからよけい……。有難う」
照れたようにうつむいたまま、へへっと笑ったアイカは「私ね」と言葉を続けた。
「もうすぐ、元の世界に戻りそうなんだ。」
「―――え!?」
突然告げられた言葉に衝撃を受ける。
それは、彼女にとって確かに良いことなのかもしれない、だけど――――――
「いつ帰るのかは分からない。でも、何となく感じるの。あぁ、もうすぐ戻るんだって。たぶん、ここに来た時と同じように目が覚めたら元の世界に戻ってるんだと思う。だから、私、戻る前にもう一度だけでもいいからリシェルとちゃんと話をしておきたかった。だって、私もリシェルのこと大好きだったから……」
少し悲しそうな顔をして、アイカは顔を上げる。
彼女の言葉に私は「あぁ」と納得した。
何度、追い返してもアイカが私の部屋に訪れて来たのにはそう言う理由があったからだったのだ。
「私ね、リシェル達と会えて本当に幸運だったって思ってる。何処から来たのかもわからない私にみんな優しくしてくれて。すっごく楽しかった。もし、また、フィラディアルに来れたら…………」
言い掛けて、アイカは口をつぐんだ。
確信がないのだ。
彼女が再びこのフィラディアルに来ることができるという確信が。
もし、彼女がここへ来たのが事故であったなら、そんな事故が二度も起こるなんて限らない。
けれど、私は彼女に言う。
ありったけの願いを込めて。
「“もし”なんかじゃない。アイカは必ずまたここへ来るわ。きちんと戻って来ないと承知しないから。私から陛下を奪っておいて、もう来ない、なんて許されると思っているの? もし、もう来ないって言うのなら、私がアイカの世界まで行って無理矢理にでも貴女を連れて帰るわ。」
アイカは驚いたように私を見つめ、最後に、また「有難う」と言って笑った。
「私ね、この世界に来た時……、異世界に来たんだってちゃんと自覚した時、ちょっとドキドキして恐かったんだ。」
「なぜ?」と問うと、アイカは笑って言った。
「だって、私が読んだことのある物語の主人公はね、異世界に飛ばされたら必ず戦争とか争いに巻き込まれて大変な目に会うの。だから、もし戦争が起こって、闘わなくちゃいけなかったらどうしようって思ってた。取り越し苦労だったけど」
「そんな、アイカが来るたびに戦争が起こっていたら困るわよ。私はアイカが来たっていうそれだけで充分、大変だったのよ? お願いだから、これ以上私に気苦労を掛けさせないで」
「はーい、気を付けます!」
片手をピンッ、と挙げ、彼女が元気良く返事をする。
その後、アイカと私はお互いに顔を見合せ、クスクスと笑った。
そしてアイカは翌朝、私が目を覚ました時にはフィラディアルから居なくなっていた。
彼女は宣言通り、本当に呆気なく元の世界へと帰って行ったのだった。
「行ってしまいましたね」
「ああ」
そう言った陛下はやはりどこか寂しそうに見えた。
執務室の窓から見える風景へと目を向け、何か思い出したかのようにふっ、と笑う。
「アイカは最後まで俺のことを名前で呼ばなかったな。リシェルのことは“リシェル”と呼ぶのに……」
「やきもちですか?」
思わぬ陛下の言葉にクスクス笑いながらそう聞くと、殿下は窓の外を見ながら「そうかもな」と笑った。
「残念でしたね。でも、これはアイカの親友である私だけの特権なのです」
今も陛下のことを見て辛くはない、と言ったら嘘になる。
でも、以前に比べ私の心は穏やかに凪いでいた。
きっと、いつかこの痛みもきれいに消えてしまうのだろう。
そう思うと、少しだけ寂しい。
「陛下」
そう呼ぶと彼は「何だ?」と私へとその青い瞳を向けた。
「私はちゃんと陛下に恋をしていましたよ」
陛下を見た時に溢れていた温かな気持ちも、この胸の痛みも、きっと偽りなんかじゃなかった。
憧れの気持ちが強かったのかもしれない。
けれど、そこには確かに、“愛しい”という彼を想う気持ちがあった。
私はちゃんと恋をしていたのだ。
今なら胸を張って言える。
例え、この想いが報われることがなくても、この十数年思い抱いていた気持ちが無駄では無かったと、偽りでは無かったと、知っていて欲しかった。
陛下は驚いたように目を見張っていたが、やがて目を細め、「そうか」と笑った。
「それは、光栄だ」と。
だが、と彼は続ける。
その顔に苦笑の交じった笑みを浮かべて。
「俺はずっと思っていたんだ。それこそ昔からな。今、リシェルの目がこちらに向いていようとも、いつか必ず離れると。アイカが来ようと来なかろうと、たぶんそれは変わらない。もし、アイカが来ていなかったら、俺は自然にリシェルのことを好きになって、妃に迎えていたと思うぞ。だけど、リシェルは違う。必ず、俺の傍から離れただろう。妃となってもその心が俺に向くことは無かっただろう。そしたら、俺はきっと一人取り残されていた。そんなことになるのは御免だからな、俺はアイカが来てくれて本当に助かった」
「それは、どういう意味でしょう?」
私から陛下を離れる? そんなことが本当に起こっただろうか?
首をひねる私に、「わからないか?」と陛下は再び口を開いた。
「昔いただろう。リシェルを追いかけまわしていた少年が」
「ああ……、あの嫌がらせですか」
泣いて逃げ回った幼い日々を思い出し、私は少しげんなりする。
それを見て、陛下がくっくっ、と笑った。
「本当にただの嫌がらせ、だと思うか?」
「あれが嫌がらせ以外のなんだというのです」
蛇や虫を持って追いかけてきた少年。
その記憶は、今でもたまに見る悪夢の一つだ。
けれど、殿下はかぶりを振った。
「いや、少なくとも本人はそうは思っていなかったぞ。お前に喜んでもらおうと自分が好きな蛇や虫を持って行ってリシェルに見せようとしてたんだ。ただ、方法が間違っていることに全く気付いてなかった。いつも泣いて逃げるリシェルを見て、ひたすら首を傾げていたぞ?」
「ラスリー…………」
かつての記憶にそんなオチがあったとは。
私はその少年の名を呆れ交じりに呟いた。
「それに、その首飾りだ」
そう言って私の首元を指差した殿下に、私は慌てた。
なんとなく、ずっと外し損ねていた物。
ラスリーに貰った“恋のお守り”だという、トパーズの首飾り。
「こ、これは……」
「それは、ヒルデルト家の庇護を示すものだ」
「―――え?」
思わず聞き返してしまった私に、殿下は「知らずにつけていたのか?」と驚いたように呟き、次いで納得したように頷いた。
「そうだな。リシェルが知らないのも無理はないか。これは、宮廷にいる男の中だけでの暗黙の了解だからな」
「……どういう意味なのでしょう?」
全く意味が分からない。
困惑を隠せない私に、殿下は「つまりな」と、続けた。
「それは、手を出すな、という周りへの牽制を示すものだ。ヒルデルト家の人間には昔から自分の最も大切な女(ひと)に自分の瞳と同じ色の宝石を渡す習わしがある。そして、今ではそれが周知の事実となっている。リシェルがつけているそれは奴の瞳と同じ色だろう?」
「―――――――!?」
ラスリーの瞳と同じ橙の宝石の首飾り。
そこまで言われたら、さすがの私にも分かってしまった。
みるみるうちに顔が火照り出す。
「それに、だ。恐らくお前の不安を掻き立てないようにと、アリュフュラス家からはリシェルのところへ情報がいっていなかったのだろうが、あの噂が流れた後からアイカが狙われていたのと同様、リシェルも狙われていた。あの時はむしろ、アイカよりもリシェルの方に害をなそうと画策しているものが多かったはずだ。この機会に大貴族であるアリュフュラス家の姫を排そう、とな。その首飾りはそれすらも牽制していた。アリュフュラス家の後ろにはヒルデルト家もいるのだと。二大貴族を敵に回そうなんてそんな馬鹿はなかなかいないからな。しかも、それを証明するかのようにラスリーはリシェルの部屋に通い詰めた上、あの噂に対して、自分の方がリシェルを落とそうとしているのだ、と明言しただろう?それは決定的で、だからこそリシェルを守る手段と成り得たんだ」
「そんなこと、私は全然…………」
―――知らなかった。
知らない間に、私は彼に守られていた……?
「大体、ラスリーが宰相まで上り詰めたのは何故だと思う? それもやはり、リシェル、お前を手に入れる為だ。ラスリーはヒルデルト家の長子と言っても養子だからな。しかも、ヒルデルト夫妻の間に嫡男が生まれた後、傍目から見たらより一層その立場は危うい。とてもじゃないが、アリュフュラス家の姫に手を出すなんて不可能だ。それが、王の妃候補である姫なら尚更な。まぁ、それでも、リシェルが王妃候補であり続ける限り、そんなことは叶わなかったろうが」
「…………」
「そんな必死になってる奴にリシェルの目が向かないはずがないだろう?」
面白そうに私へと目を向けた陛下に、だけど、私は最後の抵抗を示す。
「けれど……、私はまだラスリーのことが好きなわけではありません」
そう言うと陛下は「奴もなかなか報われないな」と言って笑った。
陛下の執務室を辞する前、私は扉の所でふと立ち止まり、もう一度中を振り返った。
どうしても、これだけは言っておかなければ。
「陛下―――いえ、アトラス。これは友人として申し上げます。私は貴方がアイカのことを泣かせるようなことがあったら許しませんよ。あの笑顔が失われるようなことがあったら私は一生アトラスを許しません。あの花を、美しくも愛らしいあの花を守るのだ、と貴方が言うのならば、私は貴方とアイカに全面的に協力しましょう。それを、よく覚えていて下さいね」
「―――ああ、肝に銘じておこう」
パタン、という音と共に私は扉を閉めた。
そして、歩を進める。
次に向かう場所はもう決まっているのだ。
未だ床から離れられない、蛇や虫を手に私を追い駆け回した、かつての少年の元へと向かう。
とにかく一言、私に嘘をついたあの男に文句を言ってやらねば。
首元で花の形にあしらわれた橙の宝石が揺れる。
東棟から西棟へと続く渡り廊下、私は空を見上げた。
何処までも続くこの空の下、きっと彼女は何処にもいない。
けれど、彼女もまた、見上げているだろうか。
私の知らない彼女の世界で、この空に似て澄み渡った空を。
突然現れた類稀なる黒髪と黒の瞳を持つ人物。
あっという間に私の世界を壊してしまった彼女。
だけど、私は貴女に会えて良かったわ。
貴女の愛らしい笑顔に会えて本当に良かったと思っているわ。
ねぇ、アイカ?
私は、今、あなたを想います。
End
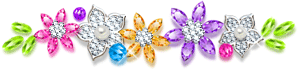

(c)aruhi 2008