four o'clock 7:偽無き本心

「ねえ、リシェル、開けて? お願いだから! 話をして!!」
「アイカ様。いい加減お引き取り願います。エリィシエル様は公務で忙しいのです」
「少しでいいの。お願い、ほんの少しでいいから……」
「お引き取り下さい」
バタン、と無情にも閉められた扉。
その向こうで、アイカがまた何度か扉を叩き、やがては諦めて元来た道を戻っていく。
ここ数日繰り返される光景。
何度も部屋を訪れて、訴えるアイカの姿に良心が痛まないと言ったら嘘になるけれど、ようやく止んだ扉を叩く音に安堵するのも、また、確かだった。
それに、アイカに告げていることもあながち嘘ではない。
事実、私はここ最近公務に追われているのだ。
そう自分に言い聞かせて、手元の書類へと目を落とす。
こうしている間は、仕事に集中できる。
他のことを考えなくていい分、幾らか楽だった。
「エリィシエル様、お茶にいたしましょうか?」
一息ついたところで、ユージアがそう言った。
彼女には本当に心配を掛けている。
何を言うまでもなく私の望むことに気付き、先を見越して行動してくれるいつもの適切な気遣いが、この頃は倍近くなった気がする。
そう言ったら、彼女はただ微笑んだ。「私が望んでしていることなのですから」と。
「有難う、ユージア。けれど、この書類をランスリーフェン侯爵に届けなければならないの」
「それなら私が参りましょう。エリィシエル様は少し休まれて下さい。働き詰めではお体に障ります」
「私もそうしたいのだけど、重要な書類だから直接持ってくるようにと言われているの」
本当に何を考えているのか。
“重要な書類”と言ったが、取り立ててそのようには思えない。
あの男の前で取り乱してしまった手前、こちらも顔を合わせづらいし、向こうだってそうだろうに。
漏れそうになる溜息を何とか嚥下させ、笑みを作った。
これ以上ユージアに心労を掛けるわけにはいかないのだ。
「それじゃあ行ってきますね。供は結構です。一人でのんびりと行きたいから」
「……然様ですか」
ユージアはどこか納得のいかない顔を浮かべていたが、それ以上何も言わずに私を送り出してくれた。
ランスリーフェン侯爵の執務室は大抵の公務に使われる部屋がそうであるように東棟にある。
私は居住区域である西棟から東棟へと渡る途中、渡り廊下から覗く中庭を今日は見ないように意識して歩いた。
ここを通るたびに眺めていた庭園は今日も変わらず、多種多様な花が咲き誇っているのだろう。
見なくてもその光景が浮かぶほどに親しんでいた庭園に今はただ、目を閉じた。
「ちゃんと来ましたね」
「仕事ですから……」
自分でもそう思うほど、ぶっきらぼうに言うと、部屋の奥、一番大きな窓の前にある机に座っている男の横に書類を置いた。
手を止め、少し驚いたように、こちらを見上げる橙の瞳に気付き、少し身じろぎしてしまう。
「何か?」
ランスリーフェン侯爵は、「いや」とかぶりを振ると、目を細めて笑った。
「御苦労様でした。部屋までお送りしましょう、エリィシエル姫」
「結構です」
「私がお送りしたいのですよ、リシェル」
そう言うと、彼は手にしていたペンを置いて立ち上がり、扉へ向かう。
私はこないだの夜の出来事に触れられないことにひどく安堵したのと同時に、何事もなかったかのように扉を開けて待っている彼に呆れを覚えた。
「―――もう、勝手にして下さい……」
私達はただ黙々と廊下を歩いていた。
普段はどれだけ話題を持っているのかと言うほど話し続けているのに、今は沈黙を保っているランスリーフェン侯爵を奇妙に思う。
別に、この沈黙が息苦しいという訳ではない、それよりも寧ろ、何も話さなくていい、というこの状態が楽で、妙に心地よかった。
けれど、こんな状態は長くは続かず、私は目の前に現れたフィラディアルでは珍しいその黒い髪に足を止めた。
「アイカ……」
「ごめんね、リシェル。待ち伏せするなんて最低だと思ったんだけど。でも、王様にもうそろそろ東棟に来ているはずだって聞いて、渡り廊下で待ってれば、帰りに会えるんじゃないかって。どうしても、リシェルと話がしたくて……」
「ここでずっと待っていたの?」
そう問うと、アイカはこくりと頷いた。
必死に訴える黒い瞳が、こないだ見た傷つき歪んだ瞳を思い出させ、胸にチクリとした痛みを覚える。
私は溜息をつくと隣に並んで歩いていた男を見上げた。
「謀りましたね」
わざわざ私に書類を持って来させた意味がわかった。
陛下と一緒になって、アイカが私に会えるようにと仕向けたのだ。
「さて、何のことかな?」
「―――もう、いいです。ここまでで結構ですので、もうお戻りください。送って下さって有難うございました」
「大丈夫か?」
心配そうな色を浮かべた橙の瞳に、逆に決心が決まった。
この男にまで心配されたら終わりである。
本当はまだ手が少し震える。この場から逃げだしたい。
だけど、そんな自分はもう終わりにするのだ。
私はしっかりと目の前にいる男を見上げ、例え虚勢と言われようとも微笑みを浮かべることができた。
「はい。逃げないで、ちゃんとアイカに私の気持ちを伝えます」
そう告げるとランスリーフェン侯爵は「頑張れよ」と囁き、踵を返した。
私は深呼吸をする。
きっと、もう以前のようにアイカと親しくすることは無理だ。
私は、そんなに器用じゃない。
今でも、やっぱり温かだった私の世界を壊してしまった彼女を恨んでいる。
あの日、思わず叫んでしまった言葉はずっと抱いていた本心だった。
アイカなんて来なければ良かったのに、確かにそう思い、今もその気持ちがある。
私が彼女を思う時、それは醜く、汚いドロドロとした感情で溢れ返る。
私は朗らかに笑うアイカが嫌いではなかった。
だけど、今は―――――
「アイカ、私の本当の気持ちを伝えるわ」
例え、それが彼女を今以上に傷つける結果になろうとも、私はもう彼女に会いたくなどないのだ。
私にとって彼女に接することは苦痛以外のなにものでもないのだ。
だからこそ、この無意味な繰り返しを、彼女が毎日私の部屋を訪れるというその行為を、終わらせたいのだ。
その為には、私の本心を彼女に伝える必要があった。
私の言葉にギュッと手を握りしめながら、アイカが頷く。
傍目にも彼女が緊張していることがわかった。
「私は―――――――」
その時、アイカの背後で何かが光った。
鈍いその光に背筋が凍る。
「――――アイカ!」
彼女が振り返ったときに揺れた黒く輝く髪が、まるで時の流れが遅くなったかのように、ゆっくりと目の前を舞った。
「アイカ様、ご覚悟――――!」
頭が真っ白になる。
次の瞬間、私は地を蹴っていた。
「やめて――――――――!!」
必死で小さな体を受け止めて、床へと倒れこむ。
「―――っう!!」
ずぶり、という鈍い音と共に美しいほどに紅い雫が次々と滴り落ちた。
金臭いその液体はどろり、と流れだし、次々とドレスを染めていく。
「―――リシェル!!」
恐怖に見開かれた黒い瞳が私を見上げている。
けれど、私も恐怖を持って目の前の男を見上げていた。
「――――――ラスリー!!!」
苦痛に歪められたその顔は、しかし、ふっと緩んで橙の瞳が私を見つめた。
ゆっくりと伸ばされた手が私の頬へ触れ、ぬるぬると生ぬるいその感触に私は脅えた。
「怪我はないか、リシェル?」
「―――ええ」
カタカタと震えながらも頷く私を見て、彼は「よかった」と溜息を漏らした。
頬に触れていた彼の手がずるり、と滑り落ちる。
庇うようにして覆いかぶさっていた彼の体が完全に私へと覆いかぶさって来た。
私は自分にのしかかってきたその重さに、恐怖する。
「ラスリー……? ラスリー? ラスリー?」
揺すってもびくとも動かない。
目の前の世界が一気に歪み、揺れ出す。
この前とは比べ物にならないほどの恐怖。
「こんなはずでは……」
返り血を浴び、呆然と立ち尽くす男の声など私の耳には届かなかった。
ただ、目の前の現状に、ひたすら恐怖する。
刻々と広がっていく赤い沁み。
動かない体。
「い、やっ……、ラスリー!? 誰かっ! 誰か、早く! 嫌、やめて、ラスリー……、いやあっ―――――!」
「リシェル、体に障る。ここは任せて、少し休め」
労わるように掛けられた陛下の優しい言葉に、私は首を振ってそれを断った。
眠っているラスリーの掛布へとしがみ付く。
「気持ちは分かるけど、リシェルが倒れちゃったら元も子もないよ。ね、ちょっと休もう? 代わりに私が見ておくから」
「エリィシエル様、アトラウス陛下とアイカ様の言う通りです。少しは休まれないと……」
アイカの言葉にも、ユージアの言葉にも私はやっぱり首を振った。
答える代わりに、ギュッと掛布を握る手に力を込める。
そんな私を見て、皆は心配げな視線を送り続けながらも、溜息を残し、諦めたように部屋を後にした。
ラスリーはあれから三日も眠り続けている。
医者は「一命は取り留めた」と言う。
けれど、そんなものただの慰めでしかない、ということなど私には分かっていた。
一命は取り留めたが、状況がいつ悪い方へと変わるやもしれない、と言うことなのだ。
それを証明するかのように医者は一時間ごとにこの部屋を訪れ、何も変化が無いと知れると安堵の溜息を洩らすのだ。
私はいつ止まるやもしれない浅い呼吸に恐怖して、上下する彼の胸を見据えていた。
恐ろしさに潰れそうになりながらも、必死に掛布に縋り付いた。
アイカを狙った男は、この国第三位の有力貴族デルクラン家の手の者だった。
アリュフュラス家の姫である私が殿下から見放された今、次の妃候補は第二位以下の貴族の令嬢たちへと回るはずだった。
しかし、殿下からは一向に声が掛る気配がない。
それどころか、ただの愛玩具と思われていた黒髪の少女(実際には少女ではないのだがやはりそう見えたらしい)にばかり、うつつを抜かす殿下に焦りを覚えたのだそうだ。
そして短絡的なことに、彼女さえ取り除けば殿下の目が、自分が仕える家の姫に向けられる、そう思った。
全ては彼による独断的犯行である、と。
それが、事実かどうかは疑わしい所である。
どちらにしろ、デルクラン家にも調べは及ぶだろう。
きっと、何事もなければ、自分と同じ「アイカさえいなければ」という犯行の理由を聞いて私は自嘲したことだろう。
けれど、恐怖に支配されている今、そんなことさえ頭の隅にも浮かばなかった。
ただ、ひたすら願う。
横たわるこの男が目覚めるようにと。
「――――――――!!」
握っていた掛布が微かに動いたことに私は顔をあげた。
シュン、と伸びた長くはないが形の良い睫毛が何度か揺れ、その瞼がゆっくりと開く。
「ふーーー」という溜息共に、掠れ、力のない声がようやく動いた口から漏れた。
「やはり……、アトラスに言われた通り、文官だからと言って毎日の鍛錬を怠るべきではなかったか…………」
「――――ふっ……」
三日間待ち続けた橙の瞳が私へと向けられる。
少し硬い、けれど、確かに柔らかく、温かで、大きな手が頬に触れた。
「泣いているのか?」
静かに滴り落ちる滴をその手で拭いながら、彼は困ったように笑った。
「リシェルの泣顔はあまり見たくないのだが……」
「―――誰の所為だと思っているのです!」
睨みつけてやると、ラスリーはいつものからかいの笑みを浮かべた。
「ようやく俺に惚れてくれたのか?」
「誰が貴方なんかに惚れますか!!」
そう言うと、ラスリーは「残念」と言って、くつくつと笑った。
「でも、ようやく俺のことを見てくれた」
「…………」
全くこの男には、ほとほと呆れ果てる。
人の気も知らないで、よくもいけしゃあしゃあ、と。
涙が零れ落ちる。
だけど、これはこないだの凍りついたような鋭い痛みは伴わなかった。
安堵と共に流れる涙は温かく、ようやく私を安心させたのだ。
「私はあの時、アイカに“嫌いだ”と言うつもりでした」
やっとのことで涙を収めると、私は横たわる男にぽつり、と漏らした。
「アイカと接するのが苦しすぎて、ちゃんと気持ちを伝えて、向き合って、それを最後に彼女とは距離を置こうと思ったのです。だけど……」
「体が勝手に動いた?」
ラスリーの言葉に私は素直に頷いた。
そう、あの時、アイカの背後に短剣を持った凶手を見た瞬間、体が動いた。
そう、いうなれば自分の意志など関係無しに、私は地を蹴ってアイカに向かって走り出したのだ。
「……きっと、それがリシェルの本心なんだろう」
「私の、本心?」
首を傾げる私に、ラスリーは「そう」と頷く。
「性急した場面に遇する時、人は誰でも本心に従ってしまうものだよ。そういう場面であればある程、それは勝手に出てしまう。例え、自分ではそうではない、と思っていてもね。だから、アイカを守ろうと動いたリシェルは本当のところではやはり、アイカのことを好きなんだろう。アトラスのことを抜きにして考えてごらん。きっと、リシェルは彼女のことを好ましく思っている。だからこそ、あの時体が動いたんだ」
「私が、アイカのことを好き?」
口に乗せて呟くと、私の中でその事実はストン、と落ちて、収まった。
思い浮かぶのは、彼女の花のような笑顔。
私はその笑顔を愛らしいと思う。
「ええ、そうなのかもしれません……。貴方の言う通り、私はどうやら彼女のことを好ましく思っているようです」
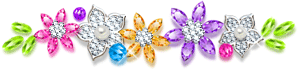

(c)aruhi 2008