four o'clock 若草色の姫君 1
またの名をアトラウス苦労話
<幼少時:アトラウス10歳、ラスリー8歳、リシェル5歳>

リシェルに初めて会った時、五歳離れた小さな金髪の少女を素直に可愛らしいと思った。
あどけない若草色の瞳、頬を紅潮させながらにこり、と満面の笑みを浮かべ「はじめまして」と挨拶をした少女。
自分の妃になるだろうと母から言われたこの女の子を自分はこれから守っていくのだ、とその時は漠然と思っていた。
けれど、それは隣で同様にリシェルと相対していた少年も同じだったらしいと知るのは後のことである。
どさり、と机の上に新たに乗せられた書類の山に溜息を落とし、その原因となっている肩まで伸びた赤毛をきっちりと束ね、橙の瞳を持つ男を見上げた。
恐らく、この男からの被害をもろに受けているのは俺だろう。
仕事の上では優秀だが、私事を持ちこむのはやめて欲しい。
「……今日は何だ?」
「別に。ただ貴方の仕事が多いだけだろう」
朝から同じ量の書類の山を五回も持ってきておいてよく言う。
「リシェルがどうかしたのか?」
「なんだ、分かっていたのか」
「分かるも何もお前が不機嫌な理由はそれしかないだろう」
おかげでいくら仕事をやっても追いつかん。
「―――アトラス、昨日庭園でリシェルに何を言った?」
「―――? 特には何も言っていないが、それがどうした?」
「何か様子がおかしい」
「何がだ?」
「そこまでは分からない」
「…………」
何か良く分からない理由で俺はこんなことになっているのか……
「ラスリー……」
「何だ?」
ラスリーが気だるそうに振り返る。
「どこへ行く?」
「たまってる仕事を取りに行くんだよ」
「まだあるのか……」
「当り前だ」
全く一体どこからそんなに仕事を持ってくるのか。
文句を言いたかったが、余計仕事が増えそうなのでやめておく。
「アトラス……、リシェルを泣かすなよ」
不機嫌そうな言葉と共にパタン、と扉が閉まる。
恐らく本人すら口にするのは不本意な言葉なのだろう。
リシェルに対してだけは昔から不器用な二つ下の幼馴染に苦笑しつつ、多大なる書類の一つへと目を落とす。
大体、リシェルを泣かせていたのはお前の方だろう……
「―――アトラス!!」
目に涙を浮かべながら必死に走って来た小さなリシェルを抱きとめ後ろにかばいつつ、続いてやって来た赤毛の少年へと目を向ける。
「ラスリー、またお前か……」
今日はまだら模様の蛇を手にやって来たラスリーを睨みつける。
昨日は白い虫の幼虫だった。その前は確か緑の青虫。
すでに日課となっていた一連の行動が、どうやらリシェルに対する嫌がらせではないと知ったのはラスリーが漏らした意外な一言だった。
「リシェルはどうしていつも泣いて逃げるんだろう?」
ラスリーと二人、勉強の後、今日の要点を整理していたら、ペンをインク壺につけたままラスリーがぽつり、と呟いた。
「それ、本気で言っているのか?」
驚いて尋ねるとラスリーがこくり、と頷く。
てっきり嫌がらせかと思っていた。
「そりゃ、逃げるさ。蛇だぞ?」
「でも、こないだは小さな幼虫を持っていったんだよ? 青虫も。それでも泣いたから、小さいのは嫌なのかと思って、おっきい蛇にしたのに」
「……怖がっているとは考えなかったのか?」
「怖がってる? 何を?」
「蛇や虫をだ」
「怖がってたの!?」
大きく見開かれた橙の瞳に、呆れ果てて机に頬杖をつきながらこめかみを押さえた。
「普通の女の子は皆怖がる」
女の子どころか、貴族育ちなら男だって怖がるだろう。
庶民の出故、やはり考え方が違うのだろうか。
「そう……、だったんだ……」
納得したように頷いたラスリーに、これで明日からは大丈夫だろうと思った。しかし、次に彼が口にした言葉にそれは無理だということを悟る。
「じゃあ、明日は蛇と虫はやめて、トカゲにしよう。リシェルが恐がったら困るからね」
それじゃあ、全く意味はないだろう。
七歳でこの王宮まで上がってきたほどだ、しかも、大貴族ヒルデルト家といっても養子というハンデを抱えて。
頭はかなり良いはずなのだが、なぜわからないのだろう。
否定するのも忘れ、ただただ呆れたのを覚えている。
「―――聞いたか?」
稀にみる真剣な面持ちで眉間に皺を寄せるラスリーに頷きを返す。
それが数日前から流れ出した噂を指していることは明白だった。
アイカを連れて街へ案内に降りた後からは、その噂に拍車を掛けてしまっていた。
そして新たに流れだした噂。
そのどちらもがアリュフュラス家の姫の危うさと持つ権力に対する危惧を含んだものだった。
「あぁ、動きがあるかもしれん」
「まぁ、どいつが動くか大方予想はつくがな」
ふっ、と冷笑を浮かべ、腕を組み直したラスリーがこちらを見据える。
「もう少し人目をはばかって会わないからこういうことになるんだ」
「―――悪かった」
「アイカにも手が及ぶかもしれないぞ?」
「分かっている。手は?」
「数日中に全て打ち終わる。完全とは言えないが、後は目を離さないようにするしかない」
「そうか、助かった」
「―――アトラス」
「分かっている。俺も近日中にリシェルの所へ顔を出す。近頃、元気がないから気になっていたし、丁度いい」
「有難うな」
珍しく礼を口にした男に目を見張り、苦笑する。
「別にお前の為じゃない。リシェルの為だ」
俺が行くことで周りの者への牽制になるなら、こんなに容易いことは無い。
幼いころから二人で守ってきた花を、易々と手折られるわけにはいかないのだ。
けれど、部屋を訪れたその日、リシェルの首に下がっていた橙の宝石に俺は驚くこととなった。
まさか、ここまでするとは思っていなかった。
自分の想いすら伝えていないはずの相手に、本来は妻となる女性に贈る物を贈るとは。
「とうとう動いたか」
思わず苦笑してしまう。
一体どこまで必死なのか。
噂を塗り替え、貴族中に脅しともとれる牽制を掛け、それでも不安だったのか、最終手段まで持ち出した。
ヒルデルト家の庇護。
もともとアリュフュラス家の庇護を持つリシェルがそれを手にした時、敵に回せる者などいない。
それでも手を出そうとするのはよほど愚かで捨て身の者だけだろう。
奴らが最も危険だが、この宮廷には保身を気にする貴族しかいない。
ほぼ確実に今のリシェルは安全だった。
微笑むリシェルを見ながら、本当に俺ができることはなくなってしまったんだな、と実感する。
アイカを狙った刺客によってラスリーが倒れた時、決して離れようとしないリシェルを心配しながらも、昔からの予想が実現しつつあることを感じ、その行動に納得する。
「王様、なんだか寂しそうだね?」
部屋から出てすぐ、アイカに言われた言葉に苦笑を洩らし、ポンポンと滑らかなる黒髪を撫でる。
「ああ、そうだな」
「アトラス、今は大丈夫だよね? ラスリーいないよね?」
「ああ、大丈夫だよ」
びくびくと脅えて、俺の体に隠れながらも、いつもラスリーの存在を気にしていた少女。
かつて不器用な少年から守っていた小さな姫君は、今、そのかつての少年によって守られようとしている。
俺の役目はとうの昔に終わっていたのだ。
だからこそ、アイカが帰ってしまった後、部屋に訪れたリシェルの言葉は俺を驚愕させた。
「私はちゃんと殿下に恋をしていましたよ」
俺に微笑みを向けてくれながらも、彼女が常に気にしていたのはラスリーだと知っていたから、ラスリーにだけは気兼ねなく文句を言っていることを知っていたから、ずっとそう思っていたから、驚き、単純に嬉しかった。
本当に「それは、光栄だ」
嬉しくて、だから、つい、リシェルに話してしまったのだろう。
後でラスリーに散々文句を言われると知りつつも、彼が彼女の為にしてきたことを。
困惑しつつも驚きに見開かれていく若草色の瞳を見ながら、アイカが言っていた通り少し寂しく思う。
本当にアイカがいてくれてよかった。
そうじゃなければ、俺は離れていく存在に耐えられなかっただろうな。
「けれど……、私はまだラスリーのことが好きなわけではありません」
全てを告げた後に呟かれたリシェルの言葉。
“まだ”、か…………
本人はそう言ったことに気付いているのだろうか?
それは、未来には可能性があることを示す言葉。
「奴もなかなか報われないな」
そう笑いつつも俺は秘かに安堵する。
こんなことを言ったらラスリーに怒られるだろうが、俺が置いて行かれるのはまだ少し先の話のようだ。
扉へ向かうリシェルの背を見送っていたら、ふと、彼女が足を止めて振り返った。
若草色の瞳が真っ直ぐとこちらを見据える。
「殿下―――いえ、アトラス。これは友人として申し上げます。私は貴方がアイカのことを泣かせるようなことがあったら許しませんよ。あの笑顔が失われるようなことがあったら私は一生アトラスを許しません。あの花を、美しくも愛らしいあの花を守るのだ、と貴方が言うのならば、私は貴方とアイカに全面的に協力しましょう。それを、よく覚えていて下さいね」
それは、アリュフュラス家が全面的に協力するということを暗喩する言葉。
小さな姫君だったリシェルが、今度は自分の大切なものを守る為に発した言葉。
そして、同時に俺の大切なものを共に守ってくれるという何とも力強い言葉。
目の前の若草色の瞳をしかと見据える。
感謝と誓いを込めて。
「―――ああ、肝に銘じておこう」
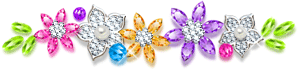

(c)aruhi 2008