four o'clock 若草色の姫君 2
またの名をランスリーフェンお家事情

俺が持つ一番古い記憶は、教会のステンドグラス。
天上から差す光に彩られた純白の床。
次は穏やかな笑みを浮かべ、俺を覗き込んだ夫婦。
彼らは嬉しそうに俺に手を差し伸べた。
「今日から私達が貴方の家族よ。ラスリー」
その日、彼らはただの“ラスリー”だった俺に“ランスリーフェン・アッカルディ・エル・ヒルデルト”の名を与えた。
「数多いる孤児の中でなぜ自分を選んでくれたのか」と、昔、養父母に尋ねたことがある。彼らは笑ってこう答えた。
「さぁ、私達にもそれは分からない。けれど、貴方が子となってくれたのは私達にとってこの上ない幸運だった」と。
そして、彼らが父と母になってくれたことは俺にとっても、やはり、この上ない幸運だったのだ。
引き取られたその当時、彼らには子がいなかった。
母は当に三十路を越え、年を追うごとに子を身籠ることも、ましてや出産など難しくなっていった。
父はヒルデルト家の血を絶やさぬためにも、側室をとるようにと親類縁者に何度も薦められ、その度に何度も断った。「お前達の子が大貴族ヒルデルト家を継げるかもしれぬのだ。嬉しいだろう」と皮肉りながら。
最も、頭の固い親類縁者に家督を譲る気などさらさらなかったらしいのだが。
けれど、やはり子は欲しかったらしい。
だからこそ養子を取ったのだ、と言っていた。
しかし何の悪戯か、俺が養子としてヒルデルト家に入った翌年、母は突如妊娠した。
当然ながら両親は心の底から喜んでいた。
それこそ毎日、神に感謝を捧げるほどに。
「ラスリー、貴方に弟か妹ができるのよ」
まだ、ちっとも大きくは無い腹を擦りながらそう言う母に、嬉しそうな顔を向けつつも、内心では「自分はもう必要なくなってしまう」という不安と焦りでいっぱいだった。
両親に嫌われないよう、捨てられないようにと必死に勉強した。そうすれば、誰からも認められるほど優秀であれば、きっと自分も「ここに居ていい」と言ってくれると思ったのだ。
後で母にそう言ったら「そんな馬鹿なことを考えていたの? 今もあの頃も私にとって貴方はかけがえのない子供なのに」とクスクスと目を細めて笑われた。
生まれた弟は可愛いもので、俺の危惧など知る由もなく小さな手で俺の指を掴み、歩けるようになればよちよちとどこまででも後を付いて来た。
我ながら、よくもまぁここまで慕われたものだと、未だに嬉々として今日あった出来事を毎日報告しにやって来る弟をみながら苦笑する。
とにかく、その当時、必死に勉強したおかげか、同年代の子供に比べ群を抜いて頭の良かった俺は王子であったアトラスの学友として王宮に上がることになったのだ。
彼女に会ったのはそれからちょうど一年後。
薄い水色のドレスに身を包んだアリュフュラス家の姫君。
輝きを放つ金髪に、みずみずしい若葉のような若草色の瞳。
アトラスの王妃候補だという彼女は、恐らくまだそのことをよく理解していないながらも一心にアトラスの方を見つめて、にっこりと笑っていた。
はじめてリシェルを見た時から、家に飾ってある人形のように可愛い子だなとは思っていた。
けれど、まだその時はそれ以上の感情などなかったというのが実際の所なのだ。
いつか王妃となるだろうこの女の子を、隣に立っているアトラスと同じように、いつか自分の主君として仰ぐようになるのだろうな、という漠然とした考えしか持っていなかった。
だから、その時の俺が今の自分を見たらさぞかし驚くだろう。
仰ぐべき主君を差し置いて、その若草色の瞳を持つ姫君を手に入れようと必死になっているのだから。
そう考えると少し笑える。
とにかく、リシェルとの関係が動いたのはそれから約半年が経過した後。
今もそうであるが、宰相位という地位を持っていなかった分、その当時の俺はかなり微妙な立場にあった。
ヒルデルト家の長男でありながらも、養子。しかも、ヒルデルト家には嫡男である弟がその時すでにいた。
平民の孤児であったにも関わらず、養父母となったヒルデルト家の名の元に王宮へと上がっていたのだ。
大人たちは陰で揶揄する。
もちろんそんなことは知っていたが、それは別にいい。無視すればいいのだから。
問題は同じ様にアトラスの友として王宮へと迎え上げられていた同年代の子供達だった。
こちらは、もう、本当にどうしようもない。無視したくてもあっちから突っかかって来るのだから。
「また、お前らか……」
アトラスとの授業へ向かう途中、道を遮るようにずらりと並んだ少年たちに嘆息する。
こっちは、ずっしりと重い教科書を抱えているのだ。手が疲れるから勘弁してほしい。
「お前、目障りなんだよ。下賤の出のくせしてヒルデルト家を笠に威張って」
言ってやった、と得意げにふふん、と笑うリーダー格のルブラン家子息に呆れた目を向ける。
「下賤って、意味分かって使ってるのか?」
「―――下賤は下賤だろうが!!」
慌てて言いかえす少年を見ながら、やっぱり分かってなどいなかったのか、と鼻で笑う。
どうせ、親が言っていたのを訳の分からぬまま使ってみたのだろう。
意味も分からぬ言葉を使って威張っている者ほど滑稽なものは無い。
「お前らみたいに馬鹿な奴らに付き合っているほど俺は暇では無いんだ。さっさとそこをどけ」
「はっ、“俺”だってさ。これだから平民の出は。口が悪いにも程がある。おぉ、嫌だ、嫌だ」
おどけて手をひらひらと振って見せたルブラン家子息の言葉に周りの少年たちがドッと笑いだす。
その様子に舌打ちを打つ。
今日はなかなか離してくれそうにないな。いい加面倒くさい。
大体口が悪いのはそっちの方だろう。
再び嘆息をついたとき、ふわふわと広がる淡い桃色のドレスを翻しながら目の前に金髪の少女が現れた。
「こらー! ラスリーをいじめるのはやめなさい!!」
そう啖呵を切って、キッと若草色の瞳で少年たちを睨み上げる自分よりも小さな女の子。
両手を広げて少年たちと俺の間に割って入ったのはリシェルだった。
少年たちは驚きながらも、笑顔を取りつくろい睨んでくるリシェルに声を掛けた。
「……エリィシエル様、ご機嫌麗しゅう」
「麗しくありません。貴方達は何をしているのですか」
むすっとした顔を作るリシェルに少年たちの顔がひきつった。
「いいから、リシェル。行くよ?」
リシェルの背中を押して今のうちに通り抜けようと促したら、今度は逆に俺が睨まれた。
「よくない! 口が悪いのはあっちでしょう!! ラスリーを馬鹿にして!」
そう言ってリシェルが少年たちを指差す。
さっき自分も思っていたことを言われて思わず噴き出したら、ますます睨まれてしまった。
「けれどエリィシエル様。そいつは平民の出なのですよ? それなのに殿下の学友として選ばれるなんておかしいじゃないですか。絶対にヒルデルト家の力を使ったに決まってます」
「それは、ラスリーが貴方達よりもうんと勉強を頑張ったからよ。当り前だわ、ラスリーは貴方達何か遠く及ばないほど頭がいいもの。大体ラスリーはラスリーよ。お家のことは関係ないでしょう」
腰に手を当ててフン、と胸を張って言いきったリシェルに目を見張る。
こんなに小さい体のどこにそんな力強さを隠し持っていたのか。
「リシェルの言う通りだ。ラスリーはお前達よりも賢いからこそ選ばれた。大体、俺も“俺”と言う」
「アトラス!!」
リシェルは顔をぱっと輝かせ、少年たちの背後から現れたアトラスの元へと駆け寄った。
王太子殿下であるアトラスの登場に少年たちは、ますます気まずそうな顔を浮かべ、誰からともなく慌てて散り散りに散っていく。
「遅いから迎えに来た」
そう言って笑うアトラスの横にはリシェルが嬉しそうな表情を浮かべてしがみついていた。
「あぁ、ごめん。……有難う」
二人に近寄って行くと、アトラスはニカッと笑った。
「いいんだ。“俺”はラスリーと違って勉強は好きじゃないからな。勉強の時間が減って助かった」
「ああ、有難う」
もう一度礼を言って彼らの隣を勉強部屋へと向かって歩き出す。
俺は知っているのだ。
アトラスが“俺”と言い始めたのは、俺と出会ってからだということを。
微妙な立場にある俺のことを気遣ってくれていることも。
それを悟らせないようにしながらも、真の友達になってくれたことも。
いつもは文句ばっかり言っているが、実は随分前から彼には感謝している。
まぁ、こんなこと、死ぬまで奴には言うつもりはないが、俺が宰相になったのはそんなアトラスを支えたいと考えたのも確かにあったからなのだ。
そして、小さな体で守ってくれたリシェルにも、もちろん感謝している。
あの時は、とても心地の良い気持ちになったものだ。
歩きながら若草の瞳とかち合い、小さく微笑む。
そんな俺を見て彼女がすぐに微笑み返してくれたのは、恐らくこの時が最後だった。
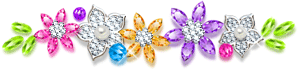

(c)aruhi 2008