four o'clock 若草色の姫君 4

「―――リシェル!!」
リシェルを見つけたのは陽を失くした空がその色を明るい橙から薄い桃が混じった紫へと色を変え始めた頃。
大人たちが行き交う回廊の下、綺麗に刈り取られた垣根にその場には似つかわぬ小さな少女の姿を見つけ、やっとのことで胸をなでおろした。
額から流れる汗に構うこともなく、彼女へと歩みを進めもう一度その名を呼びかける。
「リシェル?」
びくりと一度体を震わせてリシェルが恐る恐る振り向く。
若草色の瞳にめい一杯涙をためながらひっくひっくと嗚咽を漏らしていた彼女は、それでも、現れた俺の姿に再び恐怖の色を示す。
「大丈夫、何も持ってないよ」
リシェルの目の前で両手を広げて見せて、どうにか安心してもらおうと、さらに声を掛けた。
その願いが伝わったのか、どこか安堵したように広げられた手をじっと見つめ、それからこちらを見上げた。
「一人で怖かっただろう?」
淡い黄緑のドレスをきつく握りしめたままリシェルがこくりと頷く。
頷いたことによって溜まっていた涙がまた一つリシェルの頬を流れた。
膝をついて目線を合わせ、リシェルに片方の手を差し出す。
「よく頑張ったね。もう大丈夫だから一緒に部屋に戻ろうね」
おずおずとのせられた小さな手をギュッと握り返して立ち上がる。
すっかり暗くなり明かりの灯された回廊を通りながら西棟への道をゆっくりと歩き出す。
ふと隣に居るリシェルに目をやると、若草色の瞳と目が合った。
リシェルはまだ涙でその瞳を潤ませながらも、嬉しそうに、にっこりと笑った。
まるで、リシェルと初めて対面したあの日のように。
「ラスリー、迎えに来てくれて有難う」
俺はリシェルの涙が苦手だ。
過去の己の悪業を思い出して後悔するから。
反対に笑みを向けられるとそれだけで陽だまりに居る様な心地にさせられるから不思議だ。
リシェルはあっという間にアリュフュラス家の姫として相応しい女性になっていった。
その美貌も、その才も、リシェルに敵う姫君は恐らくこの宮廷中にはいないだろう。
けれど、俺は知っている。
そうなることが決して簡単だったわけではないことを。
そうなる為にリシェルが我慢してきた多くのことを。
いつも泣いていたあの少女が感情を隠すことがすっかり上手くなってしまったことも。
それは、どれもこの王宮で生きていくには必要なことなのだが。
そうなってしまったことに、本人すら気付いていないのかもしれないが。
なぜなら、きっとそんなこと考える暇さえも彼女には与えられなかったのだから。
父が昔、俺に聞いた。
「それほどまでにアリュフュラス家の姫君が好きなのかい?」と。
あまりにもリシェルに執着する俺に半ば呆れたように。
その頃の俺は、また毎日のようにリシェルを追いかけまわしていたから。
また、「あの笑顔が見たかったから」というたったそれだけの理由で。
その所為で余計嫌われていたことにまた気付きもせず。
本当に性懲りもなくよく追い回してしまったものだ。
父の問いに何の躊躇いもなく首肯した俺に、父は半ば困ったように苦笑した。
「難しいぞ、ラスリー? アトラウス殿下と渡り合えなければならないのだから。お前の才が対等か、それ以上になれたとしても、それでもアリュフュラス家の姫君の隣に居ることは叶わぬかもしれないぞ?」
「そうしたら、その時考えるよ」
当時、父の言った意味がよく分かっていなかった俺は単純にそう答えた。
とにかく、高い地位が必要らしい、今まで以上の勉学が必要だと、それだけは分かったが、その他の複雑な事情は、まだよくは理解していなかったのだ。
父は苦笑いを浮かべながら「そうか」と呟き、言った。
「いいか、ラスリー。もし、アリュフュラス家の姫君が手に入らなかったとしても、彼の姫を守る方法だけはあるんだ」
それは何? と問うと、父は俺の瞳へと人差し指を向けた。
「その瞳の色だ。その瞳の色がアリュフュラス家の姫君を守ることになる。これは、アリュフュラス家の姫君だけに限ったことでは無い。お前が大人になった時、守りたいと思った女性、その唯一の女(ひと)を守ることができる。私もお前の母さんに渡した。自分の瞳と同じ色の宝石を相手の女性に渡すのだ。それは、ヒルデルト家の伝統で、宮廷に属する男なら誰でも知っていることだ。だからこそ、その宝石はヒルデルト家の庇護が付いていることを示し、守りの手段となる。もし、必要となった時、ラスリー、お前もその瞳と同じ宝石を大切な女(ひと)に贈るといい。たったそれだけだが、それは相手の女性にとっての最大の武器となる。そのことを忘れるな」
書類を持ってきたリシェルを見て思わず笑みをこぼしてしまった。
彼女は不審そうな眼を向けるがそれは苦にもならない。
アトラスとアイカの仲が完全に露見してしまった後、“恋のお守り”と言って渡したその首飾りがもはや叶えるはずが無いと知りながらも彼女はそれをつけていた。
それがただ単に外し損ねただけだったとしても別に構わないのだ。
ただ、それが嬉しかったから。
だから、本当に守れてよかったと思う。
自分の力が及ばなかった所為で彼女を失ってしまうことがあったら後悔してもしきれないだろうから。
こうやって、ただ横になっているだけだと色々なことを思い出してしまっていけない。
アトラスとリシェルとの三人。
別にこの二人と一緒に居ることが嫌だったわけでは無い。
むしろ、心地いいと言っても良かった。
けれど、リシェルがアトラスの王妃候補である限り手を伸ばしても手に入れることはできないと知った日から、それは、温かいながらも苦痛を伴うものに変わった。
どちらも大切なのだ。
アトラスもリシェルも。
頭では分かっているが、素直に二人の幸せを願うことなど俺にとっては到底無理な話だっただけだ。
自分で自分が嫌になる。
リシェルの傷つく姿が見たくないと言いながらも、アトラスとアイカが一緒に居る所を見て、泣き崩れたリシェルに少なからず安堵を覚えてしまったことを。
それどころか自分の持っていた感情まで耐え切れずにぶつけそうになってしまったことを。
二人の為に退いたリシェルを単純に嬉しいと思い、そしてそのことを確かに今も喜んでいることを。
「―――らしくないな」
一人溜息をつき、自嘲する。
それと同時に扉が叩かれ、次いでリシェルが入って来た。
ちょうど、彼女のことを考え、自責の念にかられていたところだったので正直、驚き、戸惑う。
けれど、彼女はそんな俺には気付いた様子もなく、少し怒ったような顔をして、寝台の横に置いてある椅子へと腰を下ろした。
「ラスリー、嘘をついたでしょう」
ただ一言リシェルがそう言い、若草色の瞳が俺を見下ろす。
彼女の首元で光る自分の瞳と同じ色をした橙の宝石。
やはり、彼女には似合わない色だと、残念に思う。
だけど、傍にあるのがいつか自然になるなら。
「嘘はついてないさ。少なくとも俺にとってのモノだから」
「本当に貴方って人は……」
彼女が呆れたように溜息をつく。
何度も何度も見てきた表情。
「ラスリー……」
彼女が名を呼ぶ。
かつて、そう呼んでくれたように。
そして、ちらりとこちらを向いた後、彼女は言いにくそうに目線を下げた。
「――――守ってくれて、ありがとう」
ようやく壊れた温かくも苦しかった世界。
新たに始まる世界では、どうか君の隣に。
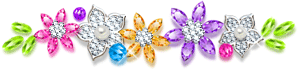

(c)aruhi 2008