four o'clock 若草色の姫君 3

「リシェル、こないだのお礼を持って来たんだ」
取り出した薄紅の紙に包まれただけの小さな箱にリシェルは首を傾げた。
戸惑いながらも受け取り、箱を開いたリシェルは中に入っている白い粉まみれの球状の物が何か分からなかったらしく、ますます首を傾げた。
「何? これ?」
「これはお菓子だよ。“フーアグ”って言うんだ。庶民のものだから、リシェルは食べたことがないかなと思って。でも、とっても甘くておいしいんだ。食べてみてよ」
こくり、と頷き、一つ摘まんだフーアグをリシェルは恐る恐る口へと運んだ。
そして、口に含んだ瞬間「美味しい!」と、若草色の瞳をキラキラと輝かせた。
リシェルは「美味しい、すごく美味しい」と笑いながら、白い粉砂糖が口と手の周りにたくさん付いているのも気にせず、パクパクとフーアグを食べ続けた。
あっと言う間に空になってしまった箱を名残惜しそうに見つめるリシェルが可笑しくて、俺は約束したんだ。
「また明日、フーアグを持ってくるよ」と。
翌日、リシェルは「ラスリー!」と手を振りながら一直線に俺の元へと走って来た。
そんな彼女に向かってフーアグの入った薄紅色の箱を掲げると、リシェルはパッと顔を輝かせた。
リシェルの喜んでいるその顔があまりにも可愛らしかったから、きっとこれが始まりだったのだ。
今思えば何と馬鹿なことをしたのだろう、とかつての自分に呆れかえる。
今のリシェルが聞いたら、自分の犯した失態にものすごく嫌そうに顔を歪めるかもしれない。
けれど、当時の俺は、早速フーアグの箱を開けて幸せそうに微笑むリシェルの笑顔をもっと見たいと思っただけなのだ。
フーアグをつまんで食べようとしているリシェルに向かって、いいことを思いついた、とばかりに「リシェル、リシェル、こっちにもいいものがあるんだ」と彼女に呼びかけ、ポケットから今日見つけたばかりのあるモノを取り出した。
リシェルが興味ぶかそうに握られた俺の手を見つめる。
ゆっくりと開かれた手の中、「ゲコー」という鳴き声と共に顔を現したのは鮮やかな緑を身に纏った蛙だった。
リシェルが固まる。
そして、俺の手の上に乗っている緑の物体が何かを理解した途端、リシェルは「キャーーーー」と叫んで一目散に駆けだした。
リシェルが振り上げた薄紅の箱から、白く甘い粉砂糖に包まれた丸い菓子がパラパラと降り、辺りに転がった。
リシェルがなぜ逃げたのか理解できなかった俺はしばらく呆然と立ち尽くした。
そして、優れた才を持つと一目置かれていた当時の俺が導き出した答えがコレ。
「そっか、リシェルは蛙はあまり好きじゃないのか」
そう、ここまでは良かった。問題はここからだったのだ。
「そうだな。蛙はちょっとぬめぬめしてるからな。やっぱり虫の方が良かったか。今度は虫を捕まえてリシェルに見せてあげよう」
うんうんと一人納得して頷く。
ようやく逃れることのできた蛙は柔らかな草の上に舞い降り嬉しそうにもう一度「ゲコー」と鳴いた。
こうして、俺のリシェルを追いかけまわす日々が幕を開けた。
ただ、もう一度、リシェルのあの笑顔を見たいが為に。
それが、却ってリシェルの笑顔を遠ざけているとも知らず。
「―――アトラス!!」
涙を浮かべて逃げて行くリシェルを今日もアトラスが受け止め背中に庇う。
「ラスリー、またお前か……」
アトラスが少し怒ったような呆れたような目で俺を見据える。
けれど、俺はその後ろで見え隠れする金の髪を持つ女の子がなぜ泣いて逃げるのか、気になってしょうがなかった。
だから、その日アトラスに聞いてみたのだ。
「リシェルはどうして、いつも泣いて逃げるんだろう?」と。
確かに、アトラスは的確な答えを返してくれた。
けれど、またもや「蛇や虫を怖がっているなら、トカゲにすればいいのか」と勘違いしてしまった少年の間違いを正してやっても良かったのではないか、と思う。
おかげで俺はやはり次の日もリシェルに泣きながら逃げられることとなった。
もはや日課となってしまったこの一連の行動。
リシェルは俺を見るだけで、逃げるようになってしまった。
例え、その時、リシェルが嫌がるようなものを持っていなかったのだとしても。
「本当に全く思い当たりもしなかったのか」と聞かれると「全く思い当たらなかった」と答えることしかできない。
それには、俺の周りの環境も大きく関係していたと思うのだ。
まず、初めに育った修道院では、子供達は皆、虫や蛇、蛙を捕まえて遊んでいた。
男も女も皆。
嫌がっていたのは修道院で働く大人たちだけ。
それも、虫などが嫌いという訳では無く、「命あるもので遊ぶのではない」ときつく戒める為。
ヒルデルト家も少しばかり変わっていたのかもしれない。
下の幼い弟は俺が採ってやった虫をいつでも無条件に喜んだ。
父はなんだかんだで、一緒に採集をして遊んでくれたこともある。
母は、今思うと嫌だったのかもしれないが、俺が採ってきた虫を見て「あら、こないだ取ってきた虫よりもずいぶんと大きいわね。すごいわ」と、褒めてくれていたのだ。
けれど、リシェルが逃げる理由を教えてくれたのもまた、この両親だった。
リシェルを追いかけまわして三か月ほど経った頃、両親に相談を持ちかけてみたのだ。
息子の相談内容に、二人は頭を抱えた。
「ラスリー……。お前は、アリュフュラス家の姫君に何てことをしていたんだ」
「そんなことをしていたら、姫君に嫌われてしまうのは当り前ですよ?」
こうして、父と母に長々と諭された後、俺はようやくリシェルが虫や蛇などそういった類のモノを全て嫌って怖がっているということを理解したのだった。
とにかく、謝らなければ。
小さな俺はそう思い、次の日、城に来てすぐリシェルを探した。
広い庭園の片隅。
沢山の花弁を持った大きな赤い花々の元、黄緑の薄いドレスのリボンが揺れた。
「リシェル!!」
そう呼びかけると、彼女はビクリ、として急いで立ち上がる。
「―――あっ……」
こちらを見る若草の瞳が恐怖に染まっていくのを感じて、激しい後悔に襲われた。
声を掛けるのをためらっていると、リシェルはその隙をついて、ダッと駆けだした。
「ちょっと、待って、リシェル!!」
慌てて追いかけたはいいが、数歩遅れた為かリシェルの姿はもうどこにも見当たらなかった。
それでも、何とか謝ろうと、リシェルが消えた方へと走り出した。
探し始めてどれくらい経ったのだろうか。
空の真上にあった太陽は、今ではもう西の空まで来ていて、その輝きを橙色へと変えていた。
夕日を浴びて、城が、周りのあらゆるものが色を変える。
今日はもう諦めて明日にしよう、と溜息をつきながらトボトボ歩いていると後ろから背を叩かれた。
「アトラス!」
何冊もの本を抱えて傍に立っていた自分より少し身長の高い少年の名を呼ぶ。
アトラスは眉を顰めてこちらを睨んだ。
「ラスリー、勉強の時間をさぼってどこに行ってたんだ。おかげで不機嫌な教師共にいつもより多くの宿題を押し付けられた」
「―――へ?」
てっきりリシェルのことで何か言われるのかと思っていた俺は予想とは違うアトラスの言葉に間抜けな声を出してしまった。
「“へ?” とは何だ? ちゃんと聞いてるのか? 後で、もちろんラスリー、お前にも手伝わせるからな」
不機嫌そうな声を出すアトラスに自分が持っていた疑問を問いかける。
「アトラス、リシェルに会ってないの?」
「……会ってないが。ラスリー、またリシェルに何かしたのか?」
呆れたように吐き出されたアトラスの言葉も、その時の俺には初めの半分しか聞こえてなかった。
リシェルはいつも一番にアトラスの所へ逃げる。
それは、絶対だった。
探しても、探してもあまりに見つからないからアトラスに会った後、リシェルは部屋に帰ってしまったのかと思っていた。
リシェルの部屋まで行くのはちょっと怖くて、行けなかったのだ。
けれど、アトラスはリシェルに会っていないと言う。
「待て、ラスリー! そんなに慌てて、どこに行くんだ?」
後ろから聞こえるアトラスの問いかけに答えている暇はない。
俺は絶対に走るなと言われていた王宮の廊下を走りだした。
重く、高い扉を叩く。
中から顔を出した侍女が気付かれないほどに一瞬小さく眉を寄せたがそんなことには、かまってなどいられなかった。
「―――リシェルは?」
「……エリィシエル様は、まだ戻られていませんが。それが何か?」
やっぱり!
俺は元来た道とは反対の方向へと走り出した。
リシェルはきっとこの広い王宮の中で迷っているのだ。
リシェルが王宮内に住まってから半年と三月が経つ。
けれど、小さな女の子が短期間で王宮内全てを把握するにはこの王宮は広大で、複雑過ぎた。
昼間に探し回ったのは居住区である西棟だけだ。
生活の大半を西棟で行っているリシェルがもし西棟に居るなら自力で戻って来れないということはないはずだ。
それならばきっと、彼女は政務が行われている東棟に迷い込んでしまったのだろう。
それも、庭園から駆けだしたのだから、東棟の外に居る可能性が高い。
陽は刻々と陰りだす。
陽が落ちてしまうまで、そんなに時間は残されていない。
けれども、何とか夜になる前に見つけなければ。
俺は急いで東棟に続く渡り廊下へと向かったのだった。
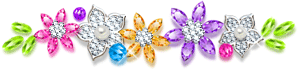

(c)aruhi 2008