four o'clock Trick or Treat!
アイカ × アトラウス

美しい飾り目のついた、けれども、すっきりと違和感なく纏まっている木でできた焦げ茶の大きな扉を二度、コンコンと叩く。
「どうぞ」と中から響く、低く落ち着いた、くすぐったく、けれども耳に心地よい声。
すっかり、馴染みつつある真鍮の取っ手を廻して、開いた扉の隙間から顔半分だけ覗き込む。
うっわぁ、今日もすっごい書類だな……
「何の用だ?」
お目当ての人物はちらりとも目もくれず、手元の書類へとペンを走らせて続けていた。
「王様、王様! お菓子をくれなきゃ、悪戯するぞ!」
私がそう言って両手を上げて、部屋に飛び込んだ途端、王様はびっくりしたように顔を上げた。
わーい、成功! 成功!
後ろ手に扉をパタンと閉めると、ニマニマとした顔で王様へと近づいて行った。
「びっくりした?」
「ああ、驚いた」
王様の青い目が驚きから、優しい目へと変わる。
私はこの瞬間が大好きだ。まるで、穏やかに凪いだ海みたい。けれど、そんな海ともまた違った不思議な色。
「ごめんね、仕事忙しそうなのに邪魔しちゃって」
「別に構わない。ちょうど少し休憩しようと思ってたところだ」
嘘つき。
バレバレだよ、王様。
いつもなら休憩も取らずに働き詰めだってこと私だってきちんと分かってるんだから。
でも―――
「私が来なくても、きちんと休まなくっちゃ駄目だよ!」
「ああ」
「――――――ぅわっと、王様! 不意打ちは禁止だってば!!」
「だが、アイカの反応はいちいち面白いからな」
「もう、人で遊ばないでよ……」
王様がくつくつと笑う。
ああ、私って本当に、この笑顔に弱いなあ。怒る気無くしちゃったよ……
キッと王様を睨み上げた目が、みるみるうちに威力を無くしていくのが分かる。
それなのに火照った顔は、なかなか元に戻りそうになくて、私はポスリと頭を王様の胸へと押し付けた。
そのままギュッと王様の体を抱きしめる。
ふわぁ~。人の体温ってなんでこんなに気持ちいんだろう。
温泉に入った瞬間のような、ほうっと溜息をつきたくなるような安心するこの感覚。
「これがさっき言ってた悪戯か?」
「へ?」
顔を上げると、ふわりと抱きしめられた。
お互いの顔が見えるくらい。軽く、優しく、でも、お互いの温もりを確かに感じる距離。
「“お菓子をくれなきゃ悪戯するぞ”?」
「―――ああ」
そのことか。
「さっきのはね、私の世界のハロウィンっていうお祭りの決まり文句なの。子供達が魔女やお化けなんかに変装して、いろんな家を渡り歩くんだよ。“お菓子をくれなきゃ悪戯するぞ!”ってね。それで、いっぱいお菓子を集めるの。あの世とこの世がつながる日でもあるらしいんだけどね。」
詳しいことはよく知らないが、日本で言うお盆だ。
―――って、でも、王様にお盆なんて言っても分からないからなぁ。
「それも、ニホンのお祭りなのか?」
「ううん。これはイギリス」
「イギリス?」
「日本と同じ島国だよ。ちょっと遠いんだけどね。ヨーロッパっていってフィラディアルと似た雰囲気の地方の国の一つ。日本にもあれば良かったんだけどね、ハロウィン。子供のころは憧れたんだぁ。だって、お菓子一杯貰えるんだよ? けどね、この頃は日本にもちょっと入ってきてるの。お店何かにはハロウィンの為のカボチャの提灯も売ってあるんだよ。かわいいんだぁ!」
「提灯?」
「あ、ランタン……ランプみたいな物のこと。」
「カボチャでランプを作るのか……?」
王様の形の良い眉の間に皺が寄る。
あは。考えてる、考えてる。
王様とカボチャ。似合わないなぁ。うーん……でもちょっとだけ可愛いかも?
ニマニマしてたら、頭の上にゴツンと固い衝撃が。
「―――い、痛い……」
どうやら頭に当たったのは王様の顎らしい。
うう。笑ってすみませんでした。
「……今度作ってあげるから、許して?」
「約束だからな?」
頬に柔らかで温かかなキスが触れる。
うわぁ! だから不意打ちは駄目だってば!
そろりそろりと顔を上げると、王様が優しい目で笑っていた。
うう。その笑顔も反則ですよ、王様?
けれど、その王様の表情が「そうだ」という呟きと共に厳しいものへと変わった。
両肩を掴まれ、真剣な青い瞳で私を覗きこんでくる。
何か、重要な話? 大変なことが起こったのかな?
王様の鋭い目つきに、自然と背筋がピンと伸びる。
「アイカ……さっきの言葉だが絶対にラスリーの前では言うなよ?」
「は?」
さっきの言葉って“お菓子をくれなきゃ悪戯するぞ”だよね?
それがどうしたって言うんだろう?
しかもランスリーフェン侯爵限定?
疑問符だらけの私に、けれど、王様は真剣な表情を崩さず(というか、きっと王様は真剣なんだろうね)言った。
「ラスリーに言ったら、何されるかわからないぞ?」
「うぇ? え? ……へ!?」
うーん。でも、確かに、それはちょっと怖いかも。
ランスリーフェン侯爵って楽しいけど、よく何考えてるか分からないところあるし。
何よりも、王様の目が“何かされたとき”の恐ろしさを切々と物語っていて私は素直にこくりと頷いたのだった。
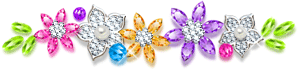

(c)aruhi 2008