four o'clock Trick or Treat!
アイカ × エリィシエル × ランスリーフェン

王様の部屋の扉とは違った純白の、けれど、やはり、こちらも凝った造りの大きな扉をコンコンと二度叩く。
「どうぞ」というお許しの言葉と同時に白い扉が開く。
「お菓子をくれなきゃ悪戯するぞ!!」
そう言うなり、勢い良くリシェルの部屋に飛び込むと、扉を開けてくれた侍女さんが目を見開いていた。
あ、すごく驚いてる……? 期待道理の反応だけど、なんだか、ちょっと申し訳ない。
「ほう。それで? どんな悪戯なんだ?」
予想外の声に顔が反射的に引きつる。
「ランスリーフェン侯爵……!」
王様のさっきの忠告が甦る。
ぎゃー!!
でも、これは完全に不可抗力だと思うの。だって、リシェルの部屋に居るなんて思わなかったし!
いや、確認しなかった私も悪いけど!!
でも、でも……!
「何してるんですか、ラスリー」
リシェルが溜息と共にランスリーフェン侯爵を睨む。
それと同時にランスリーフェン侯爵が吹き出した。
「いや、悪い。アイカの反応は楽しいから」
何か、さっきも同じこと言われたような気がするんですけど。
―――というか、本当にやめて下さい。さっきのはちょっと、いや、かなり怖かったですよ?
あれは絶対、半分本気だったよ!? だって橙色した目が光ってたもん!
「―――アイカ、迷惑だったら迷惑って、きちんと言っていいんですよ? それでも、この人には、ちゃんと伝わるかどうか分からないくらいです」
あれ、リシェル。いくらなんでも、それはちょっと酷くない?
「何言ってる。いつも、ちゃんと聞いてるじゃないか」
「それなら、何故貴方はここに来ているのですか。毎日迷惑だと申し上げているつもりなのですが。アイカも来たことですし、いい加減お引き取り下さい」
「まだ、茶も一杯しか飲んでないのだが……」
「ちょうど良かったではないですか。ちょうど一杯飲み終わったところだったのでしょう?」
冷ややかな目線を送るリシェル。そして、それを軽く受け流して微笑むランスリーフェン侯爵。
うーん。
どう見ても二か月前、全く病室から離れようとしなかった人物と同一人物とは思えないんですけど、リシェル。
進展が無いって王様が言ってたの本当だったんだ……。
ランスリーフェン侯爵は「ふうっ」と肩を竦めると立ち上がった。
「まぁ、どっちにしろアトラスに仕事を運ばないといけないから、そろそろおいとまするか」
「―――え? まだ仕事増えるの?」
あんなに書類がいっぱいあったのに?
ちょっとした非難を込めてそう問うと、ランスリーフェン侯爵は口の端を上げてニヤリと笑った。
「どうせ、アトラスが俺に気をつけろとか何とか言ってたんだろう?」
―――うっ! ばれてる! ばれてるよ王様!!
ほんっとうに、ごめん王様!!
後で謝りに行こう、と固く心に決めて、廊下へと続く扉に向かうランスリーフェン侯爵の背中を見送っていたその時
「―――っ!」
突然ランスリーフェン侯爵の足がカクリと折れて、床へとうずくまった。
「―――ラスリー!?」
「ランスリーフェン侯爵!?」
リシェルが血相を変えてランスリーフェン侯爵に駆け寄った。私も慌てて駆け寄る。
あの時のランスリーフェン侯爵の傷は今はもう塞がっていて仕事にも復帰しているが、まだ完全には治ってはいないと聞いている。
それはそうだ。あんなに深い傷を負ったんだもの。医者じゃないから良く分からないけど、治るのにはもっと時間がかかるはずだった。あまりにも、元気に振る舞っているから気付かなかっただけだ。
「ラスリー、大丈夫ですか? ―――ユージア、早くお医者様をここに!!」
「――――は、はい!!」
「―――いや、ユージア殿それは必要ない。」
緊迫した空気の中に響いた、今にも吹き出しそうなその声に、部屋に居た皆の視線が中央で、うずくまっている男の元へと集まった。
「ラスリー……?」
気の抜けたように彼の名を呼んだリシェルへとランスリーフェン侯爵が笑みを向ける。
「ちょっとした“悪戯”だ。」
その瞬間、力が抜けたようにリシェルが、へたりと床へと座り込んだ。
「……貴方なんかもう知りません!」
リシェルは立ち上がろうとして、でも力が入らなかったのか、その場に座り込んだまま顔を手で覆った。
同時に、その場に居た全ての侍女さん達の冷たい目線がランスリーフェン侯爵の元へと送られる。
もちろん、私だって送った!!
だって――――!!
「ランスリーフェン侯爵! そんなの“悪戯”じゃ、済まされないでしょう!? あの時、リシェルがどれだけ心配したと思ってるの!?」
ランスリーフェン侯爵が昏睡状態に陥っていた時、リシェルはほとんど飲まず食わず、ろくに睡眠もとらないで傍に付いていたのだ。
リシェルの侍女さん達もそろってウンウンと頷く。
これだけ、仲間がついてれば恐くなんてないんだから!
「悪かった、リシェル。ちょっと冗談が過ぎた」
ランスリーフェン侯爵が戸惑いながらも、リシェルの金色に輝く頭をポンポンと撫でる。
それから、ふっと困ったような笑みを浮かべた。
「―――本当に、リシェルに泣かれると弱いな……。どうすればいいのか急に分からなくなる」
そう言ったランスリーフェン侯爵は慣れた仕草でリシェルの前髪を掻きあげると、そこにキスを落とした。
それは本当に、あっという間の出来事で、しかも、私は人がそんなことしてるのなんて初めて見ちゃったもんだから、多分数秒固まってしまった。
恐らく、侍女さん達も同じ気持ちだったんじゃないかな?
中には本当に口をあんぐりと開けたまま、今主人にされたことを呆然と見ている侍女さんもいる。
「―――ちょっと、ランスリーフェン侯爵!! リシェルに触るの禁止!」
私の号令(?)と共に我を取り戻したらしい侍女さん達は一斉に大きく頷くと、主人の隣に座り続けているランスリーフェン侯爵をリシェルから引っぺがして連行して行った。
私は、ふんっと鼻を鳴らし、その様子をしっかりと見届けるとリシェルの元へと駆け寄った。
「大丈夫、リシェル?」
覗き込むと、リシェルは一つ大きく息を吐き出して、顔に被せていた手をどけた。
―――うっわぁ。
リシェルのこと美人だ、美人だと思ってたけど、泣き顔まで可愛い!
未だに潤んでいる若草色の瞳は、まるで若葉の上の朝露みたいだ。
うん。やばいよ、本当に。ランスリーフェン侯爵に見せなくて正解だよ。
耐え切れずに私はリシェルをぎゅっと抱きしめた。
「……ラスリーなんか嫌いです」
くぐもった声が耳の横から聞こえる。私はリシェルの背中を撫でながら頷いた。
「うん、そうだね。あの性格直してもらわないと好きにはなれないね」
「好きになられては困りますよ。こんなにエリィシエル様に心配を掛けて……。この頃、昔に比べて大分株が上がって来たところでしたが、元通りですね。いや、それ以下でしょうか。簡単にエリィシエル様を差し上げる訳には行きません」
ユージアさんの言葉に周りの侍女さん達が再びウンウンとそろって頷いた。
私はユージアさんに同意しながらも、ただ、ただ苦笑するしかなかったのだけど。
「恥ずかしい所を見せてしまいましたね」
出された紅茶を飲んでいると、リシェルが少し決まり悪そうに、そう呟いた。
リシェルと私の間にはたくさんの、しかも全部異なった種類のお菓子が並んでいる。
「そんなことないよ。私になら、もっとじゃんじゃん見せちゃっていいから」
普段、リシェルは落ち着いて、少し淡々としたところがある。だから同い年でも私から見ると、お姉さんに見えるんだろうな。
だけど、多分そうじゃないんだ。
リシェルはきっと人よりも自分の感情を綺麗に隠してしまうんだろう。
それもきっと大切なんだろうけど、誰か、リシェルが自分の気持ちをちゃんと吐露することのできる人がいればいいと思う。
それが、私だったらいいなぁと思う。
それにしても――――
私はコクリと紅茶を飲みながら向かいに座る少し目が腫れたままの友人を見た。
ランスリーフェン侯爵のあんな嬉しそうな顔、初めて見た。あ、困った顔もか。
きっとリシェルだけに向けられる顔なんだろうな。
王様が私に向けてくれるみたいに。そして、私が王様に向けるみたいに。
侍女さん達に引かれていく時のランスリーフェン侯爵の顔。リシェルが見たら、どう思ったんだろう?
リシェルだって……ねぇ?
人一倍ランスリーフェン侯爵のこと心配してるんだってこと、見てて分かるし。
いろいろ言い合ってるのも、言い合える相手ってことだよね。
これはもう、時間の問題かな?
微笑ましいんだけど…………もう! なんだか、じれったいなぁ!!
「そういえば……」
「え、何?」
自分の考えに没頭していた私はリシェルの呟きで紅茶から顔を上げた。
リシェルが首を傾げる。
「“お菓子をくれなきゃ悪戯するぞ”と言っていましたが、アイカは、そんなにお菓子が欲しかったのですか?」
―――あ、覚えてたんだ。
でも、どうして今更その質問なのリシェル?
ついさっきまで、ランスリーフェン侯爵のことで泣いてたのに!?
「あ、さっきのはね、ハロウィンっていう私の世界のお祭りの決まり文句なんだよ」
―――やっぱり、リシェルとランスリーフェン侯爵がくっつくのは、まだまだ先の長い話かも……?
そう思いながら、私は王様に説明したばかりのハロウィンの解説をリシェルにも再び繰り返したのだった。
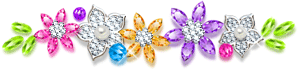

(c)aruhi 2008