four o'clock 1:歩きだした足音

アイカが帰って来た。それは何よりも嬉しいこと。
けれど、それだけでは済まされない問題が彼女の帰還と共に浮上したのも事実。
宮廷内においてのアイカの存在意義は、前回の騒動で一変した。
アイカを襲ったデルクラン家は未来永劫、宮廷に上がることが許されぬほどに厳しく罰せられたのだ。
その処断がデルクラン家に下ったことは宮廷を激しく震撼させた。
どこからやって来たのかも知れない異国の女。
いつの間にか王の傍に仕えていた黒髪の愛玩具。
その程度の認識しか持たれていなかったアイカ。
だが皮肉にもアイカの命が狙われた先の一件こそが、アイカの重要性を宮廷中にはっきりと知らしめることとなった。
大貴族の中でも第三位の権力を誇っていたデルクラント家。
本来ならば、失脚など有り得るはずのない家に下された厳しすぎる処断。
その瞬間、アイカの名は王にとってかけがえのない存在であると、貴族たちの間にはっきりと刻まれることとなった。
アイカはそんなことがあったという事実を知らない。
なぜなら、彼女はその時、すでに元居た自分の世界へと戻っていたのだから。
だけど、今回は違う。
彼女が帰って来たのは、良くも悪くもアイカという存在がすでに認識され定着してしまった場所なのだ。
彼女を危惧する声は当然ながら少なくはない。彼女を利用しようという声は到底、数えられないほどだろう。
そして、彼女はそのこともまだ知らない。
いずれは分かってしまうこと。
知って欲しくないといくら私が願っても、彼女はきっと気付いてしまうだろう。
噂は巡る。そこかしこに。
様々な憶測と共に、膨れあがっていた噂の蕾は、アイカが戻ってきたことで一気に弾け、花粉をまき散らしながら、次の花へと巡り始めた。
だけど、その結果として彼女の朗らかな笑みが消えてしまうことだけは絶対にあってはならないことだ。
アイカの笑みが失われることを少なくともここに集った者達は望んでなどいない。
だから、私は言う。
国王であるアトラウスと宰相であるランスリーフェン、この宮廷内において最も力を持つ二人の幼馴染たちへと。
「アイカの部屋を王妃の部屋へと移しましょう。それに伴うアイカへの妃教育は私が担当いたします」
アイカにアリュフュラス家の庇護が付いていることを公に知らしめること。
そして、次期王妃として一番近い場所にいる者こそがアイカであると改めて知らせるのだ。
それが、今、私に考えられる唯一で最大のアイカを守る術。
陛下は頷く。その青の双眸に鋭さを湛えて。
「分かった。リシェルの言う通りにしよう。そっちのことについては全て任せてもいいか?」
「もちろんです。愛らしいだけでなく、立派な貴婦人に仕上げて差し上げますよ」
「随分と頼もしいな」
「前に、陛下と約束しましたからね」
「そうだったな」と笑みを浮かべた陛下に、裾をつまんで正式な礼を返す。
「陛下の隣にあるべき花は、私にとっても守るべき花ですから。私の力が及ぶ範囲で全面的に協力させていただきます」
顔を上げて、陛下の横に立っている赤毛に橙の瞳を持ち合わせた男を見る。
「裏のことは……」
ラスリーは僅かに口の端を上げて、了承の意を片手で示した。
「ああ、そっちのことは俺に任せて下さい」
宮廷の裏側は誰よりも私よりもラスリーの方が遥かに適任だ。
「恐らく、貴方に敵う者などこの宮廷にはいませんからね……」
「全くだ……」
どこか感慨の多く入り混じった視線を私と陛下から向けられ、ラスリーはくつくつと笑いを洩らす。
「一応、褒め言葉として受け取っておこうか。まあ、実際のところ二人ほど敵わない者はいるんだけどな」
「だ、誰ですか……!?」
「そんな奴いるのか!?」
同時に返された私達の驚きの問いには答えず、ラスリーはスッと顔を引き締め、口を開いた。
「問題ない。また、この間のような失態を犯してしまってはたまらないからな。今度こそ、絶対に誰も動かせはしないさ」
一度浮かべられた冷笑はすぐに影を顰め、穏やかのものへと変わる。
「そういえば、リシェル。珍しい茶が手に入ったんです。後で伺ってもよろしいでしょうか?」
「生憎、この後はアイカと庭園に降りる予定なのですが……」
張り詰めた空気を一気に拭い去った男に呆れと同時に苦笑を洩らす。
確かに、もうこれ以上話すことはない。とりあえず今日は、ここで切り上げるべきだろう。
「リシェル、俺も邪魔してもいいか?」
「陛下がそう仰るのなら……」
顔を顰めたラスリーに向かって、陛下が苦笑しながら肩を竦める。
「それなら、庭園でお茶にしましょう。アイカもきっと喜ぶでしょうし、駆け引きはここから始まります」
アイカの存在を次期王妃として認めさせること。
他に取って代われる者はいないのだと宮廷を行き交う誰もに今以上に知らしめ、認めさせること。
それが私達にとって最重要課題である共に、最優先事項である。これらを成し遂げることこそがアイカが彼女自身を守る手立てとなりうるのだ。
けれど、まだ、アイカはこのことを知らない。
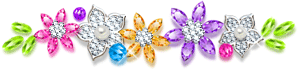

(c)aruhi 2008