four o'clock 2:お茶会は庭園で

「え? 部屋を移動するの?」
秋の花が咲き誇る庭園でのお茶会。話を切り出した私に向かって、アイカは問うた。
普段とても元気が良いにもかかわらず、どこか不安げな彼女は、隣に座る陛下を見上げる。
「大丈夫だ、一応部屋は広くなるぞ?」
「……王様、そういうことじゃないんだけど。というか、今だって充分広いよ」
的外れな答えを返した陛下に、アイカは素直に眉を寄せて少しばかり彼を睨む。
けれど、それすらも今では微笑ましく見えて、私は苦笑してしまったのだ。
「アイカ、大丈夫よ。移動と言っても新しい部屋も大して私の部屋からは離れてないわ。私の部屋からちょうどニ、三部屋隔てたところにあるの」
アイカは「そうなんだ」とホッと安堵の溜息をつく。
私はそんな彼女を見ながら一口、ティーカップに入った亜麻色に輝く茶を飲むと、アイカに向かって微笑んだ。
今、私達が使っているのは王妃候補の部屋。そして、アイカがこれから移るのは今までは使われていなかった王妃の部屋。
宮廷内で最も美しいとされる王妃の部屋に誰かが入った瞬間、王妃候補の部屋は今までの意味を失くす。そして、新たにその部屋に入った者は、王妃に連なる者。つまり、王妃を支える者として周りから認識されるのだ。
「私の部屋は変わらないので、いつものように遊びに来てくださって構いませんよ、アイカ」
「え、リシェルは変わらないの? 新しく変わる部屋が私の部屋と近いのかと思ってた」
私は頷く。「ええ、もちろん」と。
なぜなら、私は今居る部屋から退く気など塵ほども無いのだから。
けれど、アイカは部屋自体が特別な意味を持つことなど、まだ知るはずもないのだ。だから、彼女は不思議そうに首を傾げる。
「じゃあ、私だけ部屋を移動するの?」
「ええ。実はね、アイカの部屋は元々他の方の部屋だったのよ。けれど、今度その方が王宮に戻ってくることになったから部屋を空けてもらわなければならないの、ごめんなさいね」
これは本当のこと。彼女は王妃候補と言うよりは、私の友として宮廷に上がってくれていたのだけれど。
「そうなんだ……。ねぇ、その人ってリシェルの友達?」
「ええ、そう。カザリアという名なの。きっと、アイカもすぐに親しくなれると思うわ。彼女が帰ってきたらすぐに紹介するわね」
「うん。楽しみ」
何の心配も垣間見え無くなった彼女の笑みに、私もどこか安堵する。
「―――しかし」とラスリーは切り出した。
「カザリアが帰ってくるのですか……」
端正だと周りの貴女達からは言われている顔を、ラスリーは珍しくも歪めた。
その表情同様、渋さの滲む言葉の意味に私と陛下は苦笑する。
「そういえば、ラスリーはあまり仲が良くなかったな」
「良くない、というか、反りが合わない」
「貴方は昔から何かといってはカザリアに突っかかられていましたからね」
「ようやく結婚して旦那の所へ行ったから平和だと思ってたんですけどね……」
「けれど、私はカザリアが大好きですよ」
「……だから厄介なんですよ、エリィシエル姫?」
意味が分からずキョトンとする私の向かい側で、アイカが吹き出す。
なんだかとても面白そうに笑うアイカの姿に、ラスリーはますます顔を歪めた。
「ねぇ、ねぇ、カザリアさんってどんな人なの?」
「顔だけは綺麗ですね」
陛下が苦笑しながら、ラスリーの言葉を受け継ぐ。
「ああ、綺麗だな。宮廷内ではかなりもてていたと思うぞ。あとは、元気」
「そうですね、アイカとはまた違った元気の良さですよ」
「へぇ~」とアイカが相槌を打つ。
「カザリアさんかぁ、早く会ってみたいな。そうしたら何して遊ぶ、リシェル?」
肘を付いた両手に顔を乗せ、ウキウキと近い未来に想いを馳せているアイカに、けれど、私は釘を刺す。
「アイカ、遊んでばかりはいられませんよ。とりあえず、今日練習した字を見せて下さいね」
手を差し出すと、アイカの顔が引きつった。
だけど、これこそがこのお茶会の本来の目的だったのだ。陛下とラスリーが加わることが決まる前から、私はアイカの字の添削をすることを彼女と約束していた。
フィラディアルの字を覚えたいと言って来たのはアイカ自身だ。確かにそれは必要なことでもある。だからこそ、彼女の願いは聞き入れられ、先週から先生がつくようになった。
けれども、やはり、こことは異なる世界から来た彼女にとってフィラディアルの字は難しいらしい。だからこそ、先生に出された彼女の課題を、私はアイカに会う度によく添削しているのだ。
しかし、「まだあまり自身が無い」と言うアイカはいつも渋々と課題を差し出す。
やはり、今日も溜息をつきながら、けれど、きちんと持って来ていたらしい一枚の課題の紙をアイカは取り出した。
「何と言うか……下手だな、アイカ」
庭園に居ることも忘れ、いつもの口調でそう言い放ったラスリーを睨みつける。
「何てことを言うんですか! とても上達したのですよ?」
「―――これで、か……?」
ラスリーが私の手元にあったアイカの課題を掴んで、ひらりと掲げた。
そこに書かれている字は確かに美しいとは言い難い。だけど、かろうじて読めるほどのものだ。アイカがフィラディアルの字を習い始めた当初のものよりかは格段に上手い。アイカに教授している先生が泣いて喜ぶほどに彼女の字は確実に形がとれるようになってきていた。
「読めないことは無いぞ。本当に上達したじゃないか、アイカ」
「ううっ」と呻き声を出し、小さくなってしまったアイカの黒髪を陛下はポンポンと撫でる。
「それに、この短期間で字を読むことはもうある程度できるようになったのですから、すごいことですよ、アイカ」
「だって、リシェルが綺麗な絵本貸してくれたから。どんな話かも気になったし、読んでみたくって。だから、それはリシェルのおかげだよ」
「けれど、それもアイカの努力があってこそでしょう? 本当にアイカは良く頑張っていると思います」
彼女が少し照れたように微笑する。
だが、ラスリーは呆れたような目を向けて、溜息を落とした。
「……二人とも甘すぎるだろう」
「ランスリーフェン侯爵! 貴方は少し黙っていて下さい!」
上昇したかに思われたアイカは、再び激しく落ち込んでいった。そんな彼女を、陛下は苦笑しながらも穏やかな目で見つめる。
「ですが、字を覚える以外にも覚えなければならないことが、まだたくさんあるのですよ?」
ラスリーの言葉に、アイカはガバと顔を上げた。その表情は何とも不安そうであり、とても嫌そうでもある。
そして、何よりも、彼女がそのことについて全く知らなかったことを私に告げた。
「―――陛下、アイカにまだ何も伝えていなかったのですか?」
彼女が覚えるべきことは、部屋を移ることで発生する対処を別にしても、彼女がフィラディアルに帰ってきた瞬間から決まっていたことである。と言うよりは、彼女が帰ってくる前から決まっていたと言った方が正しい。
「悪い、すっかり忘れていた……」
陛下は苦笑いを浮かべた。陛下の心中も分からなくはない。アイカが帰って来たのが嬉しかったのは私も同じなのだから。
「けれど、困るのはアイカなのですよ。せめて心の準備くらいさせてあげないと、いきなりでは驚いてしまいます。まぁ、私が確認しなかったのも悪かったのですが……」
首を傾げて説明を待っているアイカに向かって私は口を開く。
「アイカ、貴女には明日から習字の他に礼儀作法を含めたいくつかの授業が加わります。私ももちろん手伝いますが、恐らく結構大変ですよ。なんせ舞踏会まであと一か月しかありません。それまでに完璧にものにしておかなければなりませんから」
「舞踏会!? 踊るの!? 私が!?」
予想道理ひどく驚いていてしまったアイカへと私は頷きを返す。
「ええ、もちろんですよ。アイカが踊らなければ、どなたが陛下と踊るのですか」
「リシェルとか!」
「無理です。諦めて下さい」
なぜなら、今では皆がすでに私が妃候補から外れていることを知っているのだから。それにヒルデルト家の庇護を示す橙の首飾りは今も私の首元で揺れている。
「舞踏会が開かれるのは、星夜祭。毎年開かれるフィラディアル独自の祭りです。街でも、ここ王宮でも一晩中盛大な宴が開かれます。王宮には宮廷中の貴族が集まるのですよ」
アイカは机に顔を突っ伏した。
「だーーー! なんか余計嫌だ!」
「必死にやればなんとかなるだろう」
「何とかって、ラスリー侯爵! みんなの前で王様に恥かかせることになっちゃったらどうするの!?」
「別に俺は構わないが。大体そんなの恥ではないだろう」
「でも、私のせいで王様が何か言われたりするのは嫌なの!」
勢いよく起き上がり、陛下に向かってそう宣言したアイカへと私は笑みを向ける。
「それなら頑張りましょう、アイカ。嘆いても仕方がありません。けれど、その意気ならきっと大丈夫でしょう。アイカさえ完璧にこなせれば他の誰にも文句は言わせませんし、言えるはずもありません。私は結構厳しいですからね。覚悟していて下さいよ?」
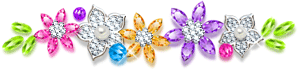

(c)aruhi 2008