four o'clock 8:花うら

太陽はとうとう真横まできてしまって、赤々と燃えるように空を彩る。綺麗な赤が、ぼんやりとした視界にやけに映えて、夕日が目に染みるってこういうことを言うんだなぁと思った。
カザリアさんが帰った部屋の中、また一人で座りこむことしかできない。話すことはできた。きっとぎこちなかったけど笑うこともできてた。リシェル達に言ったことだって、嘘じゃないし、そうしたいと思ってる。
でも、カザリアさんを見送った途端これだ。手を振って扉を閉めた瞬間、ふっつりと糸が切れたように、力が抜けかけた。なんとか寝室まで戻って来て、この部屋に居てくれる侍女さん達に心配をかけないようにと閉じこもる。
こんな自分が嫌でたまらなくって――でも、ここが今の私の限界だった。
それをまるで見計らったかのようにやって来るんだから、王様も相当意地が悪い。
王様は静かに静かに部屋に入ってきた。人払いをする声も妙に落ち着いていて、ああ、こういうことに慣れている人なんだなって、実感してしまう。
全部知っているんだなって、全部知っていたんだなって。ただ私が能天気だったから、見えなかっただけなんだ。隠してくれていたんだ。つきつけられて、初めて気付くなんて遅すぎた。なんて愚かだったんだろう。
王様は、ベッドの縁に腰かけて、「アイカ」といつも通りに私を呼んだ。
王様が座った分、このベッドは傾いて、だから私の座っている場所も自然と傾いてしまう。
私は、この人の前でもちゃんと笑えるのだろうか。
「…………」
「王様」って呼び返せない。「何?」って聞けなかった。口は開けたのに、すぐに閉じてしまった。じゃないと、別の言葉を言ってしまいそうだった。
それなのに、王様はゆっくりと頬を擦ってくれた。「ごめんな」と言った。
「悪い、アイカ。遅くなった」
「――ちがうの、遅くなったのは私の方だよ」
頬にあてられた温度の低い手が気持ちいい。目をつむりたくなった。まだ何も気づいてはいないのだと、そういうことにして逃げてしまいたかった。
王様は穏やかに微笑んだ。なのに、静かな青色の瞳には、泣きそうになっている自分が映る。だから、やっぱり私はこの人の前では無理に笑うことはできない。
「王様……ごめん、分からないよ、私」
カザリアさんが言ってくれた言葉と逆のことを口にする。
「だって、私、知らないよ。王妃なんて知らない」
本当は知っていなければならなかったのに。“王様”の隣に立つべき人は“妃”でなければならないなんて、考えなくても分かるようなことだったじゃない。
ううん、知識としてなら、とっくの昔から知っていたんだ。それこそ、本当に小さかった子どもの頃から。ただ、王様に置き換えられなかっただけ。自分がその立場に立つなんて考えもしなかっただけ。ちゃんと理解できていなかったのは私だ。
「だけど、そんなの知らないんだよ。分からないよ、王様。だって、私はまだ二十歳で、……私の世界では結婚なんて友達となんとなく話したりするだけだよ。私の歳じゃまだ実感湧かない子の方が多くって……。無理だよ、分かんないよ。だって、王様といたかっただけだった。そんなことまで、考えていられなかった」
ただ嬉しすぎたんだ。またここに戻ってこれたことが。王様たちに会えたことが。それだけだった。
「王様……私、王妃なんて」
これは自分の中にある弱さだけの問題じゃない。
王妃の座は私には重すぎる。想像なんてつかないくらいの責任がつきまとうのだろう。
今回はフィラディアルに来ることができた。でも次は? やっぱり保証なんてどこにもないんだ。ここから帰れないと決まっていたのなら、まだ良かったのかもしれない。だけど、ここにずっと留まれる――その保証だってどこにも見つけられない。
もしも、今回みたいに、しばらくの間いることも可能で、行き来できたとしよう。でも、そこには私の意志が介在しない。訳の分からぬ力に引っ張られてくるだけ。力を自由に操作したりはできないのだ。
つまり、日本にいる間は私の意志に関係なく、ここにはいられないということ。王妃の不在などあっていいはずがない。
だってフィラディアルの地理も歴史も、教えてもらっていたことは全部王を支える為の手段につながるに違いない。だけど、私にはきっとそれができない。ただでさえ王様を支えられる自信なんてないのに、ここにいられないなら、“王様”を支えることが不可能なのは決定的じゃないか。
それに、私にはまだ選べない。どちらか好きな世界で生かしてあげよう、と選択肢を与えられたとしても。家族も、友達も、親しんだもの全てを手放す決心だってつけられないに違いない。
「王様、私、王妃になれる自信ない。なっちゃいけない、と、思う」
頬にあった王様の手を外して、ゆっくりと下ろす。本当はもっと慰めてもらいたかった。
「私、ちゃんと王様のこと好きだけど。それは誰にも負けたくないけど。だけど、それだけじゃきっとだめなんでしょう?」
私は知っているんだ。だから、聞いた。王様はきっと全部受け入れてくれる。とても、甘いのだ。ラスリー侯爵が怒るくらいに。だからこそ、この人は、引きとめたりなんてしてくれない。
沈黙は長くは続かない。「本当のところは大丈夫だと言いたいけど」と彼は微かな自嘲をのせてさえも、やっぱり言う。
「これは俺の我儘だったから、アイカのしたいようにするといい」
慣れ親しんだ手がくしゃくしゃと頭を撫でる。その所為で、とうとう俯いてしまった私は握りしめた王様の手を見ていることしかできなかった。
「なぁ、アイカ? アイカが立っている場所は、アイカが言ったように絶対的な安定を持っているものではない。アイカには俺たちが知らないアイカ自身が生まれ育った世界があることは理解している。ただフィラディアルにいられる間は、アイカが宮廷に“いるべき人間である”とした方が何かと都合が良かったんだ。星夜祭は宮廷の一員であると示す為の機会。この部屋に移ってもらったのも同じで一番手っとりばやい方法だと思ったからだ。それに体制が一番整っているのがここだった」
来て、と王様は静かに立ちあがって、私の手を軽く引いた。この部屋の右隅、扉とは対角に備え付けてある本棚の前で立ち止まる。王様は繋いでいた私の手を離すと、膝をつき、最下段の本を抜き出して、床に重ね始めた。
一体何をしているのだろう。本棚の一番下の棚に並べられていたのは大型の本。大学の図書館でよく見た美術図版よりもサイズが一回りか二回り大きくて、厚さも数冊を一冊にまとめたぐらいの結構な厚みがある。前に王様の部屋でも同じものを発見して、見せてもらったことがあった。フィラディアルと周辺の諸国、この世界の地図が編纂されているものだ。
王様は左端から五冊取り出したところで、棚の奥を探りだした。ついで、パカリと何かが外れたような音がする。
手招きに促され、私も王様の横にしゃがみ、本棚の中を覗き込んだ。
覗いてみて驚く。取り除かれた本の代わりに、ぽっかりとした穴があった。さっきの音は、棚の奥側の板を外したせいだったらしい。棚の床にそれらしい板があった。
開けた穴は暗くて先が見えない。だけど、穴からは、ほんの少しひんやりとした風が流れてきた。
「王様、これ……」
「ああ、外に繋がっている。万が一の時の為の抜け道だ。王族の部屋にしかない。今のフィラディアルでは、ほとんど必要とされていないけどな」
思わず仰ぎ見ると、王様は苦笑した。
「カザリア嬢たちも知らない。知っているのはラスリーとリシェルくらいだ。昔、母が臥せっていた時に何度か三人で遊んだからな」
外からこの部屋に入り込もうとする度にこっぴどく怒られたという。確かに、本棚の奥から壁をコツコツと叩かれでもしたらびっくりしそうだ。「入れて」と乞う声が子どものものだったら、尚更だろう。
城内だけでなく、城外まで続く道もあり、出口も一つだけではないらしい。幾重にも張り巡らされたこの隠し通路は、正しい道筋を知っている者でなければ、再び日にお目にかかれる可能性は無きに等しいと教えてくれた。
「使わないことに越したことはないが、万が一ということもある。自分の都合でアイカを別の世界で死なす訳にはいかない。ただここに移すと余計なことまで増えるからな。とりあえずは星夜祭だけに留めておくつもりだった。誰がアイカについているかはっきりとさせられる分、あれだけでも大分違うから。だけど、リシェルがアイカをここに移そうと提案してくれた」
「リシェルが?」
「そう。念頭にあったのは同じことだろう。リシェルがこの抜け道を忘れているはずがない。こないだみたいなことがあっては困ると思ったんだろう。ついでに、星夜祭前にも、アリュフュラス家がアイカを認め、アイカについていることも大々的に宣伝できると。それが分かったから、この部屋にアイカを連れてくることを受け入れた」
それだけだ、と王様は言った。少なくとも俺には他はついでだった、と。
「今度、帰ったアイカがまたここに来られるという確証がないことは俺も気付いている。アイカが戻ってこない時には迷わず別の妃を取るだろうし、それがこの世界の普通だ。だから、アイカが重荷に感じる必要はないし、強要するつもりもない。アイカのことに関しては、本当に俺個人の身勝手でしかないからな。それに付き合わなくてもいい」
王様の目はとても優しそうな色をしていた。とてもとても寂しくなるような色だった。「ただ」とこの人は続ける。
「また戻って来た時は単純に嬉しいと思う。戻って来てくれた時には何度だって歓迎する。アイカが嫌でなければ、その時だけでもいてくれたらいい」
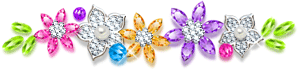

<<back <novel top> next>>
(c)aruhi 2009