four o'clock 7:落し物

「アイカ、入りますよ」
鳴る音はいつの時も高くて中身がない。そして、引き開く扉はいつの時も重くのしかかる。白い扉。蔦と鳥の装飾が丁寧に刻まれ、滑らかに磨き上げられたこの扉こそが、王妃の寝室とを隔てるものなのである。
この王宮内で唯一の扉。
隙間ほど開いたところで取っ手を持つ手は動きを止めてしまった。
情報は先程入ったばかり。アイカの気がそぞろだったと地理を担当しているテルナダから連絡が来た。こんなことは今まで一度も無かったのに、と。それと前後するように遣わされたヒルデルト家直属の従者――ラスリーからの伝言を受けて、『やはり』と思う。
アイカにも全てが知れたのだ。どちらにしても知られてしまうだろうと思っていたこと。知っていてもらわなければならなかったことでもあった。星夜祭までは残り後二週間。アイカが戻ってきてからは一ヶ月と半分。アイカを含めて動き出してからはちょうど二週間が経つ。だから、時間としては充分だっただろう。むしろこれまで、予想していた以上に長い期間猶予があったことに感謝すべきかもしれない。
それでも、開いた隙間は広がらなかった。
「……リシェル」
「はい、分かっています」
カザリアの手が肩に置かれる。促されるように、残りの扉を一気に開いた。
部屋の中、大きな窓からは、傾き始めた午後の光が降り注ぐ。
寝台の上には座り込んでいるアイカ。彼女は窓に背を向けて、光照らされる壁をぼうっと眺めていた。動くのは時折瞬かれる彼女の瞼と睫毛だけ。私たちが入ってきたことにさえ、アイカは気付きはしなかった。
「アイカ?」
顔はゆっくりとこちらへと向けられた。何も映していなかった表情は、けれど、私たちを見出したからか、次第に、わずかな微笑みをたたえた表情へと変わっていった。
「あれ、リシェル? それにカザリアさんまで。どうしたの?」
明るく紡がれた声音。そのことに私は驚いた。
同じく呆気にとられていたらしいカザリアは、だが、すぐに我を取り戻すとアイカのもとへと歩み寄り、両手を腰に当ててアイカを覗き込んだ。
「“どうしたの”じゃないわよ、アイカ。テルナダから今日の授業の様子を聞いた後に庭園でのことも聞いたから、見に来たのに」
「あぁ、そっか。ごめんなさい。いきなりだったから、さすがにびっくりしちゃって。テルナダ先生にも後で謝らなくちゃ」
アイカは申し訳なさそうに「へへへ」と笑いながら、こめかみに手をやった。
「でも、心配してきてくれたってことは、あの人たちが言ってたこと、やっぱり本当なんだ」
「……アイカ」
「あのね、自分でもちょっとおかしいと思ってたんだよ。だって、ここ前の部屋より広いどころか、リシェルの部屋よりもずっとずっと広かったから。王妃の、部屋だったんだね」
広いはずだよ、とアイカは呟いた。どうして気付かなかったのかな、と。
「アイカ。今まで黙っていたこと、ごめ―――」
「リシェルは謝らない」
カザリアはピシャリと言った。彼女は私を見据えて、それから、アイカの方へと向き直る。
「私も謝らない。確かに当事者であるアイカに話していなかったのは悪いことよ。だけど、私たちはアイカによかれと思って隠してた。フィラディアルのことほとんど知らない状態で告げても……私が初めて会った状態のアイカに告げても、きっと受け止められなかったもの。受け入れたように見えたとしても、それはきっと理解が伴ってなかったわ。ちっとも意味ないもの、そんなの。今だって難しいことは分かってるけどね」
アイカは俯いて、握りしめた自身の手を見つめた。カザリアはアイカの隣に腰を下ろして続ける。
「リシェルがずっと守ってきた場所はこういう場所なのよ」
「―――カザリアっ!」
「ダメ、これだけは一度言っておきたかったのよ。リシェルが認めてるからアイカが今更負い目に感じることなんて一つもないけどね、それでもアイカが初めてここにやって来た時、私がここにいたならきっと確実に貴女を追い返してたわ。そのくらい必死で守られてきた場所だもの、ここは。気付いてしまったらずっと笑っておくなんて無理でしょう?」
答えも、頷きも返らなかった。ただ握られている拳が力を増したのが分かったから、思わず手を伸ばして重ねてしまう。
「アイカ、大丈夫?」
傍にしゃがんで覗き見上げたら、アイカの笑顔はくしゃりと苦しそうに崩れていた。あの時とは違う、だけど、別のもので苦しそうに彼女の顔は歪む。
せめて彼女が真実を知ったときに傍にいられたら良かったのにと思った。
「アイカは大丈夫よ、リシェル。だってちゃんと分かっているもの。私が先生を引き受けたのはこのことをアイカに知っていて欲しかったから。だから、もう私にはすることないわ。後は知ったアイカがどう動くか。そうでしょう?」
「そうですが……、アイカ……」
ぎゅっとアイカの手に重ねる手へ力を込める。すると、その手は解かれて、崩れた拳の代わりに両の手が繋がれ握り返された。
俯いていたアイカはほんの少し顔を上げ、ほんのりとうち笑う。その笑みはぎこちなく見えたけれど、先程のものよりもずいぶんと柔らかなものだった。彼女は、自分で確かめるようにこくりと頷いた。
「うん、安心して、リシェル。星夜祭にはちゃんと出るよ。リシェル達が私にしてくれたこと無駄にできないから」
「無理はしていませんか?」
「今日の授業受ける元気はさすがにないけどね」
アイカが肩を竦めてみせる。いつもの元気のよさを取り戻してようにも見えた。
「それなら、今日の授業は私のだけにしときましょうか。他はお休みね。庭園に降りるのは辛いでしょうから、今日は特別にここで行いましょう」
「あ、それは助かります、カザリアさん」
カザリアがアイカの背をぽんぽんと叩く。
「ねぇ、アイカ。こればっかりは私たちにもどうしようもないの。だけど、私たちが傍にいることを忘れないで。私とリシェルだけじゃなくて、他にも」
「ええ、アイカ。私は今いる場所を今度こそは絶対に動きませんよ。今と同じようにずっとアイカの傍にいます。だから―――」
「うん、ありがとう」
今も、とアイカは繋いだ手を持ち上げてみせる。断ち切られてしまったから、私には繋がれた手を離さないようにすることしかできなかった。「いつもありがとうね」と彼女は礼の言葉を繰り返す。
「ええ、アイカ。貴女がそう言うのなら」
手を繋いだまま、私もアイカの隣へと腰を下ろす。
「他の授業は全て無しにしておきますから、今日はゆっくりして下さい」
ね、と首を傾けたら、頷きが返った。
カザリアが身を乗り出して、「アイカ」と彼女に呼び掛ける。
「一応聞いておくわよ? 貯め込むのもよくないしね。庭園で何と言われたの?」
「ええー……言いますか?」
黙ったまま揃って頷き返した私たちに、アイカはふっと困ったように吹き出した。
「ただ、“ごきげんよう、王妃様”って。意味が分からなくて聞き返したら、ここの部屋の意味を教えてくれました」
「うっわぁ、わっかりやすい皮肉ね。私の授業が何の役にも立たないじゃない」
「それだけで、どこの御令嬢か大体の見当がつきますが……」
「ええ。相変わらず、おつむが小さいと言うか何と言うか。もうちょっとひねってこればいいのに」
間に挟まれて戸惑っているアイカの腕を、カザリアはポンポンと叩いて慰めた。
「その程度のお嬢様方ならどうってことないわ。アイカは周りを気にせず、自分のことをよく考えなさい」
「……よく……」
「そう、“よく”」
カザリアはもう一度アイカの腕を二、三叩く。「そう、それでいいから」と。
扉がトントンと叩かれたのはその時だった。
顔を扉の方へと向けたアイカが「はい」と応答する。
「アイカ様、エリィシエル様への使いの方が来られています」
告げられた言葉を受け、アイカはこちらを向いた。私も思い当ることがあった。今日は約束があったのだ。そのことを、すっかり失念してしまっていた。使いとは、きっと来訪を告げに来たものであろう。
「アイカ……」
「うん、私はカザリアさんもいるし大丈夫だから、行ってリシェル」
ほらほら、とアイカに立ち上がらされて、微笑まれる。離れそうになった手を離す前に、またきゅっと握り繋いだ。
「アイカ、私はアイカが適していると思いますよ。だって、貴女はアトラスのことを考えている。アイカの考えていること全て分かってあげることはできないでしょうけれど、それだけは絶対に分かっていますから。私は貴女の答えを受け入れます」
だからどうか頑張って、と願いを込めてから彼女の手を離す。
部屋を出た私には、後のことを知ることはできない。
ただ自室に戻りながら考えてしまった。遠くかけ離れた道に私が立っていたのなら、どうしたのだろう、と。それでも、それは今ここにいる私ではないことも知っていた。だから、今の私が考えたものとは別の結論をきっと彼女は出したのだろう、とも。
「エリィシエル姫!」
自室に辿り着いた瞬間、迎え出た彼は満面の笑みを浮かべて抱きついてきた。昔から変わらぬ勢いのある抱擁に、深い安堵を感じてしまう。そうっと背に手を廻して、常なる挨拶を返す。
「また大きくなりましたね、グラン」
「今、成長期だからね、これからもぐんぐん伸びるよ」
腕を解いたグランはにっこりと口元を綻ばせた。紺の瞳は柔らかく細まる。
「約束をしていたのに、お待たせしてしまって、すみません」
「いいの、いいの。僕から頼んだんだから気にしないで」
ね? と彼は体ごと横に傾ける。その拍子にひょこんと揺れた茶色の三編みがなんだか可笑しかった。
「良かった、笑った。エリィシエル姫、入って来た時すっごく険しい顔してたよ」
こんなの、とグランは顎に手をあてがい、眉間に深い皺を寄せてむっと口を結ぶ。険しい、と言うよりは、睨めっこをしているような変な顔だ。つい笑い声を洩らしてしまったのも仕方がないことだと思う。
「何かありましたか?」
右手を取られたかと思ったら、朗らかに尋ねられた。
「どうしてあなた方は……」
「そりゃあ兄弟ですから?」
グランは嬉しそうに胸を張った。皆を言う前に、返された答えに苦笑してしまう。
血が繋がっていない彼らの見た目はちっとも似てはいないのに、つくられる表情は時々とても似通っている。
「それで?」
グランは再び問うた。勘が良すぎるのも困りものだ。
「何かあったのは私ではないのですよ。それよりも、グラン。ラスリーから聞きましたよ、マルシアローズ嬢のこと。良かったですね」
「あ、あ、あ、兄上!」
グランは顔を真っ赤にしてここにはいない兄に向かって恨み事を叫ぶ。ぱっと離れた手を彼はパタパタと振った。
「どうして聞いちゃったのですか!?」
「どうしてと言われても、聞いてしまいました」
「エリィシエル姫にこそは自分から報告しようと思ってたのに」
「ええ。おめでとう、グラン。星夜祭が楽しみですね」
もう随分と昔から彼の相談を聞き続けてきたのだ。結ばれたことが自分のことのように嬉しい。祝福をしても、し足りないくらいに、心から良かったと思う。
拗ねているらしいグランは、こちらを横目でちらと見ながら「僕も聞きましたよ」と言った。
「エリィシエル姫は兄上から首飾りを貰ったのでしょう?」
それは紛れもない事実なので素直に「はい」と頷く。だが、グランは顰めた顔のまま「なら」と続けた。
「どうして、つけていないのですか?」
せっかく兄上が贈ったのに、と不満げに告げられたことが理解できず、言葉を失ってしまった。そのままグランの顔を見上げていたら「首飾りです!」と言い返される。
「え?」
「だから、兄上がエリィシエル姫に贈ったはずの首飾りですよ!」
指摘されて初めて気付く。胸元に確かにあったはずのひんやりとした橙の石の感触がない。信じられなくて、手を当ててみたが、やはりそこには何もなかった。
「もしかして、どこかに落としたの?」
呆然としてしまった私に、グランが問う。
「落と、した……?」
それは絶対にあってはならないことだ。特に今は絶対にあってはならないことなのに。
グランの言う通り、落とした以外に考えられなくて、慌てて部屋の中を見渡す。
「ユージア!」
「はい」
同じ部屋の中にいて事態を把握しているユージアが他の侍女にも素早く的確に指示を出す。
「本当に落としちゃったの、エリィシエル姫」
グランが目を丸くして問う。信じられないとでも言うように。私もこんなこと信じたくはなかった。
あの石が持つ価値は今の状況において重大すぎるものなのに。
「あ、兄上に……」
「―――言わないでっ! 言わないで、グラン」
グランの服の袖に取り縋って懇願する。知られてはいけない。今は誰にも知られてはいけないのだ。
「グラン……お願い、誰にも言わないで」
知られてしまえばまた崩れてしまうかもしれない。あの時と同じようにいとも簡単にあっさりと。
けれど、今回のものは絶対に崩壊させてはならないのだ。今あるものだけは絶対に崩したくない。
つい今さっきもアイカにそう宣言してきたばかりなのだ。
「……エリィシエル姫が、そう言うのなら誰にも言いません」
約束します、とグランは固い声で誓う。
「……あ、ありがとう……」
グランの言葉にほっとして、彼を見上げる。
きゅっと握りしめた胸元には空気しか無かった。
それなのに、胸は息が詰まって息苦しくてたまらなかった。
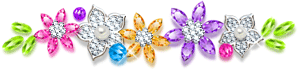

(c)aruhi 2009