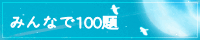予兆 05
「お嬢ちゃん! お嬢ちゃん! お嬢ちゃん!」
噂好きの女たちから隠し姫の部屋を聞きだしていたクニャは、待ち構えていた張本人が王の側近の青年に抱えられて回廊の角から姿を現したのを見て、歓喜に顔を輝かせた。
びくりと目を覚ましたシィシアは、大げさな手振りで駆けてくる豊艶な美女を映して目を瞬かせる。
「誰あれ」
「知るか」
己を抱き抱える青年に尋ねてはみたものの、彼自身も知らないらしい。きまり悪そうに視線を上向けた彼の不審な行動が気にならないでもなかったが、結局「妓女の誰かだろ」としか答えてくれなかった青年に、シィシアは「役立たず」とぼやいたのだ。
シィシアの言葉に怒り心頭したらしい青年は、むっつりと顔を歪めながらも、彼女を乱雑に扱ったりはしなかった。ただ、義務的にシィシアを寝台に下ろした直後、これで役目は終わったとばかりに、さっさと部屋をあとにする。
見知らぬ妓女と二人きりで取り残されてしまったシィシアは、自分の隣に腰を下ろした赤茶髪の女をまじまじと見つめた。
滑らかな小麦の瞼上に引かれた黄緑が、赤茶の睫毛と伴って翅をひらめかせる。陽光を灯し入れた橙色の双眸が、距離を測りかねている娘の様子を映して、柔らかに細められた。
親し気に取られた手に驚いたシィシアは思わずその手を引っ込めそうになる。けれども、妓女の方は大して気にした風もなく身を乗り出してきた。
「ずっと心配していたのよぅ? あの日以来見かけなかったもんだから。きっとどこかにいるんだろうってことは分かってたんだけどね」
朝になってもずっと目を覚まさなかったし、と妓女は続ける。息つく間もなく動き続ける妓女の厚みある唇を眺めていたシィシアは、記憶にない女を前に、考えることを早々に放棄した。
「誰」
「クニャよ。そっか、そういやお嬢ちゃんが、あたしのこと知るはずなかったわよねぇ」
ごめんごめんと謝る妓女は、シィシアの背をパシパシ叩きながら、ころころと笑う。
「お嬢ちゃん、あれから何か食べさせてもらった? これでよければ、さっき台所でこっそり貰って来たんだけど」
はい、とクニャから手に握らされた木の実にシィシアは微妙な顔になる。
「よく噛みなさいね」
「そうね」
シィシアは妓女に頷いてはみたが、貰った木の実を口にするのはやめておいた。手の内にある球状の固体の感触を持て余す。だが、しきりに口を動かしていたクニャが急に黙り込んだことに、シィシアは違和感を覚えて小首を傾げた。
ついさっきまで表情を賑やかに変えていた妓女は、息をつくと、もう一つ持ってきていた皮の小袋をシィシアの前で取り出した。クニャは結ばれていた袋の口をほどき、膝の上に中身を広げてみせる。
平たく潰れて皺が寄っているそれは、どうやら果実を干したものらしい。ほとんど匂いはしないのだが、黒く爛れた物体はいやに苦味を帯びて見えた。これが何であるのか。シィシアの視線を汲んだクニャは「王様から渡されてたのよ」と肩を竦める。
「ジブラクの煮干し。子を流す道具よ。あたしはあんまり好きじゃないんだけど。他にも薬はいくらもあるし。これは確実に効果がある分、強すぎるから。一度食べたら一週間は寝込むことになるわ。まぁ、仮に子どもができちゃったとして、今のお嬢ちゃんの身体なら、それ自体が命取りでしょうけど」
「いいよ。ちゃんと貰っておく。あんたに咎めがあったら困るだろう? え、……っと、クニャ」
「助かるわ」
クニャは微笑むと、広げた煮干しを袋に戻し、元の通りに紐を縛った。シィシアに皮袋を渡してしまうと、妓女は寝台から立ち上がって裾を払う。
「できたら今度、ここにあたしを呼んでくれないかしら。みんなお嬢ちゃんに会いたがってるのよ。特にラーヤがうるさくって。ダンも口には出さないけど気にしてる」
「ラーヤにダン?」
「その子らとあたしで、お嬢ちゃんを洗ってあげたのよ。それこそ頭のてっぺんから爪先まで。口の中だって綺麗にしてね。そりゃあ、もう大変だったのよぅ? お嬢ちゃんたら汚れの固まりみたいなもんだったんだから」
あぁ、とシィシアはようやく得心して、妓女を見返す。
「なら、いつだって勝手に来るといいよ。わたしはよく分からないけど、何か言われたら言われたで、その時考えるから」
よろしく言っておいて、とシィシアは最後に付け加えた。
*
西の魔女は、暗がりにそっと降り立った。
己の一挙一動が隅々まで感覚に障る風のない夜。静寂が満たす闇は、上下が定かでない水を掻くのによく似ていた。無数の星明かりに照らされたか細い月光は、木窓の閉じられた部屋の中には届かない。
ぽぅ、と右手に光球を生み出した魔女は、寝台に仰臥している女の額にあけていた左手を添わせた。
「起きなさい。それとも、もう起きていた?」
あてがわれた掌から額へじわりと熱が沁みだす。指摘通り空寝をしていたシィシアは、日溜まりに侵食されるような感覚に、観念して身を起こした。顔にかかった雑多な黒髪を掻きあげる。
光球に照らされた初老の女の顔は穏やかでありながら、光と同量、影を色濃く含ませていた。飾り布を編み込んだ淡茶の髪は、右肩に寄せられて前へ流れる。白濁した双眸は、彼女の目が見えていないことをシィシアに悟らせた。
にもかかわらず、伸びてきた女の手は、寸分も狂うことなくシィシアの両頬を挟み込む。
自然、顎を上向けられたシィシアは、意に添わず首の反る体勢にきつく眉根を寄せた。
「魔女?」
「当たり。私は今代の西の魔女。もしも自由になりたいのなら、シィシア、あなたをここから連れ出してあげる」
「いらない」
シィシアはすげなく答えた。意外そうに白濁の双眸を見開いた西の魔女に、シィシアは嘲弄めいた笑みを広げる。
「わたしは、わたしがひとりで生きて行けるなんて到底思えない。それなら誰かに庇護してもらわないと。だってわたしはひとところに留まっておく方法しか知らないし、今更知ろうとも思えない。それとも、あなたがそれをくれる?」
「……南の魔女のところへ連れて行ってあげることはできるわ。あなたにはそれだけの素養がある」
「それって結局は同じことだろう? なら、まだここの方が近いよ。わたしは、王に感謝を返す必要がある」
「そう」
深閑とした部屋に受諾を落とした魔女は、笑う娘の顔から両手を離す。傍で浮いていた光球を手元に戻して、魔女は光球の中から零れ出た耳飾りをシィシアに差し出した。
怪訝気な娘に薄い藍石が表面に貼られた耳飾りを示して、魔女は言う。
「ならば、これだけ。あなたには見えるはずのないものが視えているはず。『森』が揺れているせいか、なぜか南が強く出ているけれど」
「言っている意味がよく分からない」
「あなたがまだしばらくここに留まると言うのなら知らない方がいいの。あの男に利用されたくなければ、黙ってこれをつけておきなさい」
シィシアは、魔女と掌上の耳飾りを見比べる。
果たして取っておくべきか否か。口にせずともあぐねているのが一目瞭然の娘に、魔女は迷子になった時分に幼い息子が見せる表情を重ねて苦笑した。
「いいわ。明日、あなたの好きになさい」
選択の余地を娘に与えて、魔女はあとかたもなく姿を消す。同時にかき消えた明かりの端で、耳飾りがカツンと落ちた。
形のない暗闇の中。目映い光から一転して闇に放り出された目は何も捉えない。目が慣れるまで、とシィシアはじっと夜の底を見続けていたが、夜陰に紛れる藍色の石を見つけられるはずもなかった。
感知できない時間の終わり。木窓の隙間から挿し込み始めた朝日に、夜通し眠ることのできなかったシィシアは痛む目を堪えた。敷布につけっぱなしだった腕が痺れる。寝台からおろした素足の裏を石床が指先から冷やした。
窓に寄り添い、木窓を押し開ける。澄んだ早朝の空気が詰まりかけていた肺をこともなげに満たした。窓枠に囲まれた空はまだ淡く白い。階上から見えていたはずの都の残骸に代わり、荒れた地表に点在する草の茂みがぐんと近まってみえた。風雨にさらされてきたからか黄味を帯びた天幕の合間からは、熾火の細い煙が幾筋も立ち上がる。
やがて随分と低くなった景色から目を離したシィシアは、思考の回らぬ頭を巡らせて、自分の置かれた位置を鑑みた。石床に転がる藍石の耳飾りが、伸び始めた朝日を受けて存在を主張する。
強大な力故に畏怖の対象とされてきた魔女と賢者は、だがその一方で困窮した者たちが最後に助けを求める存在でもある。それ故、普通に考えるなら西の魔女の言葉は信用に値するのだろう。少なくともこの砦を押さえた男よりは、ずっと。
石床に膝をつけたシィシアは、足元にあった耳飾りを用心深く拾い上げた。小さな耳飾りは命運を委ねるにはあまりにも心許ない。
強く両手に握り込んだ藍石を、シィシアは額に押し当てた。
「母様」
懇願に似た嘆きに耳を貸す者はない。口にした彼女でさえも、対する相手が今生きているのかは知らなかった。だが、かつて躊躇なく彼女をここに残した母の為に、母の意に沿う術が知りたかった。
叩かれた木扉に、シィシアは硬く下ろしていた睫毛を震わせる。
水盆を持って現れたクニャは、石床に座り込んでいるシィシアを見て、驚いた顔をした。
「どうしたの?」
クニャは水盆を床に置くと、シィシアの前に跪く。途方に暮れている女の顔を、クニャは小麦色の手で拭った。
「食べたの?」と聞くクニャに、シィシアは拳を握りしめたまま力なく首を振る。
なら、と妓女は明るい声で呼びかけた。
「水で顔を洗いなさいな。そうすればきっとすっきりするわ。気分も少しはよくなるわ。聞いて。あたしたち、しばらくお嬢ちゃんの世話をできることになったの。後から、ラーヤも来るわ。他の子たちも。笛に弦を聞かせてあげる。あなたの歌を歌ってあげる。覚悟しておいて、お嬢ちゃん。あたしたちはみんな、人を愉快にさせることにかけては、一番の誇りを持っているんだから」
朝食を急かしてくるわ、とクニャは手をついて立ち上がる。顔を上げたシィシアに気付いたクニャは、部屋を出る間際、振り返って片目をつむった。
遠のいていく足音を聞きながら、シィシアは再び変わり果てた日常を思う。水盆に貼られた水は清潔で、手を差し入れると指先がじんと痛んだ。輪を広げる波紋は、淵に遮られて消えてゆく。
銀の水盆には、茫洋とした緑眼の女が映った。久しく見ていなかった顔が水面で笑ったのを見て、彼女は「ちょっと眠かっただけよ」と語りかける。
シィシアは包みこんでいた手を広げた。水にさらした掌の上で、藍石の耳飾りが手中に沈む。
「いいわ。あなたの手を借りる。望むのならば、喜んで利用されてあげる」
シィシアは、水ごと耳飾りを掬う。腕を滴る水に構うことなく、彼女は耳飾りだけを摘みあげた。
眼前に掲げた耳飾りを見据え、シィシアは藍色の薄石へ笑いかける。
「ねぇ。わたしたちの王を殺してくれたお優しい王様?」
そうして隠し姫と呼ばれた女は、左耳の上側に耳飾りの針を突き刺すと、歌の通りの黒髪で藍色の石を密かに隠したのだ。
Copyright (C) 2010 あるひの森の中 All Rights Reserved.