four o'clock 3:庭園で

「わぁ! すごく綺麗!!」
アイカがやって来て一週間がたった。すっかり王宮にも慣れ始めた彼女を誘って中庭にある庭園へと降りる。
宮殿の東棟と西棟、そしてその棟を結ぶ渡り廊下によって切り取られた空間にある中庭には初夏の花々がまさに今が盛りと咲き誇っていた。
貴族たちが好んで足を運ぶこの中庭。途中途中にテラスが置かれているこの場所では、よくお茶会も開かれる。植物で生い茂っていることもあり、密談にも使われる場所だ。皆が集まるからこそ、噂や情報が飛び交う場所でもある。もちろん、隣で歩きながらはしゃいでいるアイカがそんなことを知るはずもない。
それぞれの思惑を持って訪れられることの多いこの場所を今日は何の企てもなく、ただ楽しむためだけにアイカと共に区画ごとに分けられている花園を順々に回っていった。
その中でも芳しい芳香を放つバラ園でアイカは足を止めた。
「こんなにたくさんのバラ初めて見た。いい香り!」
「バラはアイカの世界でも"バラ"というの?」
「うん、そう。バラにも漢字があるんだよ。難しくて私は覚えてないから書けないけど。でも、そういえば不思議だね。文字は全然違うのに言葉は通じるし、物の名前も全部一緒だもんね」
「そう言われてみると、そうね……」
「ドラ〇もんのホンヤクコンニャクみたいなものかなぁ?」
「ドラ〇もん? ホンヤクコンニャク?」
「あ、えっとね、テレビに出てくる青色のネコ型ロボットが持ってる道具でね、それを食べると言葉が通じない人とも会話できるようになるの!」
「テレビ? ロボット?」
アイカの口から次々と飛び出る謎の言葉に首を傾げる。初めて会った日もそうだったが、彼女が不可解な言葉を口にすることは少なくない。一体彼女は何の話をしているのか。
「え~と、だから、簡単に言うとお互いが話す別の言葉を自動翻訳してくれてるんじゃないかって思ったの。どういう仕組みかは分からないけどさ。でも、この国に無い言葉はやっぱり通じないみたいだね。まぁ、考えてみると当り前か」
うんうんと一人納得したようにアイカが頷く。
その後ろで咲く濃いオレンジ色のバラ。彼女の黒い髪には周りのバラの色がよく映える。
だけど――――
「やっぱり、アイカにはピンクのバラが一番ね」
手折った赤みがかったピンクのバラの花をアイカの編み込まれた黒髪へと挿し込んだ。その途端に、バラの鮮やかさが増す。
「うわ、もったいない! せっかく綺麗な薔薇なのに、私の髪に飾るよりも、花瓶に飾った方が絶対いいのに!! というか、リシェル私の話聞いてなかったでしょう?」
「もちろん聞いていたわよ。でも、実際に話せているのだから、答えの出ないことを考えても意味がないでしょう?」
「そうだけど……」
「ね、そうでしょう?それに、もったいなくなどないわ。アイカの黒い髪に飾るとこのバラはただ咲いているだけよりも、ずっと美しく見えるもの」
顔を真っ赤にさせてしまったアイカにぷっと吹き出してしまう。
笑い続ける私に複雑な表情を向けたアイカの髪をそっと撫でた。
「それに、フィラディアルでは花を髪に飾ることは珍しくないのよ。飾る花に意味を持たせるの。特にこの王宮内では一種の遊戯なの。例えば、ピンクのバラは、そうね、いろいろあるけれどアイカにぴったりなのは“温かい心”と“美しい少女”かしら?」
そんなことない、と言って再び頬を染めるアイカは本当に可愛らしいと思う。
「リシェルは?」
「え?」
「リシェルは髪に飾らないの、花? リシェルって肌、すっごく白いし、私なんかよりも絶対似合うのに!」
「つけた方がいいかしら?」
がくがく、と首を振ってアイカが頷く。
「そうねぇ……」
少しバラ園を歩きながら、白いバラが咲き誇る場所で足を止めた。その中の一本、咲きかけの白いバラを手折ると髪へと挿した。
「どうかしら?」
「可愛い!」
アイカがパチパチと拍手をする。本当に彼女は私の周りにいる人々とは全く異なった反応をするから面白い。次から次へと表情がくるくる変わる。
「そのバラにも何か意味があるの?」
「ええ。白いバラは、心からの尊敬、無邪気、純潔、私はあなたにふさわしい、といった意味があるわ。だけど、今回は意味は関係無くて、私の好きなバラなの。ほら、花の芯が淡い黄緑でしょう。完全に花が開くときには消えてしまうのだけど、この色が好きなのよ」
「本当だ。綺麗な色。すごくリシェルに似合ってる」
「有難う」
ゆっくりと花に囲まれた小道を歩く。どこかウキウキと歩いていたアイカが楽しそうに口を開いた。
「ピンクと白、ちょっと色は違うけど、こうしてると“ゆきしろとべにばら”になった気分」
「ゆきしろとべにばら?」
「そう、私の世界に伝わる御伽話なの。ゆきしろとべにばらっていう二人の姉妹がいてね、雪の日に倒れていたクマを助けて介抱してあげるの。それとか意地悪な小人のお爺さんが出てきてね。最後はクマが実は王子様でね、それから、王子様とその弟がゆきしろとべにばらとそれぞれ結婚するんだよ」
「なんだか、変わった話ね。人間だったから良かったものの、熊を家に入れるなんて危ないじゃない。初めて聞いたわ」
「言われてみると、確かにそうだけど……。ねえ、リシェルも何か教えてよ。こっちの御伽話ってすっごく気になる」
期待に溢れた眼差しに私はしばし考え込み、とりあえず一番有名な話をすることにした。
「塔に閉じ込められた美しい姫と竜の話はどうかしら?」
「あ、知ってる! 塔に王子様が助けに来るんでしょう?」
アイカが告げた話の内容に思わず首を傾げる。どうしたら、そういう展開になるのだろう?
「いいえ、閉じ込められた姫は竜に乗って、世界を見て回るのよ。それは楽しい旅なの。だけど、閉じ込めたはずの姫がいなくなってるのに気が付いた王が激怒するの。この王は悪い宰相に騙されていてね、姫を閉じ込めておかないと災いが降り注ぐって思いこんでたのよ。竜が味方に付いてくれているとしても、国の軍全体を相手にするのは無理だと悟った姫はね、隣国へ行って支援を要請するの。隣国の王は支援する代わりに姫が一の王子に嫁いでくることを条件に出して、姫は渋々承諾。なんとか、悪政を敷いていた宰相を倒して、王を改心させ、元通りの平和な国を取り戻したのよ。それから、約束通り隣国へ嫁いで両国の友好条約の懸け橋になったとか」
話し終えた後、隣を歩くアイカを見たら変な顔をしていた。一体どうしたのだろう?
「……それって、御伽話っていうの?」
「ええ。あまり気に入らなかった? そうね、他には継母と義姉達に苛められていた娘が名づけの親の妖精の力を借りて、ガラスの靴を履き、舞踏会へ行く話かしら?」
「それってシンデレラ? 灰かぶり姫のこと?」
「アイカの世界にも同じ話があるの? 名前も似ているのね、私達の世界ではサンデリィラというの」
「やっぱり! 舞踏会の後ガラスの靴を落として帰ってしまったシンデレラを、王子様が一人一人娘にガラスの靴を履かせて見つけ出すって話だよね?」
嬉々として話すアイカに私は首を振った。
「いいえ。サンデリィラは舞踏会に行ったのは良かったのだけど、踊れなかったのよ。だって、ガラスの靴なんて、ただ痛いだけでしょう?」
「…………」
「それでも踊ろうとはしたのだけどね、やっぱり足が痛くて結局隅で座っていたの。中は煌びやかな世界。だけどサンデリィラはそこから離れてただ一人、夜のバルコニーから中の様子を見ていたの。当然、主役の王子と踊れるわけもなく、ただ憧れの王子の姿を目で追っていたのよ」
「え? でも、ちゃんと王子様と結ばれたんでしょう?」
「そうよ。一人ポツンと座っていたサンデリィラに気付いた王子は踊ろうとしない彼女を不思議に思って、バルコニーへとやって来たの。ただし、それは主役の第一王子の方ではなくて、その弟の第二王子だったのよ。王子はサンデリィラの足を見た途端顔を顰めてこう言ったの。『なぜ此処にいらっしゃるのかと思ったら、そんな靴では痛くて踊れませんね。』サンデリィラの足は固いガラスの靴のせいで肉刺(まめ)ができていたのよ。そして、王子はサンデリィラの為に柔らかな革の靴を作らせた。サンデリィラはお礼を言って微笑んだ。それから、王子は新しい靴を手に入れたサンデリィラを誘って、二人で踊ったの。サンデリィラは王子の優しさに、王子の方は笑顔の愛らしいサンデリィラにそれぞれ胸を打たれ、みごと結ばれたっていうお話」
「へえ~、私の世界のとは違ってて途中色々びっくりしたけど、面白かった。似たような始まり方でも、全く違う話になっちゃうんだね」
そう言いながらアイカが微笑んだ。どうやら、サンデリィラの話は気に入ってくれたようだ。良かった。
バラ園を抜けたところ、夏の様々な花が植えられた棟と棟をつなぐ渡り廊下に面する場所に差し掛かった時、アイカは「あっ」と小さく声を上げて走り出した。
アイカの行きついた先、そこにはこんもりとした緑の草が茂っている。緑と緑の間から覗く小さな濃いピンクの花。けれども、その少なさが、花の盛りが過ぎてしまっていることを告げていた。この花の一体何がアイカの興味を引いたのだろう?
そう思った矢先、アイカが振り向き、「へへっ」と笑った。
その顔を見て唖然とする。
「アイカ、その顔、どうしたの?」
アイカの肌にはたくさんの白い粉が付いていた。肌よりも白いその粉で、顔がものすごく奇妙に見える。
それなのに、アイカが白い粉を付けたまま笑うから、とうとう私は噴き出してしまった。それと同時にアイカも噴き出す。可笑しくて涙が出てきそう。
「アイカ、すごく変な顔よ?」
「うん、そう思う。でも、なんだか、すっごく懐かしくって、童心に帰ってみました。リシェルはやったことないの?白粉花(おしろいばな)の種を潰して顔に白粉(おしろい)を付ける遊び」
「ないわ。そんなことができるなんて、初めて知った」
そう言うと、アイカは意地悪そうに、にやりと笑った。
「リシェルにもしてあげよっかぁ~~~~?」
白い粉のついた指を伸ばしてくる。
「わ、ちょっと、アイカ―――!」
「あはは、待て待てーーー!!」
追いかけてくるアイカから逃げるため、夢中で走りだす。
笑いながら追いかけてくるアイカは、幼少時に私を追い駆け回してきた、とある貴族の少年を思い出させ、はっきり言って、少し、いえ、とても怖かったので、私はいつの間にか必死で逃げていた。
「―――!」
「―――リシェル!」
躓いてしまい、体が傾ぐ。
走りにくい長いドレスで必死に駆け回っていたせいか、足にドレスが絡まってしまったのだ。
しかし、次いで、与えられるであろう強い衝撃は、思ったよりもかなり軽いものだった。
自分を支える人物。手が触れた厚い胸に驚き、顔を上げる。
「―――陛下!」
目の前の人物が苦笑する。見慣れた青の瞳が私を見下ろしていた。
「大丈夫か?」
陛下が私を支え直して、きちんと立たせてくれた。
「は、はい、有難うございました。」
慌てて、陛下から離れる。赤くなり出した顔は抑えることもできない。
恥ずかしい…………
何とか赤みのある顔を隠そうと奮闘していた私の背後から、アイカが走って来た。
「ごめん、リシェル。ふざけ過ぎた! 大丈夫?」
「え、ええ、大丈夫よ。私こそごめんなさいね。つい本気で逃げてしまって……」
「本当にごめんね」
申し訳なさそうな顔をするアイカとは対照的な、カラカラとした笑い声が上から降って来た。
お腹を抱えて笑い出した陛下に、少なからず驚いた私はその様子を茫然と見守っていた。
こんな風に殿下が全身で笑うのは子供の時以来だ。
未だに笑い続ける陛下のことをアイカがジトッとした目で睨む。細められた黒い瞳はなかなか迫力があった。
「―――王様! いくらなんでも笑いすぎ!!」
「いや、悪い」と言いながら、陛下は笑いを抑え込んだ。けれども、やはり、口の端が笑っている。
「だが、アイカ、その顔は酷いぞ?」
その言葉に私も再び噴き出してしまった。
「―――もう、リシェルまで!!」
怒っているけど、アイカも顔が笑ってる。
結局皆の笑いを引っ込ませたのは、その場にいたもう一人の男の声だった。
「ほう、思ったよりも愛らしいじゃないか。」
長く肩まで伸びた赤毛の髪を一つに結んだ、橙の瞳を持つ男。すらりと痩せているのに、痩せ過ぎているわけではない長身の何とも羨ましい体形をしたこの男。恐らく初めて見るこの男にアイカは戸惑いを隠せないでいた。
「えっと……?」
「おや、失礼。私はランスリーフェン・アッカルディ・エル・ヒルデルト。爵位は侯爵。アトラウス陛下の片腕として宰相をさせていただいております。以後お見知り置きを」
そう言って、ランスリーフェン侯爵はアイカの手を取って、甲に口付けた。
「おや、おや。」
みるみる顔が赤くなり、アイカが慌てて手を抜き取ろうとする。だが、ランスリーフェン侯爵によってがっちりと掴まれた手は抜けず、アイカはますます動揺しだした。
その様子をランスリーフェン侯爵は面白そうに眺めている。本当に性格の悪い男だ。
「ラスリー……」
「ランスリーフェン侯爵、アイカをからかうのはやめて下さい」
陛下と私に睨まれているにもかかわらず、クスクスと笑いながらランスリーフェン侯爵はようやくアイカから手を離した。
「いや、可愛らしくてつい、ね。でも、そんな反応が返ってくるとはね」
「ランスリーフェン侯爵!」
「おや、嫉妬かい?」
「誰が貴方なんかに嫉妬しますか」
「はは、相変わらず言うねぇ。ご機嫌麗しゅう、エリィシエル姫」
ランスリーフェン侯爵はアイカの時と同じように私の手の甲に口付けた。所作だけは見事に決まっていて、優雅だ。顔を上げ、世の令嬢達を腰砕けにさせてきた笑みで微笑む。
けれど、彼の本性を知っている私には全くもって無意味である。当然ながら平然と型通り挨拶を返した。
「ええ、御機嫌よう」
「やはり貴女には淡い緑がよく合いますね。そのバラに負けず劣らず、相変わらず綺麗です」
「それは、どうも有難う」
ランスリーフェン侯爵に、にっこりと笑ってみせると、彼は軽く溜息をついた。何ともわざとらしい。
「貴女は面白くないですねぇ。アイカはあんなに真っ赤になって可愛かったのに」
そう言うと、ランスリーフェン侯爵はアイカへと向きなおった。
またもや、動揺していたアイカだったが、ランスリーフェン侯爵が話し出すと、すぐに顔をほころばせ、クスクスと笑いだした。
本当に彼の話術にだけは感服である。これこそが、人々を丸めこみ、異論を許さない彼が宰相としての地位を確立している所以でもあった。
まさか、アイカに危害を与えるようなことはないだろうと、その様子を眺めていると、横から小さな笑い声が漏れた。
「アイカは元気そうだな。よく笑っている」
「ええ、アイカはいつも笑顔を絶やしませんわ」
微笑んだ私に、陛下は「いや」と、かぶりを振ると、前方を見据えた。その視線の先にあるのは、ピンクのバラを黒髪に挿したアイカ。
「昨日は、泣いていた」
「え?」
そんなこと普段の彼女からは想像できず、思わず聞き返してしまった。
「夜、一人で泣いていたんだ。普段は明るいが、やはり、心細いのだろう」
「そう、だったのですか」
「ああ」
アイカを見ている陛下の目がふと細められる。柔らかな表情。
胸が知らずザワリと音をたてる。
「よく……見ていらっしゃるのですね」
「ん? 何か言ったか?」
「……いえ、何も。何でもありません」
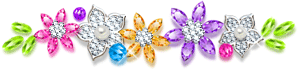

(c)aruhi 2008