four o'clock 4:噂話

「お聞きになりました? あの噂」
「ええ、なんでも陛下が突然やって来た、あの黒髪の少女にご執心だとか」
「そうそう、陛下は他の者には目もくれず、毎日のように黒髪の少女と一緒にお過ごしになっていらっしゃると耳にしましたわ」
「一体あの少女は何者なのかしら。アリュフュラス家の姫を差し置いて、でしょう?」
「彼の姫はさぞかし心穏やかではないでしょうね。何しろ、王妃として迎え入れるに相応しい家柄の姫の中でもっとも有力だったのがアリュフュラス家でしたものね」
「その立場が危ういとなると……、彼の姫には気の毒ですが、少しいい気味ですわね。こんなこと大きな声では言えませんけど」
「でも、本当に、その通りですわ。お家をかさに着て気取っていらしたものね。きっと、陛下もそれが気に食わなかったのではないかしら? アリュフュラス家の強大すぎる権力を恐れてのことかもしれませんわね」
「けれども私はあの少女のことも気に入りませんわ。ぽっと出のくせに陛下に取り入るなんて」
「あら、そうかしら? 私はあの子の方がよくってよ。黒真珠のように綺麗な髪でしたわ。それに、まだ子供ですもの。陛下が本気のはずもありませんし」
「まぁ、それもそうですわね」
「でも、もし、もしですわよ? その少女が陛下の心を射止めたら面白いと思いません? 彼の姫は一体どんな顔をするのかしら」
「見物ですわね」
羽のついた豪奢な扇を口元に当て、貴婦人達が高らかに笑った。
近頃、王宮の至る所で耳にする会話。
黒髪の少女、アイカとアリュフュラス家の姫、エリィシエルについての噂。
平和な、つまり、貴族たちにとっては至極退屈な宮廷において噂話は格好の享楽の一つであった。
ひとたび、煙が上がれば、ここぞとばかりに燃え盛る。それが、自分に関係のない他人の不幸事なら尚更、思う存分、心おきなく楽しめるというものである。
「エリィシエル様……」
ユージアが眉を顰め、口を開いた。
彼女は結いあげの為に用意した櫛とサファイアをあしらえた銀の髪飾りをそっとテーブルの上に置くと、窓の外を眺めていた私の後ろへと寄り添った。
窓の外、花に溢れた庭園の中では、今日も貴婦人達は実際の花には目もくれず、噂話に花を咲かせていた。
私はただ溜息をつく。
本人達は恐らく隠れて噂話に小さな花を咲かせているつもりなのだろうが、長年この場所で生きてきた私にとっては目の前で話されているようなものだった。
アイカは、まだ噂のことを知らないだろう。できれば知って欲しくない、とも思う。
けれど、私に関しては情報網の範囲が違いすぎるのだ。この王宮内で起こったことは全て、遅くとも次の日のうちには耳に入る。それは、この宮廷において高位の貴族であればある程、当たり前のこと。
「噂のことでしょう? 心配には及びません。確かに陛下はアイカと仲が良いですが、私だって同じくらいアイカと仲が良いし、一緒にいるわ。それに、殿下とアイカの二人だけではなく私が入って三人でいることの方が多いのが事実よ。あのような噂、気にしてはいないわ」
「しかし、皆が言っているのも一理あります。アイカ様は少しずうずうしすぎではありませんか? いくらエリィシエル様と陛下がお優しいからといっても、エリィシエル様は王妃になられるに相応しいアリュフュラス家の姫君です。その為に、幼い頃から父君、母君の元を離れ、この広い王宮でたった一人、貴女様が必死に暮らしてきたのを、努力されてきたのを、このユージアは傍で見てまいりました。それなのにアイカ様は―――」
「―――ユージア」
私は彼女の言葉を遮った。私のことを思ってくれているのはとても良く分かる。だけど、心優しい彼女の口から、アイカを否定するような言葉は聞きたくなかった。
「ですが―――」
眉尻を下げ、今にも泣きだしそうな顔をするユージアに私はゆっくりとかぶりを振った。
その時、部屋のドアを叩く音が静まり返った部屋に響いた。
会話に終止符を打てることに安堵し、侍女に任せることなく、自身で足早に扉へと向かう。
扉を開けると、そこに立っていたのは長身の赤毛の男、ランスリーフェン侯爵、その人であった。
「御一人、ですか? 陛下は……」
宰相である彼がたった一人でこの部屋を訪れることなど滅多にない。いつも傍らにいるはずの、彼が仕えるべき主君が見当たらない。
「陛下はアイカと市井へ降りています。アイカに街を見せてあげたいようです。いかにもアイカが喜びそうですからね」
「……そう、ですか」
「貴女には声が掛からなかったのですね」
「…………」
ランスリーフェン侯爵はいつもの笑みを絶やさぬまま、けれど、その目元だけは何かを試すかのように細められた。
ざわり、と、この間感じたものと同じ胸騒ぎを覚える。
けれど、それを顔に出すことはできない。感情をむやみに人に見せないこと。それは、アリュフュラス家の姫として唯一親から教えられたことだった。
「いけない。まだお茶もお出ししていませんでしたね。どうぞ中へ。ユージアお茶の用意を」
人当たりの良い笑みを作ると、私はランスリーフェン侯爵を部屋の中へと促した。
茶を啜り、一息ついたランスリーフェン侯爵は両手をテーブルの上で組み合わせると口を切った。
「それで? 貴女はアイカと居て辛くはないのですか?」
あまりにも唐突な物言い。彼の耳にもやはり噂は届いていたらしい。
受け皿に置くとティーカップがカチャリ、と音をたてた。
「アイカはとても、いい子です。私にとってかけがえのない友人です」
「それは本心からの言葉ですか? エリィシエル姫」
まるで何かを見透かしそうな橙の目。いつも浮かべられている微笑みはそこにはなかった。
代わりに私が彼へと笑みを向けた。
「質問の意図が分かりかねます」
ランスリーフェン侯爵がフッと微笑し、椅子の背へともたれた。
「まぁ、良いでしょう。嫌ならまだ触れないでおきましょう」
「…………」
「ただ、あまり心配をさせないで下さい」
それは、少々聞き捨てならない。
「いつ私が貴方に心配をおかけしましたか?」
「いつもさせているでしょう。広い宮殿の中で迷子になって泣いていた小さな女の子を見つけてあげたのは私ですよ?」
「―――ラスリー!!」
まだ、そんなこと覚えていたなんて。あれは私にとって一生の不覚だ。
敵意をこめて睨みつけているのにラスリーは怒る私を見ておかしそうにクスクスと笑い出した。
「おやおや、貴女にその愛称で呼ばれるのは久しぶりですね。いつも、そうやって呼んでくれればいいのに。リシェル」
「やめて下さい。貴方にそう呼ばれると嫌なことまで思い出してしまいます」
「酷いですね」
ふっと微苦笑するラスリーを睨みつける。
「過去の行いの反省をすることですね」
毎日のように蛇や虫を持って追いかけてきた少年。嫌だと言って泣き叫んでも、何度も笑いながらやってくる彼は幼い私にとっては悪夢だった。必死に逃げる私をいつも庇ってくれたのはアトラス―――陛下だったのだ。
「―――さて、そろそろ私は行きますかね」
ティーカップを受け皿に戻し、立ち上がったラスリーを見上げる。
「一体貴方は何をしに来たのですか……」
「休憩ですよ。紅茶を飲みに」
「なら、御自分の従者に頼めばいいじゃないですか。」
「ユージア殿の紅茶の方が美味しいからね。というか、酷い言い草ですね。わざわざ激務の間を縫って来たのに」
不服そうな顔を向けるラスリーに嫌味をこめて恭しく頭を下げてみせる。
「ユージアのお茶を褒めて頂き光栄ですわ。しかしながら、忙しいのならわざわざ立ち寄っていただかなくても結構ですよ? 御申し付け頂ければ、こちらから届けさせます、ランスリーフェン宰相殿」
「そうか? じゃあ、お願いしようかな」
嫌味を全く意に介さずラスリーは笑って答えた。いや、むしろ嫌味自体がこの男には通じてないのかもしれない。
それにしても、こんな男が宰相なんて、この国は大丈夫なのかしら? こんなのに王に次ぐ権力を与えてしまうなんて危険すぎる。陛下のことは本当に尊敬しているけれど、ラスリーを宰相に選んだことだけは全く理解できない。もしかして、陛下は何かこの男に弱みでも握られて脅されているのではないだろうか?
「ぷっ、考えていることが駄々漏れですよ?」
笑い続けるラスリーを思いっきり睨みつけてやったら、何故か頭を撫でられた。
「まぁ、そうしている方がリシェルらしい。最近ちょっと、すましすぎだ。無理しすぎ」
「馬鹿にしているのですか? 本当に何なんですか貴方は! もう、いいから出てって下さいよ。仕事がたくさんたまっているのでしょう? 貴方ほどではありませんが私にも仕事はあるんですから、長々と居座られると困ります。迷惑です」
「わかった、わかった、ちゃんと帰るって」
ヒラヒラと手を振りながら出口へと向かったラスリーは、しかし、扉の前で立ち止まると、再びこちらを振り返った。
「そういえば、今日は珍しく髪を降ろしてるんだな」
「貴方が来るのが早すぎるんですよ。纏めようと思っていた頃に貴方が来たから間に合わなかったのです。今から編み上げますよ」
「―――いや、そのままの方がいい。似合ってる」
「ユージア、髪結いの用意を」
「その反応は無いだろう、リシェル」
「その愛称で呼ばないで下さい。貴方が言うと嫌味にしか聞こえません」
「アトラスにも見せてやるといい。きっと褒められるぞ?」
それだけ言ってしまうと、ラスリーは今度こそ扉の向こうへと去って行った。
「わぁ! リシェル、可愛い! 髪、降ろしてるとこ初めて見た。ね、王様もそう思うよね?」
「あぁ、そうだな。リシェルは幼い頃から髪質も色も綺麗だったからな。確かに降ろしていた方が似合っている」
街から帰って来たアイカの第一声は褒め言葉だった。それに同意するように発された陛下の言葉。
お世辞かもしれない。でも、嬉しくて知らず知らずのうちに笑みがこぼれてしまう。
「本当ですか? 有難うございます」
陛下の言葉に完全に舞いあがっていた私が二人の後ろで、クスクスと笑っていたこの国の性悪宰相に気付いたのは、それからだいぶ経ってしまった後だった。
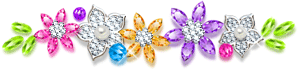

(c)aruhi 2008