four o'clock 5:崩壊

彼女を見る青い目がまるで慈しむものを見るような優しい目になったのは、いつからだっただろう?
どこか熱を帯びた彼の目に彼女が答えるようになったのは、いつからだっただろう?
私はきっと、二人が気付くよりもずっと前から気付いていた。
なぜなら、ずっと近くで見ていたから。
きっと誰よりも早く、大好きな青い目が自分に向けられることはないのだ、と悟っていた。
だけど私は蓋をする。
自分を誤魔化す為に。
陛下とアイカの隣で、私は何も気付いていないのだ、と笑う為に。
もしかしたら、そうではないのかもしれない、ただの杞憂なのかもしれない、と微かな希望にすがる。
そうであって欲しい、と心から願った。
「今日はいいものを持って来ましたよ」
扉に立った人物を見て、げんなりとする。
「また、貴方ですか。ランスリーフェン侯爵」
彼はにっこりと笑うと私の手を取り、甲へと口付けた。
「ご機嫌麗しゅう、エリィシエル姫」
優雅な仕草も、毎日見れば何とやら、である。
陛下とアイカが街へ出かけたという、あの日から彼はなぜか毎日のように私の部屋に訪れるようになった。しかも、これといって用があるわけでもなく、休憩、と言っては、ただお茶を飲みに来る。
付き合わされるこっちの身にもなって欲しい。
「全く麗しくないので、お引き取り下さい」
「あぁ、今日のドレスは淡い緑ですか。似合いますね。充分麗しいですよ?」
「よっぽど暇なんですね。とうとう首にされましたか?」
「陛下が私を手放せると思いますか? 信頼されていますからね。仕事を山のように押し付けられて困っています」
「それなら、直ちにお帰り下さい」
「まぁまぁ、いいじゃないですか。ああ、ユージア殿、これをお茶受けにお使い下さい」
ユージアは、「かしこまりました」と言って、ランスリーフェン侯爵から薄い紅色の紙に包まれた小さな箱を受け取ると、クスクスと笑いながらお茶の用意をしに隣の部屋へと消えた。
「座らないのか? リシェル」
ずかずかと我が物顔で入り込み、いつものように窓辺の定位置へと腰を下ろしたランスリーフェン伯爵に、何を言っても無駄だと、肩を落とし、やはり、私もいつものように彼の向かいへと腰を下ろした。
「ラスリー……、迷惑です」
遠まわしに言ってはだめだ、と直球で言ってみたが、やはりこちらも効果はなかったようだ。
「あぁ、あのことか」と、笑いながら、ラスリーは片手を挙げて「有難う」と呟くとユージアからお茶を受け取った。
私の前にもお茶が置かれる。白地に濃い青で花の装飾が描かれたティーカップの中では茶が黄金に輝いていた。
「今日はカレアルの花茶にしてみました。ランスリーフェン様が持ってこられたフーアグによく合うと思いましたので」
「フーアグ?」
聞きなれない名に、そう聞き返すと、「はい」と言いながら、ユージアが陶器の皿を目の前に置いた。その上には白くて丸いころころとした菓子がいくつも乗っている。
「これ……」
「昔好きだったでしょう? 庶民の菓子ですが、リシェルは気に入って、よく私が持っていたのを貰いに来てた」
彼の言う通り、ふらふらと貰いに行った私に、赤髪の少年がポケットから蛙を出したことは覚えてないのだろうか。
ラスリーが皿から菓子を一つ摘み、口の中へと放り込んだ。私も一つ食べる。砂糖でできた甘い菓子は口の中に入るとふわりと溶けて消えた。
「もう、昔のことです」
「美味しくなかったか?」
「そういう意味ではないのですが、私には懐かしすぎます」
もう、ここには、何も知らずに駆け回っていた女の子はいないのだ。
けれど、ラスリーはもう一つ菓子を含みながら笑って言った。
「懐かしいからいいのに。周りの皆は変わっていくが、思い出だけは変わらないだろう? まぁ、今はそれよりも、先に謝っとこうと思って来たんだ」
「それは、あの噂と関係があるのですか?」
私が尋ねると、ラスリーは「そう」と言って頷いた。
新たに流れ出した噂。
ラスリーがこの部屋に顔を出し始めてから流れ出した噂。
陛下に愛想をつかされたアリュフュラス家の姫、つまり私が、あろうことか目の前の男、宰相であるランスリーフェン侯爵に手を出しはじめたというもの。
しかも、それに拍車をかけるかのように、ラスリーが私の部屋へ訪れるのだから本当にいい迷惑である。
「はい、はい、そんな嫌そうな顔しない。ちゃんと否定しておいたから」
「本当ですか?」
前のめりになった私に、優雅に花茶を飲んでいたラスリーは頷いた。
たまには、よいことをする、と目の前の男への評価を改めかけた時、再びラスリーが口を開いた。
「ちゃんと、リシェルではなく、私の方がリシェルを落とそうと通いつめてるって明言してきたので、今はその噂で持ちきりだと思いますよ?」
楽しそうに笑う彼にめまいを覚え、私は頭を抱えて、背もたれへと体を預けた。
「……全く変わっていないではありませんか」
「全然違うじゃないか。それにこちらは真実だ」
クスクス笑いながら私の手を取ったラスリーを、私は呆れを持って見返す。
「嫌な冗談はやめて下さい」
「冗談なんかじゃないんだけど」
急に握られている手に力を込められ、思わず、びくり、としてしまった。
驚きに目を見開くと、そこにはいつものからかいを含んだものではなく、真摯にこちらを見つめる橙の瞳があった。
「そろそろ、俺のことを見て欲しいんだが」
そう言って、彼は私の甲へと口付けた。
儀礼的ではなく、酷く熱のこもったその柔らかさが、いましがた述べられた言葉が嘘ではないことを告げていた。
「本気、ですか……?」
驚きを隠せず、聞き返す声がかすれてしまった。
そんな私の頬にラスリーは手を触れさせ深く頷く。
私が何か口にしなければ、断らなければ、と戸惑っていると、ラスリーはふっ、と笑い、彼の手が頬から離れた。
「口にしなくていいです。貴女の立場は分かっていますし、それでなくとも、まだ私に分がありませんからね」
「…………」
いつもと同じ彼に戻ったことに安堵しつつも、一体何を話せばいいのかわからず、俯いていると目の前の机に一つの長い箱が置かれた。焦げ茶の木の箱には細かく美しい模様がいくつも彫られて、それ自体が芸術品と言ってもいいような代物だった。
突然出されたその箱に首をかしげつつ、目の前の男へと説明を求めると、箱を開けるように促された。
中に入っていたのは橙色のトパーズのついた首飾りだった。宝石部分は加工されて四つの花弁を持つ小さな花の形にあしらわれている。
「それは黄玉のものではないので上等ではありませんが、まぁ、用途が違うので許して下さい。恋のお守りです。貴女に差し上げようと思って」
ラスリーはそう言うと私の手の中から首飾りを取り上げ、私の後ろへと回った。
「矛盾していると自分でも分かってはいるのですがね、私は貴女の笑顔が見れればそれでいいですから。貴女の願いが叶うなら、それはそれで祝福します」
最近では降ろしている私の髪をラスリーは慣れた手つきで横へ流すと、そのまま首飾りをつけた。
それから、再び私の髪を元通りに直すと、ラスリーは私の前へと回りこみ、少し残念そうに肩をすくめた。
「……やはり、リシェルの若草色の目にはあまりその色が似合いませんね。分かってはいましたが。でも、まぁ、絶対に外してはいけませんよ、それを外すと効果があるどころか、逆効果になってしまいますからね」
「それはつける前に言って下さいよ!!」
思わず声を出してしまった私に、ラスリーは面白そうに笑いながら、「だから、外さなければいいんですよ」と言ってぽんぽんと頭を叩き、「お茶、ごちそうさま」と、そのまま部屋を出て行ってしまった。
何だかどっと疲れてしまって、ぼんやりと空を眺める。
空は広く青く澄み渡っていたが、そこへ彩りを加える白い雲は風にせきたてられ足早に通り過ぎて行った。
次々と流れる、雲をどのくらい見ていただろうか?
もうそろそろ、お茶を下げさせようかと思った時、再び扉が叩かれた。
「エリィシエル様、アトラウス陛下がいらっしゃいました」
侍女の告げた来訪者の名に少なからず驚いたが、許可を出すと、当たり前なのだが、やはり陛下が現れた。
「誰か来ていたのか?」
部屋へ入って来た殿下は、テーブルの上に広がったままになっていた茶器を見てそう尋ねた。
「はい、ランスリーフェン侯爵がいらっしゃっていました」
陛下は、「ああ、だからフーアグなのか」と言うと、皿に残っていたフーアグを一つつまんで口の中へと入れた。
「懐かしいな。リシェルが好きだったよな、で、貰いに行ったら、よくラスリーに泣かされていた」
「……はい」
嫌な思い出です、と続けた私に陛下は笑い出した。
「そうだ、お茶を用意させますね。どうぞお掛けになって下さい」
私がそう言うと、陛下は椅子に腰を下ろしただけで首を振った。
「いや、すぐに出なくてはいけないから、その必要はない」
陛下の言葉に私は眉をひそめる。
「それでは、何か緊急の御用ですか?」
慌てて陛下の向かいの席に腰を下ろすと、陛下はものすごく驚いたような顔をした。
「それ、ラスリーに貰ったのか?」
「え? ……ええ」
陛下の目を止めたのが先ほど貰ったトパーズの首飾りだと気付いた私は首肯した。まさか、恋のお守りだとは言えず、曖昧に笑みを浮かべると、殿下は「とうとう動いたか」と苦笑した。
その言葉の真意がわからず首を傾げた私に、陛下は「何でもない」とかぶりを振って話を変えた。
「ここへ来たのは、別に緊急の用ではないのだが……」
言い淀んだ陛下に私は首を傾げる。
「一体どうされたのですか?」
「……いや、ただの様子見だ。最近元気がなさそうに見えたからな」
気遣いを含んだ笑みを向けられ、なんだか急に胸がぽかぽかと暖かくなるのを感じた。
「―――それだけで忙しい中わざわざいらして下さったのですか?」
「“それだけ”なんかじゃないぞ? 俺にとっては重要だ。俺にとってリシェルは大事だからな。元気がなさそうにしていると気になる。何かあったのなら、貯め込まずにちゃんと言うんだぞ?」
嬉しかった。
素直に、ただ単純に。
陛下が私のことを気にかけてくれていると知って。
優しく微笑みかけてくれる殿下が。
嬉しさと感謝とで、ぐちゃぐちゃと入り混じった殿下への気持ちはとても表わすことができなかったから、ただ一言、精一杯の気持ちを込めて微笑んだ。
「―――はい、有難うございます」
その夜、私はなんとなく寝付けず、少し散歩をしようと思いたち、静まり返った廊下へと出た。
廊下の窓から見える無数の星があまりにも綺麗だったので、自然と足が庭園へと向かう。
途中で行きかった守衛たちに「お供します」と申し出られたが、「少しだけだから」と言って全て断り、一人目指す場所へと向かった。
上着を纏ってはがいるが、夏だというのに夜は少し肌寒い。
私は自分の両腕を掻き合わせながらゆっくりと歩いた。
庭園に咲き誇る花々は月の光を受け、ぼんやりと神秘的に浮き上がっていてすごく綺麗だ。
下りようかとも思ったが、結局、庭園の中へは下りず、渡り廊下を歩いていた私は夜の庭園にはあるはずのない人影に息を呑むこととなった。
「ん……ふっ……んんっ……」
重なり合っている黒い二つの影。
それが誰であるか、すぐに分かってしまった私は渡り廊下の太い柱へと身を隠した。
「……ふわっ、苦しかった!!」
「―――くくっ、色気がないな」
「ちょっと、王様! 絶対わざとでしょう!?」
聞こえてくる声が、無情にもその考えを肯定する。
私はただ呆然として柱へと身を預けた。
「嘘つき」
ポツリとこぼし、貰ったばかりの首飾りを両手でぎゅっと握りしめた。
それと同時に自然と涙が溢れ出て、頬を伝うのを知る。
嗚咽は出てこなかった。
ただ、静かに涙が流れ、背中に感じる冷たく硬い感触を感じながら寄りかかっていた。
しかし終には、その柱さえ、私の体を支えてくれようとはせず、私はずるずると柱を滑りながら、床へと座り込んでしまったのだ。
その夜、この瞬間、今まで当たり前だと思っていた私の世界が、ガラガラと音を立てて崩れ落ちた。
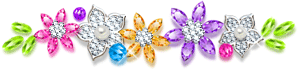

(c)aruhi 2008