four o'clock 6:相対す

「本当に貴女は自分を傷つけるのが得意ですね」
呆れたように、そう耳元で囁かれた瞬間、私の体はふわり、と浮き上がった。
「―――何を!」
抱きかかえられた私は、目の前の男へと声を上げる。
けれど、「しっ」と言う声と共に、ランスリーフェン侯爵はその人差し指を私の唇へと触れさせ、その先の言葉を遮った。
「貴女も、覗き見をしていたなどと二人には知られたくないでしょう? 部屋までお送りしますから、静かにしていて下さい」
押し黙ることしかできない私は彼に身を預けたまま、その場を離れた。
庭園が遠ざかる。
黒い二人の人影も。
できれば何も知りたくなかった、と閉じた目からは、また一つ涙が零れて消えた。
部屋の前に着いたところで、ランスリーフェン侯爵は私を下ろした。
彼の手が、頬を伝い続ける涙を拭う。何度も何度もその動作を繰り返しながら、彼は溜息を落とすように言った。
「心配をさせないで下さい、と言ったでしょう?」
その言葉に私はかっとなって、相対する男を見上げた。
「貴方は……、全てご存じだったのですね?」
彼は肩をすくめて、首肯した。
「ええ、知っていましたよ。けれど、貴女も気付いていたはずでしょう? ―――違いますか、リシェル?」
私は悔しくて、唇を噛んだ。
その通りだ。
私は、ずっと気付いていた。
だけど、それを肯定したくはなかった……
彼の言ったことが事実であると、そう認めたくなくて、私は話を逸らした。
この男が私の前に現れてからずっと疑問に思っていたこと―――
「どう、して……、貴方は、あの場所にいたのですか? 私のことを、見張っていたのですか? あの二人の邪魔をしないように?」
睨みつける私に、ランスリーフェン侯爵は溜息をついた。
「この城内部の情報はどんなに細かいことでも耳に入ります。瞬時にね。貴女も同じでしょう? それに今日言ったはずです。―――俺が好きなのはリシェルであって、あの二人のことは俺にとってはどうでもいい。ただ、リシェルが傷つくのだけは耐えられない。だからあの場所へ行った」
「―――そんなの、戯言です!」
「リシェル!!」
「―――やめてっ!!」
私は耳を塞ぐ。
持てる限りの力を持って。
聞きたくない、知りたくない、もう、これ以上は耐えられない。
「やめて下さい……、もう、やめて。お願いだから。もう、これ以上、壊さないで……」
暖かく、心地よかった世界を―――
涙が落ちる。
とめどなく溢れて、止めたいのに、止まらない。
一度決壊したそれは、濁流にのみ込まれ、完全に崩壊する。
「リシェル……」
柔らかなものが涙を掬い、耳の上で固まっていた私の手をこじ開けた。
揺れる視界の先、橙の瞳だけが、揺れてはいなかった。
橙の二つの瞳が真っ直ぐと私を見下ろす。
「リシェル、酷なことを言うようだが、俺はアイカが来てくれてよかったと感謝している」
「なん、で……?」
「俺は、こんな世界早く壊れてしまえばいいと思っていた。もう、ずっと、昔から。そればかりを願っていた。そうでないと―――――――」
そこで、私の意識は暗転する。
彼が何を言おうとしたのか、私がそれを知ったのは全てが終わった後だった。
翌日、寝台に腰かけたまま空を眺めていた私は、涙は止まるものだということを知る。
あれほど、流れた涙は、止めようとしとも止まらなかった涙は、目が覚めた時には、まるで嘘であったかのように、呆気なく止まっており、それ以上流れることは無かった。
ただ、頬に残る跡だけが、昨日の出来事が確かに現実だったということを伝えていた。
その跡をユージアが濡れた布で優しく拭いていく。
気遣わしげな瞳に何も言う気力もなく、私はそれを受け入れ、為すがままにされていた。
「エリィシエル様、昼のお食事はどうされますか?」
ゆっくりと、首を振る。
朝から食事を取っていないにもかかわらず、空腹は感じなかった。
ユージアが息を呑むのが解ったが、それでも、食べる気は起きない。
「エリィシエル様、ですが……」
ユージアが言葉を繋げようとした時、扉がたたかれる音が響いた。
礼をして、ユージアが離れ、足早に扉のある隣の部屋へと向かう。
「リシェルはいるか?」
聞きなれ、落ち着いた低い声が、部屋に響いた。
それと、同時にユージアの当惑する声も。
とうとう、この時が来てしまったのだ。
溜息を、一つ洩らしながら、私は寝台を降りて、重い足を引きずるように続く部屋へと向かった。
「殿下、申し訳ありませんが、エリィシエル様は体調を崩され臥せっておいででございます。どうぞお引き取り下さい」
「すぐ済む」
「しかしながら……」
「いいの。ユージア、陛下をお通しして。陛下、このような見苦しい格好をお許しください。少し、横になっておりました故……」
陛下は「ああ」と頷くと中へ入って来た。
その顔が、どこか苦しげで、「ああ、やっぱり」と悲しくなった。
彼は知ってしまったのだ。
私が気付いていたことを…………
「ユージア、皆の者も少し席を外してちょうだい」
心配げな表情を残しながらも全ての侍女が退出したのを見届けると、私は陛下へ席を勧める。
席に着いた陛下は、深く息を吐き出すと、ただ、「ラスリーから聞いた」とだけ、呟いた。
「そう、ですか……」
私は小さく溜息をつくと、疑問を口にした。
「なぜ、なのでしょう? 私は一体何がいけなかったのでしょう? 何が足りなかったのでしょう?」
その問いに陛下はかぶりを振った。
「リシェルが悪いということなど一つもない。何が悪いという訳ではないのだ。ただ、俺が愛したのが……、愛しているのはアイカだ、というだけだ。リシェルは大事な友人だがそれ以下でもそれ以上でもないというだけだ。そういう風には考えられない。それに、――――――リシェルが見ているのは俺ではない」
陛下が言い放った、その信じられない言葉に、私は思わず立ち上がってしまった。
「なぜ、なぜそのようなことを仰るのですか!? 私は―――、私はずっと陛下をお慕いしてきました。ずっと、ずっと、殿下に相応しくなれるように、努力してきました。この気持ちが、偽りだと仰るのですか!?」
「違う、そうじゃない。ただ、リシェルは俺のことを愛してはいない、と言っているんだ。家と自分の立場に囚われて錯覚しているだけだ」
「違う、違います! 私は――――――!!」
耐えられない。
耐えられなかった。
目の前にある憐れみを含んだ青い瞳にも。
必死に縋りつこうとする、自分の姿にも。
私の体を支配する醜く汚い感情にも。
耐えられない。
あり得ない醜態だ。
惨めで、滑稽だ。
「っふ―――」
嗚咽が漏れる、けれど、涙は流れない。
私は耐え切れなくなって、自分の部屋を飛び出した。
背後で、私の名を呼ぶ声が聞こえる、「リシェル」と。
何よりも……、何よりも大好きだったこの言葉は、この日、この瞬間、消えた。
部屋を出た私は王宮内を歩き回った。
どこへ行くわけでもない。
ただ、フラフラとさまよい歩く。
見慣れたはずの王宮は何故かとても広く見え、嫌でも聞こえてしまう貴婦人達の高い笑い声が今日は全く聞こえなかった。
一体どの道を、どのように通ってここへ辿り着いてしまったのだろう。
辿り着いたのは、最も訪れたくないその場所だった。
鮮やかな花々が、まるで私を嘲笑うかのように、咲き誇っている。
それを見ていると、昨夜の光景が一気に蘇り、ドロドロとした黒い気持ちが湧き上がってきた。
吐き気がする。
いっそ、吐いてしまったら楽になれるだろうか。
「リシェル?」
聞こえてきた声に私は顔をあげた。
目が合うと、彼女は嬉しそうに微笑む。
「あ、やっぱり、リシェルだった」
「アイカ……」
「あっちから見て、そうじゃないかと思って走って来たんだ」
無邪気に笑うアイカは、きっと何も知らない。
彼女は、まるで花のように無垢なのだ。
初めて会ったあの日、彼女は“アイカ”という名は『皆を、花を愛でるように愛して欲しい』という意味で、彼女の母がつけてくれたものだと言って笑った。
けれど、きっとそれは違うのだ。
皆から愛でられる、その花こそが、アイカなのだ。
「リシェル? ……どうしたの?」
心配気に揺れる黒の瞳さえ、今は煩わしかった。
「―――何でもないわ」
そう言って、立ち去ろうとした私の手を彼女は掴んだ。
「待って、リシェル! 何かあったの?」
彼女は何も知らない。
そんなこと分かっている。
『言ってはいけない』
頭のどこかで冷静な私が、そう警告する。
けれど、私はもう自分を抑えることができなかった。
「―――何かあったの、ですって? よくもそんなことが言えたものね」
「リシェル? ちょっと待って! どうしたの? 私、リシェルに何かしちゃった?」
握られたアイカの手が震える。
「やめて、触らないで!!」
払いのけられた手に、アイカは驚愕を持ってその黒い大きな目を見開いた。
「リシェル……?」
「貴女さえいなければよかったのよ。貴女なんか、アイカなんか、来なければ良かったのに!」
彼女の黒い瞳が大きく揺れた。
傷ついた彼女の瞳が、今も、忘れられない。
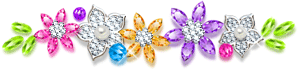

(c)aruhi 2008