four o'clock 3:花といしの利用法

「ああ、リシェル! この日をどんなに待ちわびたことか!! すごく、すっごく、すんごーく寂しかったわ!」
「私もですよ、カザリア。でも、元気そうでなによりです」
蜜色の髪を綺麗に結い上げ、翠の瞳を潤ませた二歳年上の親友は私の手をギュッと両手で包み込んだ。
「ああ、もう! 可愛いわ、私のリシェル!!」
「誰が貴女のリシェルなのですか」
ぼそりと呟いたラスリーをカザリアはキッと睨みつけながら、私の体を引き寄せた。
「リシェルに告白もできない奴に言われたくはありませんね」
「御期待に添えず悪いのですが、もう告げてしまいました」
「嘘ぉ!?」
叫んだカザリアは慌てて私の両肩を掴むと、ガバッと体を離して、驚いたように私を見た。
けれど、驚くのは私の方です。
「知っていたのですか、カザリア?」
私はこのことに関して、彼女への手紙には一度も書いてなどいない。だが、カザリアは私の問いには答えず、悲しそうに項垂れた。
「本当のことなのね……」
「まあまあ、カザリアさん。なんにつけてもランスリーフェン侯爵とエリィシエル姫の御婚約は、めでたいことなのですから」
カザリアの夫であるロウリエ伯爵が朗らかな笑みを浮かべて、彼女を抑えた。
だけど、ロウリエ伯がさらりと口にしたその言葉に今度こそ私は絶句する。一方のカザリアの方はすごい勢いで、彼に掴みかかっていた。
「ロウリィ!! そんな馬鹿なことがあってたまりますか!」
「ええ!? でも、カザリアさん、エリィシエル姫の首飾りは―――」
「―――ただのお守りです。リシェルとは婚約などしていません。
それにカザリア。他に人間はいないが、ここは一応国王の御前だということを忘れるな。昔馴染みとはいえ、きちんと場をわきまえろ」
半ば呆れたようにラスリーはカザリアを睨んだ。腕を掴まれたカザリアは頬を赤くさせるとラスリーの手を払う。
「……申し訳ありませんでした、アトラウス陛下」
ドレスを捌いて、非礼を詫びるカザリアの所作は、憤慨していても、いつもと変わらず優雅で見事なものだ。
「いや、気にする程のことじゃない。むしろ久々だから、懐かしいしな。相変わらず元気がいいな、カザリア嬢。ロウリエ伯も、任期明けすぐに呼びつけてすまなかった」
「いいえ。どちらにしろ、ご報告に伺おうとは思っておりましたので」
「そうか。だが、まあ……貴殿が言うリシェルの首飾りに関しては、本来の意味しかない」
なっ、と投げかけられた陛下の苦笑を受けて、ラスリーは肩を竦めてみせた。それを認めたロウリエ伯は「そうなのですか」と頷く。
彼らの中だけで成立してしまったらしい会話に、私は顔を顰めた。
「まだ、何かあるのですか?」
「いいえ。何も。少なくともその首飾りにはリシェルが知っている以外に意味はありません」
目に留めた橙の双眸を持つ男の表情からは何も伺えない。ただ、ラスリーが誰に対しても向ける笑みを浮かべたので、私は貰った首飾りの橙の花を握りしめながら、「なら、いいです」と溜息を落とした。
本当は陛下にもラスリーにも、ずっと守られるだけの存在であるのは嫌なのだ。だからこそ自分にできる範囲で、今度は私がアイカを守りたいと思った。
けれど、私はアイカを守る為にもこの花を利用している。だから、ラスリーから貰ったヒルデルト家の庇護をも含むお守りに他の意味が含まれていようと、私には何も言う資格が無いのことも理解してはいるのだ。
分かっているのに、零れ出てしまった呟きと溜息。
隣に立っていた古くからの友人は、私の手を引いた。
「……これだから貴方をリシェルに近づけるのは嫌なのですよ」
「何でだ」
「事情を知っている貴方ですら察せていないことを、事情を知らない私が分かるわけないでしょうが!」
「―――カザリア……!」
再び息巻き始めたカザリアの気持ちを有り難く思いながらも、彼女の腕を引っ張って留める。
「ほら、カザリアさん。エリィシエル姫も困ってますから止めましょうね。どうやら陛下も宰相殿も気付いてはいないようですが、こういうことは自分で気が付かないと意味が無いのですよ」
はいはい落ち着いて、と言いながら、ロウリエ伯はカザリアの肩をぽんぽんと叩いた。「分かったわよ」とその場に踏み留まって唇を噛んだカザリアを彼は認めると、今度は私の方に向き直って微笑えみを浮かべる。
「エリィシエル姫だって分からないことがあったでしょう? 彼らにだって分からないことがあって当然です。だから気にしない方がいいですよ。分かっている僕から言わせていただくと、さっきの内容に深い意味など全くありませんからね。むしろ、表面を流れすぎるような、たわいのないことかもしれませんよ?」
それよりも、とロウリエ伯はなお一層柔らかく目を細めた。
「主役であるアイカ姫を置き去りにしてしまいましたね。
自己紹介が遅れました。僕はロウリエ・アジ・ハルバシン・ケルシュタイード、彼女は妻のカザリア・フォル・アナシス・ケルシュタイードです。以後、お見知り置きを、アイカ姫」
頭を垂れて正式な礼をとったロウリエ伯の隣で、カザリアも膝を曲げてドレスをふわりと広げた。
呆気にとられて私達のやり取りを見ていたアイカは、その視線が自分に動いたことに気付いて、慌ててぎこちない笑顔を作る。
「え!? いえ、こちらこそ、はじめまして。中村愛花と言います。えっと、ロウリエさんに、カザリアさん?」
「はい?」
「あの、できるのなら“姫”はやめてくれませんか? 慣れなくて、くすぐったいんです。“アイカ”でいいですから」
アイカの提案に、けれど、ロウリエ伯は困ったような顔になった。
「困りましたねぇ。アイカ姫の先生となるカザリアさんは問題はないのですが、僕はちょっと。ですが、貴女が仰るのなら、周りに人がいない時だけは、“アイカさん”にいたしましょうか」
「あ、はい。それでお願いします……ってカザリアさん、私の先生だったんですか!?」
アイカは目を丸くして、カザリアの方を見やる。カザリアは微笑んで頷いた。
「では、私はアイカと呼ばせて頂きましょう。リシェルから聞いてはいましたが、本当に愛らしいわね」
「そそそそそんなことないです!!!」
顔を真っ赤にさせたアイカは両手を突き出してぶんぶんと手を交差させた。彼女の動作を見て、カザリアはクスクスと面白そうに笑い、私の耳に囁く。
「リシェル、アイカは可愛らしいけど、後三週間では、なかなか大変じゃないの?」と。
カザリアが口にしているのは、アイカの儀礼の動作のことだろう。確かに、慌てているアイカの動作は優雅さとはかけ離れている。けれど、私はここ一週間のアイカの上達ぶりを知っているからカザリアに対して自信を持って首を振った。
「いいえ、カザリア。落ち着いていさえすれば、アイカの礼の仕方は、もうとても綺麗なものになりましたよ。ダンスの方はもう少しと言ったところですが、まだ一週間しかたっていないことを考えれば上出来です」
「へえ」とカザリアは呟く。落ち着きを取り戻しつつも、まだ顔の赤いアイカへと、カザリアは微笑みを向けて力強く頷いた。
「なら大丈夫よ、リシェル。私、アイカのこと好きになれそうだわ。何よりも、花が似合いそうだもの。特にピンクのね」
「やっぱり、カザリアもアイカにはピンクだと思いますか?」
お互い良く知った友達である私達は顔を見合せて、笑みを零す。
「そうね。秋だし、桔梗の淡いピンクなんかが綺麗でしょうね」
「ああ、カザリアさん、桔梗は―――」
「ロウリィ! みなまで言わなくていいです。もう分かりましたから!」
全く、とカザリアは首を振って片手を額に添えた。
「一体どうしたのですか?」
私が首を傾げると、カザリアは心底嫌そうに彼女の夫を見やって、大きな溜息を零した。
「毒に詳しすぎて、少しでも関連があればすぐ口に出すのよ」
「そう、なのですか……」
穏やかな笑みを湛えているロウリエ伯を見る限り、とてもそうには見えない。
「だが、だからこそアトラスもわざわざロウリエ伯を呼び戻したんだ。念の為にな」
声を低めてそう告げた背の高い赤髪の男を見上げる。
「デルクラント家への見せしめをしてる分、毒殺を仕掛けてくる馬鹿な奴らも少ないだろうけどな。それでも用心しておくに越したことはない。アイカの身の回りのものは一応全てロウリエ伯に見てもらう。口に運ぶものから全部」
そう言ってアイカと陛下を見据えるラスリーの双眸は冷たく、どこまでも透き通って見える。けれど、ふと緩められた光を見て取り、私はラスリーから目を離して、アイカと陛下へと目を向けた。
「だからリシェルは心配せずとも、アイカの教育に専念してくれて構いませんよ。ただし、リシェル自身も気を付けて」
「―――ラスリーも……今度は倒れたら承知しませんからね」
ちらと何気なく上を見上げたらラスリーが至極穏やかに微笑していたから、私は顔を多分酷く顔を歪めてしまった。辛うじてそれが誰にも見えなかったのは、カザリアが私を引き寄せて抱きしめてくれた為。
「そう簡単にリシェルは渡しませんからねっ!」
元気の良い宣言に続いて、ふっと彼女を鼻で笑う声が聞こえる。
「元より、誰もカザリアから貰い受けようなどとは思ってない」
数年前と大して変わらぬように彼らの諍いは始まる。
だけど、確かに時は流れて、変わってしまったからこそ、大切なものが増えてしまったのだとも思う。
カザリアの腕の間から見えるのは、陛下とアイカという二人の姿で――――彼らが共に過ごす穏やかな時を私はどうしても勝ち取りたいのだ。
だから私は橙の首飾りを両手で強く握りしめる。
きっと私は酷く醜くてずるい。浅ましさに気付いた瞬間は、自分自身に嫌気が差したほどに。
それでも、手放したくはないものができてしまったから――――
この橙の石で形作られた花の首飾りもまた、今はまだどうしても手放すことはできなかった。
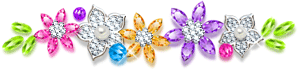

(c)aruhi 2008