four o'clock 4:込められしもの

空だけ見るとぽかぽかとしてすごく暖かそうなのに、風の中にはいつの間にか冷たさが混じり始めていた。
それでも、ぽっかりと浮かぶ白い雲を見上げながら、庭園を歩くのはとっても気持ちがいい。
「アイカ、そんなに空ばかり見ていてはこけますよ。さあ、現実逃避はやめなさい。秋桜の花言葉は?」
「……うぐっ」
もう何度詰まったことだろう。昨日までは目を楽しませてくれた庭園に咲き誇る秋の花々が今では心底憎らしい。
花言葉の先生であるカザリアさんは、秋桜の花びらのような色の口をニッと上げて微笑んだ。その笑みが何とも楽しそうで、楽しそうで。逆の立場だったらどんなにいいか、と願ってならない。
「残念、アイカ。乙女の純潔、真心、美麗。色別のも含めたらもっといろいろあるけど、今はこれだけにしときましょう。
それよりも……。さあ、アイカ、吐きなさい! 先に想いを告げたのはアトラウス陛下なの? それともアイカなの?」
カザリアさんの翠の瞳は好奇心で、それはもう輝いていて。
黙秘権を使いたくても、私が話し出すまでカザリアさんはじっと待ってるから、結局私が折れるしかない。
諦めの溜息を落としてはみるものの、正直、本当に泣きたい。
「……あれは、どっちからって言うんでしょう? 別に告白したわけじゃなくて、私が思わず王様に抱きついちゃったら、笑われて……額にキスされました……」
「きゃあ!」
『きゃあ!』って……そんな自分で思い出してても恥ずかしいのに、そんな面白そうに笑われると余計に恥ずかしいよ。大体あれは抱きついたって言うより、勢いあまって突撃したって方があってるような気がするし。
「まあ、真っ赤になっちゃって!」
「だあっ! だから、そうゆうこと言うのやめて下さい! 本当に恥ずかしいんですってば!!」
『部屋の中で勉強するよりも、庭園でした方がはかどるわ』というカザリアさんの言葉にのせられてうきうきとして出てきたのが間違いだった。まだ授業が始まって一時間も経っていないのに、ずっとこの調子。習ったばかりの花言葉を答えられなかった私は、王様との出会いから今までをことごとくカザリアさんに話す羽目になっているのだ。周りに誰も居なかったのが本当にせめてもの救い。
「そもそもどうして花言葉なんですか……」
星夜祭で私がしなければならないことはダンスであって、それ自体や儀礼の勉強なら分かるのだが、花言葉などは最も関係が無いように思える。
私が首を傾げると、風に揺れた秋桜へと手を伸ばしながら、カザリアさんが愛おしそうに微笑んだ。その何気ない仕種さえも絵のように見えるのだから、美人って得だなぁとこっそりと思う。
「花が意味をも含んでいるのはアイカも知っているでしょう?」
カザリアさんの問いに私は頷いた。
前にリシェルから、花に意味をもたせることが王宮内では一種の遊戯だと聞いたことがある。一体誰がこんな遊びを考え出してしまったのか。今の私には全くもって迷惑すぎる話なのだけれど。
「一つ一つの花が名を持つように、それぞれの花には物語があって、そこから派生した意味がつけられるの。例えば、水仙は水の中に映った自分の姿に恋した娘の化身だという話が元になってるわ。だから、水仙の花言葉は“うぬぼれ”」
「それに似た話、知ってます。ギリシア神話の青年ナルキッソス。神の罰を受けたナルキッソスは水に映った自分の姿に恋して、水の中に身を投じる」
どこか酷く残酷で、それでいて甘やかにも聞こえる話。私は授業で習った絵画作品を通してこの話を知った。
「その話も確か、最後は青年が水仙になった」
「そうなの?」
カザリアさんは少し驚いたように、大きな目を丸くさせた。
「―――けど、そうね……。別の世界でも、花の姿が変わらないなら、花から生まれる話もどこか似ているのかもしれないわね」
確かにそうかもしれないと、私も思う。だって、私が思い浮かべる水仙の花は、いつも微妙にうつむいていて、何かを覗き込んでいるようにも見えるから。
「だからね、アイカ。飾られる花は言葉だけでなく物語をも相手に連想させることができるのよ」
「はい」
先生の言葉に対して、返事をすると、カザリアさんはふっと笑う。
「それにねぇ~……いろいろ分かってると、おっもしろいんだから」
何が面白いんだろうと、首を捻る私を見ながら、カザリアさんは、くふふと笑い声を洩らした。
「だってね、あからさまに敵対心ばしばしの花を付けて挨拶に来る令嬢がいるのよ」
「それって、どこが楽しいんですか……?」
気付いてしまったら、ただそれだけで気がなえてしまいそうな気がする。
「あら、宣戦布告には堂々と立ち向かわなきゃ! 一体アイカの所にはどんな令嬢が来るかしらねぇ。今から楽しみだわ! ねっ!」
「…………」
相槌はとてもじゃないけど打てない。ただでさえ必死なのに、もしそんな人たちが来たら私に立ち向かえるんだろうか。
「やっぱりリシェルなら上手くやってたのかなぁ……」
「何言ってるのアイカ。リシェルならにこりと微笑んで、さらりとかわしてたわよ? まあ元々、この宮廷内にリシェル程に完璧な姫令嬢なんていやしないんだから、いくら言われてもやっかみにしか聞こえなかったしね」
「すごっ……!」
「当り前でしょう。リシェルよ?」
そう言ったカザリアさんはすごく自慢げで、誇らしげで、その姿が微笑ましい。
「カザリアさんってリシェルのこと大好きですよね」
「ええ。大好きよ。だから並み居る男(虫)共からリシェルを守って来たのも私」
「あは。ラスリー侯爵とか?」
「ああ、あれは論外よ」
カザリアさんは顔を歪めて、首を振る。
それが何故なのか理解できずに首を傾げると、カザリアさんは溜息を付いた。
「私がリシェルの友として宮廷に上がったのは十五の時で、つまり、その時リシェルは十三だったんだけどね、寄って来る奴らにあの男は含まれてなかったわ。それから、私が嫁ぐ為に宮廷を出るまでの五年間は少なくともリシェルのとこにラスリーはほとんど来てないわよ。だから、正直すっごくびっくりしたわ。帰ってきたらリシェルの傍に居るんだもん」
「でも、ラスリー侯爵って昔っからリシェルのことが好きだったんですよね」
そうだったって王様から聞いた。聞いたことをラスリー侯爵には言うなよってしっかりと口止めはされたけど。
私の確認に、カザリアさんは肩を竦める。
「まあね、私から見ればバレバレだったから、その時もリシェルに害が及ばないように裏で画策していたのかもしれないけど。……でも、隠れたとこでやってたって意味が無いでしょう。本当に腹が立つわ」
カザリアさんは苦々しげにそう呟いた。だけど、そこに違和感を覚えて、私はきょとんとしてしまう。
「もしかして……カザリアさんって、ラスリー侯爵のこと好きでした?」
私に向けられたカザリアさんの顔は、何と言うか、すっごく奇妙なもので、その表情が私が口にしたことが図星であったと告げる。
「そうなんですか!?」
「うっ……、む、昔のことよ……」
慌てて逸らされたカザリアさんの横顔は紅潮していて、彼女は蜜色の前髪をくしゃりと握りつぶすと観念したように溜息を落とした。
「それでも、私の中の優先順位はリシェルの方が上だったのよ。だから、もし、あいつがリシェルの所にのこのこやって来たなら昨日みたいに虐げただろうし、でも、だからと言って自分の方を向いて欲しいとかそういうのじゃなかったの。ただ、私はリシェルの傍にずっといたから……リシェルが続いてきた関係を壊すのを厭うだろうことは容易に想像できたし、多分ラスリー自身も分かってた。だからこそ、あまり近づいては来なかったのでしょう。いつもどこかリシェルとは一歩置いてたし、完全に壊れもの扱いだったもの。リシェルからは、もちろん、近づこうとはしないしね。まぁ、こっちは奴の自業自得だけど」
カザリアさんはふぅ、と息を吐くと、「つまり何が言いたいかっていうとね」と私の顔の前へと人差し指を突き出した。
「アイカが、もし少しでもリシェルに負い目を感じているのなら、それはリシェルに失礼よ。これは、ちょっとちがうけど同じような立場に居た私だからこそ、はっきり言えること。分かった?」
勢いに押されつつも、私はしっかりと頷く。
「それは大丈夫です。リシェルにも前に同じ様なことを言われました。それに、もしもリシェルが王様のことを取り返しに来るっていうのなら、私だって戦いますよ」
私はカザリアさんに笑みを作ってみせる。ちょっとだけでも、不敵に見えるといいなと思いながら。
「いいじゃない、アイカ。その意気よ! それで、甘やかされた令嬢達をぎゃふんと言わせましょうね!」
「はい!」
カザリアさんは満足そうに頷くと、「それじゃあ」と言って水色のドレスのポケットから小さな鋏を取り出した。屈んだかと思うと、チョキンという音が聞こえ、再びカザリアさんは私の目の前に立ちあがる。
「はい。では、これをアトラウス陛下に渡すこと。それで今日の授業は終了よ」
「ぺんぺん草?」
「違うわ、ナズナよ」
「はい、えっと、ナズナ……ですよね? 私達の世界ではぺんぺん草とも言うんです……って、これを王様に渡すんですか?」
「そう、これよ。本当は春の草花だけど、間違って秋に咲いちゃったようね」
はい、と掌に載せられたのはやはり見間違うはずもなくぺんぺん草で、本当にこれでいいのだろうか、と先生を見上げる。
だって、カザリアさんが取ったこれは、花壇に植えられた色とりどりの花々の中に紛れ込んでいたもので、つまりは、雑草だ。仮にも一国の王である王様に雑草をあげても、不敬罪には当たらないのだろうか真剣に考えてしまう。
掌の中にあるぺんぺん草は確かに愛らしい小さな花を付けているのだけれど……
私から見たらこれも充分に可愛いって言える花なんだけど…………
不思議に思って見上げたら、そこには今にも吹き出しそうなカザリアさんが居た。
「……カザリアさん、なんだかからかってませんか?」
「まさか! アトラウス陛下は絶対喜ぶわよ?」
「王様って、この花が好きなんですか?」
「うん、そうそう」
怪しい。なんだかすっごく怪しい。
疑ってるのが分かったのか、カザリアさんは腰に手を当てて言った。
「アイカ。これも立派な宿題なのよ。分かった?」
「―――う、はい」
頷きながら、まあいいか、とも思う。
だって、ぺんぺん草としてのナズナの遊び方を教えたら、王様はすごく柔らかい顔で笑ってくれそうな気がするから。
カザリアさんと別れた私は、そのまま王様の執務室へと向かう。
多分、今はちょうど休憩時。だから、カザリアさんもこんな宿題を出したのだろう。
こんこんと二回ノックしたら、馴染みの侍従さんが扉を開けてくれた。
聞けばやはり、休憩中で、お茶を飲んでいた王様が顔を上げて、こちらを向いた。
「アイカ、か」
「……うん、王様」
この部屋に居る王様は、他の場所にいる王様よりも、やっぱり“王様”であって、そのことになんだかいつもほんの少しだけ緊張してしまう。それでも、向けられる二つの青の穏やかさは変わらないから、私はいつの間にか緊張を解いてしまうのだ。
「あのね、王様。プレゼントだよ」
そう言って、ナズナの花を差し出した。本当の本当は宿題なんだけど、なんだか、正直にそう言うのもなぁって思ったから。
王様は小さな白い花を見た瞬間、奇妙な顔をして、それから、ふっと吹き出した。
「―――カザリアか」
くつくつと笑い出した王様に戸惑いつつも、私は「うん」と頷きを返す。
「で、どっちがプレゼントなんだ?」
「どっち?」
思いっきり首を傾げた私を見て、王様の笑い声が大きくなった。
なんだかとっても失礼だ。
怪訝さに眉を顰める私に向かって、王様は来い来いと手招きをする。
素直に歩いて行ってしまった私も悪かったとは思うんだけどね。王様は差し出した花の方ではなく、私の手を引っ張って、その腕の中に留めたのだ。
額に落ちてきた熱に思わず「ひゃあっ」と変な声を上げてしまう。
「王様、不意打ちは―――!」
「―――じゃないぞ? 今回ばかりはな。アイカは何を習って来たんだ。ちゃんと調べてから、ここに来るべきだったな」
「ふぇ!?」
瞼に寄せられた口に思わず目を閉じると、同じ柔らかさが頬にも唇にも続いた。
「まあ、今日はここまでにしとくか」と王様は最後に首筋にキスを落として、私を解放する。
再び覗いた青の瞳が悪戯っぽく見えて、なんだかとても憎たらしい。
それでも、文句が言えなかったのは私が唖然としていたからで、それを見て王様はまた可笑しそうに笑いだしたのだ。
とりあえず、私は学んだ。
どんな花にも一つ一つ隠された意味が込められていることを。
けれど、それを思い出したのはリシェルから花言葉の本を受け取った後のことだったのだ。
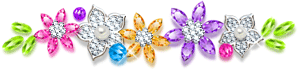

(c)aruhi 2008