four o'clock 5:課題と対策と

「うーーーわっ……何て言うか、すごいわね、これ」
「ラスリーみたいなこと言わないで下さいよ、カザリア」
「えーでも、リシェル。これ、すっごいわよ? というか、あんな奴と一緒にしないでよ」
カザリアはしかめつらしい顔をこちらに向けると、「はい」と言って一枚の紙を私に差し出した。書かれているのはフィラディアルの歴史に関する事象。アイカにどれくらい知識が身に付いたかというのを調べる為に出された問題と、彼女が書き記した解答―――つまり、歴史の試験の結果である。
「アイカの字はとても上達したと思うのですが……」
手習いを始めた時から知っている私は反論してみたが、カザリアからは呆れた顔と「とても読めたものじゃないわ」という言葉が返ってきてしまった。全くラスリーと同じことばかりを彼女は告げる。私としては、アイカに厳しく当たっているつもりだったのだが、彼らの方がよっぽど厳しいらしい。確かに流麗な文字とは言い難いが、アイカの文字は一般の文字に近い。それほど気にするものでもないと思うのだが。
けれど、不服に思っていた私が黙っていたせいか、カザリアは片眉を上げると、「甘い!」と言って、ビシリと鼻先に人差し指を突き付けてきた。
「甘い! あーまーいのよっ、リシェル! 確かに字は綺麗よ、字はねっ! だけど、よく見なさい! 誤字だらけじゃないの」
カザリアはぺしぺしと私が手にしている試験の紙を叩いた。そこには、“シャルレンの戦い”と書くべきところが、“シャリアンの戦い”と書かれてあった。
「いくら、倒れかけていたこの国を立て直すきっかけとなった戦いの名を覚えてたからって、“シャリアンの戦い”なんて書いちゃったら意味分からないでしょう。誰にも通じないわよ」
「まあ、誤字は多いですが、話している分には問題はありませんし。星夜祭では大丈夫でしょう」
事実、アイカがこの戦いの名を口にする時は、ちゃんと“シャルレンの戦い”と言っていたのだ。恐らく、試験の時もきちんとした答えは分かっていたはず。それでも間違ってしまったのは、まだこちらの文字に完全には慣れていないところがあるからだろう。
しかし、カザリアは、「だからっ、そういうところが甘いんでしょう!?」と大きく溜息を付いた。
「今回はいいとしても、これから確実に必要になるんだから覚えておくことに越したことはないのよ、リシェル」
「ええ、そうですね。分かっています」
思わずクスクスと笑ってしまった私を見て、カザリアは「もうっ」と息まき、片手を自身の額にあてがった。
「カザリアはちゃんとアイカのことを考えてくれているのですね」
彼女とアイカが出会ってからは、まだ一週間も経っていない。それでも、カザリアがアイカのことを心配してくれて、できるだけ良い方に計らってくれようとしているのが、傍目から見てもよく分かるのだ。
零れてしまった笑みをなかなか収めることが出来ずにいると、カザリアは呆れた顔をして、「リシェル」と至極真面目な声音で私の名を呼んだ。ふと顔を上げると、彼女の翠の瞳に見据えられ、取られた手に力がこもる。
「私はね、リシェル。あなたが大事にしようとしているものなら、みんな大事なのよ。あなたが、陛下が大事にしようとしているものを大事にしようとしているのと同じ。だから、アイカも私の大事なもの、守るべきものの対象に入るの。もしも、あなたがアイカのことを大事に思っていないのなら、気にかけてなんかないわよ」
戸惑いもなく、揺れもせずカザリアはそう言い切った。彼女の言葉を素直に嬉しいと思う。カザリアは、きっと『だから、感謝なんてしなくていい』と私に言ってくれてるのだろう。なぜなら、それが、私がよく知っている彼女なのだ。
だけど、「ありがとう」と私はカザリアに告げた。思ったとおり、カザリアはとてもきまりの悪そうな顔をして俯いてしまったけれど、私にはこれ以外に彼女に伝えられる言葉を知らないのだから仕方がない。
「私も……カザリアが大事にしているものなら、大事にしたいと思いますよ。私にとっては、カザリアもとても大事です」
カザリアは照れたように頬を赤らめて、「ありがと」と消え入りそうな声で呟いた。
握られていた手を、つなぎ直して、ギュッと力を込める。
「ねぇ、先生? アイカの様子はどうですか?」
問いかけると、カザリアは、ふっと笑って顔を上げた。ほんのりと色づいた頬はそのまま、けれど、カザリアは彼女らしく、どこか悪戯めいて笑う。
「そうねぇ、まだまだだけどアイカの熱心さは認めるわ。とても感心できるものよ。特にアトラウス陛下に花を持って行くよう課題を与えるようになってからね」
「初めに持って行ったのがナズナでしたからね」
「ナズナの意味をどう捉えるかはアトラウス陛下次第でしょう? 相手が花の意味をどう取るかと考えることも、勉強のうちよ」
予想通り一番面白い結果になってくれたようだけど、とカザリアは楽しそうに付け加えた。
「絵画についても、順調に進んでいるようですよ。なんでもアイカはあちらの世界のダイガクという学校で、美術史を専攻しているらしいんです。だから、元々興味があって、前に来た時も陛下からよく教えていただいていたみたいですね。舞踏の方もこのまま行けば充分形になります。何よりも陛下が補って助けてくださるでしょうから。
―――残る問題は、演劇の方ですね」
「そう、こればっかりはねぇ~」
貴族が好みそうな演劇は種類もそれを模した隠喩も多岐に渡る。一度も目にしたことがない演劇の数々を全て覚えるには無理がありすぎるのだ。実際に観劇することができるのであれば、また違ってくるのだろうが、それには時間が足りなすぎる。
アイカはとても記憶力が良いし、何よりも努力家だと思う。それでも、劇名と内容を一致させるのには難しいだろう。登場人物を加えるとしたら、それ以上の苦労が必要だ。
「一応、私も補佐には付きますが……アイカは物語の内容には興味があるようですし、少し補足すれば思い出すことも可能だと思うのです」
けれど、アイカに誰も付いていない時、つまりは、陛下も、私も、それにカザリアもが誰かに話しかけられている時は彼女一人で解決するしかないのだ。その時は、どんなに望んでも手助けはできない。話を切り上げられそうな時は、もちろん切り上げるつもりだ。だけど、話しかけてくる人物全てが、易々と話を切ることのできる立場にいる相手だとは限らない。
「もうこうなったら、いっそ、舞踏が始まるまでアイカを閉じ込めて置きたいわね」
カザリアが、ふぅと溜息をついた。
それでも、そうしてしまったのならば、私達の目的が達成されないこともまた、彼女は知っている。
―――アイカの存在を皆に知らせて、立場を確立させること。
それこそが、星夜祭においての重大な課題であるのだから。
エリィシエル様、と呼ばれた声に振り返ると、隣室に繋がる入口の前にユージアが立っていた。ランスリーフェン侯爵の来訪を伝える彼女の言葉に、カザリアの表情が一瞬にして不機嫌そのものとなる。
「追い返してきましょうか、リシェル」
「そういう訳にもいかないでしょう」
アイカに関する計画にはランスリーフェン侯爵の力が必要不可欠なのだ。アイカ自身と私達がどれだけ上手く立ち回っていても成功する可能性は低い。誰かが周りの人々をきちんと抑えておいてくれていて初めて為せることが多々ある。家格だけではとても抑えられない。
宰相位、侯爵位に就いているランスリーフェンだからこそ抑えることができるのだ。いわば、彼はアイカの次に重要なこの策略の要でもあった。
部屋へと入ってきたラスリーは誰に言われるでもなく定位置に座る。いつも通りのお茶会は、始まった時とは別の意味を、今では持っていた。
で? とラスリーは切り出した。ティーカップの横にばさりと置かれた書類を、二つに捌きながら、彼は口を開いた。
「どうしてここに、カザリアまでいるのですか?」
憮然とした表情で、カザリアを睨みつけているラスリーに呆れなかったといったら、嘘になってしまうので、素直に呆れたと言おう。
「どうして、あなたはそうなんですか」
張り詰めていた気持ちはすぐに崩れ落ちてしまう。
どうと言われてもな、と苦笑しているラスリーは分けていた書類の内の一束を私に差し出した。
受け取った束を、ぱらぱらとめくって確認する。
「普通の書類ですね」
「ああ、普通の書類だ。今回も特に変わったことは無し。皆、素直で大人しくて助かるな」
ラスリーは、ふと口の端を上げた。何処からどう見ても、普段と変わらない王宮業務の書類だ。そのことに安堵して、思わずほっと息をついてしまう。何も起こらないなら、起こらない方がいい。抑えるものが少ないなら、少ない方がいい。
礼を述べれば、「ああ」と落ち着きを宿した頷きが穏やかに返された。取られたティーカップが、カチャリと音を立てて、受け皿から離れる。
「あーあ、本当に仲良くなっちゃってるし。全く人が目を離してる隙にどうしてこうなってるのよ」
口をつぐんでいたカザリアは、片手を伸ばして焼き菓子を取って口にした。サクリと崩れた焼き菓子を二回に分けて口に放る。
「大体、ラスリー。周りにはべらしてた綺麗で可愛い令嬢達はどうしたのよ」
「…………一体いつの話をしているんだ」
ラスリーは私の隣に座っているカザリアをねめつけた。けれど、カザリアは特に気にした様子もなく、逆にひたと見据え返して、にんまりと微笑する。
「いつの話って、ついこの頃のことじゃない。たったのニ、三年前」
ねぇ、とカザリアが話を振ってきたので、私もティーカップを両手で包み込んだまま、「そうですね」と返す。
「あの頃、ランスリーフェン侯爵の周りに関しては女性の噂が絶えませんでしたからね。その所為で泣き嘆く令嬢達の話も、醜い争いを繰り広げる令嬢達の話も、たくさん。せめて一人に絞っておけばよかったのに」
「まあ、リシェルにまで火が及ばなかったからその点はいいんだけどねー」
「今思い返すと、当時は現在よりも大分静かで、穏やかでしたね」
「その分、周りがぴぃぴぃぎゃあぎゃあ、うるさかったからね。まぁ、ある意味あれも見物だったけど」
カザリアは、手に取った焼き菓子をさくりと口に入れる。ゆるく冷めていく茶の温かさを掌に感じながら、私は、ことりとティーカップを受け皿に戻した。
ラスリーは溜息をつくでもなく、にこりと綺麗に笑みを浮かべて「まあ、そんな感じだ」と告げた。
テーブルの上に置いてあったもう一束の書類にざっと目を通して確認した後、ラスリーは首肯して、おもむろに席を立った。
「これまで通り、アイカの方はリシェルに任せたから。今日はこの辺で。何かあったら、また来る」
頷きを返して、ユージアにラスリーが帰る旨を告げる。ユージアは先立って、扉を押し開くと彼の退出を待った。
ラスリーは、一度だけ静寂を宿した橙をこちらに向ける。そして、すぐに踵を返すと、いつものように部屋を出て行った。
カザリアは、ちらりと私の方を見やった。なんだかとても奇妙な表情を浮かべて、彼女はこちらを見る。
「―――さっきのはちょっときついんじゃない、リシェル。まあ、私が振ったのが悪いんだけど、さ。もう知ってるし、分かってるんでしょう?」
「けれど、本当のことですよ。それに、本当に、ああ思ったんです」
ふうん、と閉まった扉の方を見ながら、カザリアは相槌を打って、くいと私の顔を彼女の方に向かせた。翠の瞳を見上げるよう、顎を彼女の手で固定されたまま、訳の分からない私はカザリアの行動に首を傾げる。
カザリアは、はぁと溜息をつくと、言った。
「らしくないわね、リシェル。気になるなら追いかければいいじゃない」
「……別に気になってはいませんよ。気になっていたとしても、私は追いかけてはいけないんです」
「どうして?」
答えなければ離してくれないのは分かっていたから、自嘲を浮かべて「駄目なんです」とだけぽつりと答える。
すると、カザリアは肩を竦め、顎にかけていた手を今度は私の頭へとあてがって、ぽんぽんと撫でた。頭を撫でて続けてくれる友人を私は驚きを以って見上げる。
私の視線に気付いたらしいカザリアは、口元に微苦笑を刻んだ。
「私、リシェルのそういうところ好きよ?」
「…………私は嫌いです」
静かすぎる瞳の色に、違和感を覚えてしまう自分が嫌だ。
「いいんじゃない? それでも。リシェルのしたいようにすればいいわ」
「したいように、しちゃってる自分が嫌なんですよ」
カザリアはふっと吹き出した。
ユージアにインクとペンを頼んで持ってきてもらうと、置かれていた書類から一枚抜き出して、さらさらと書きつける。
ほら、と差し出された一枚の紙を怪訝に思いながら、私はじっと見つめた。
「え、何ですか……?」
「終わったのよ」
「はい?」
「終わったの」
もう一度繰り返して、カザリアは私に紙を握らせる。
「仕事終わったから、提出してきなさい。提出先は宰相殿」
「え、ええっ!? 本気ですか」
「本気も何も、どっちにしろ終わったら遅かれ早かれ渡しに行かなきゃいけないんだから、一枚も、十枚も同じでしょ」
カザリアはきっぱりと言い放った。
唖然としている合間に、立ち上がらされて、部屋の外へと押し出される。パタンと何とも呆気なく、そして容赦なく閉まってしまった自分の部屋の扉を、私は呆然と眺めることしかできなかったのだ。
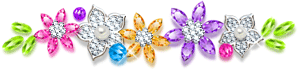

(c)aruhi 2009