four o'clock 6:音の鳴らない音

ふいに吹きそよいだ風は、思ったよりもざわりと茂みを揺らす。冬が馴染み始めた庭園は次第にくすみ、色あせつつあった。
「ランスリーフェン侯爵」
掲げた片手をひらひら振って機嫌よさそうに現れた女の姿を目に留め、思わず出そうになる溜息を何とか嚥下させる。
引き上げられた唇と同じく濃い赤の双眸を持つ彼女は、目の前に来たところで右手を突き出し、「はい、どーぞ?」と小首を傾げた。
「別に、頬でも構わないわよ?」
彼女は、ニッと形の良い口の端を、さらに上げる。
仕方がないので宙に浮いたままの手を取って、儀礼の挨拶を一つ落とした。
「ご機嫌麗しゅう、アルヴィアナ姫。…………ほんっと、嫌味なくらい機嫌よさそうだな」
「ええ、上々よ。貴方は悪そうね、宰相殿」
「それで? 何かあったのか?」
「別に、特にはなんにも……って、あはは、貴方ってホント、相っ変わらず最低ね」
ことさら報告を持ってきてすらないなら、こちらには特に用はない。
取り落とされた手を、アルヴィアナはわざわざ掲げて、「酷いわねぇ」と俺の目の前で振ってみせた。けれど、すぐに飽きたのか、後は何事も無かったように、彼女の腕は音もなく自然と落とされて元の位置へと戻る。
「どうして、ここにいるのかしらぁって思ったのよ。暇そうだったから声でも掛けてみたの」
「暇じゃない。庭園を突っ切って通った方が近いからだ」
へぇ、とアルヴィアナは面白そうな笑みを刻んだまま、東棟と西棟を交互に見比べる。
「ま、そうね。“近い”、わね。特に執務室がある辺りから居住区に行くなら、渡り廊下を通るよりかは早く着くものね」
横に目をやり、ぷちりとちぎり取った沈丁花の葉をアルヴィアナはくるくると指の先で舞わせる。半ば枯れている小さな葉は、それでも半分以上は鮮やかな緑を宿していた。
緑の葉に寄せられ、外れていた赤の瞳は、だが、ふとこちらへと向き直った。
「それで? 若草のお姫様と何かあったのかしら?」
「別に何もない」
「そうなの? 大変ねぇ~」
「何がだ」
「ま、いつものことじゃない。大絶賛大後悔中? 虫なんか投げちゃったのが悪かったわね」
「投げてはない。大体、どうしてアルヴィアナがそれを知ってるんだ」
「あら、確かにエスピア家はヒルデルト家より家格が下だけど割とやるのよ? 現に貴方だって頼りにしてるじゃない。私の情報網を甘く見ないことね」
伸びてきた手に、くくっていた髪を前へと流された。ちらりと上空を見上げ、悠然と微笑む彼女に今度こそ溜息をついてしまう。
「どうせオランリにでも聞いたんだろ」
「違うわよ、聞いたんじゃなくて、脅して聞き出したの」
邪気を覗かせない瞳を煌めかせ、「だって、あの人からかうのおっかしいんだもの」とアルヴィアナは続ける。とりあえず余計な情報を流した奴がいる財務部には後で寄っておく必要があるな、と今日の予定に付け加えておくことにした。
「せっかく限りなく零に近かった可能性が、ちょっとばっかし上がったのにね。努力報われず、あんまり意味ないわね」
クスクスとさも楽しそうに声を立てて、アルヴィアナは手にしていた沈丁花の葉に息を吹きかけ、ぱっと捨てた。
「まあ、いいんじゃない? お姫様はちゃんと綺麗なまま。貴方の望みは叶ってる」
そうでしょう? とアルヴィアナが声を出さずに口元だけを動かして、告げた。
それが、いつのことを指しているのかはすぐに思い当たる。正直うんざりしてしていると、アルヴィアナに、くいと胸元の服を引っ張られ、引き寄せられた。
「でも、壊されなくて良かったでしょう? 頑張ったかいはあったんじゃない? この美しき恩人様に感謝してよね」
耳元で囁かれた言葉は、濃すぎる甘い香りと共にすぐに離れる。頬に触れた温かみは気にするほどでもない。けれど、次いで告げられた彼女の言葉に、つい眉を寄せてしまったのも事実だった。
「思ったよりも平和に事を運んじゃったことが、安心したような、がっかりしたような、そんな感じだけどね」
アルヴィアナは肩を竦めてみせつつも、紅い口元はしっかりと弧を描いていた。
「おやおや、宰相様ぁ? 自慢のお顔が崩れてますよ?」
「―――アルヴィアナ」
はい? と首を傾げたアルヴィアナの薄色の髪の上に、書類を落とす。ぱしり、と軽い音を立てた書類の束の下から、珍しくむっと表情を崩した彼女が睨み上げてきた。
「これ、庶務部に運んでいてくれないか」
「私は使いっぱしりじゃないんですけど。何? 仕事放棄?」
文句を言いつつも頭の上から書類をどけて、アルヴィアナは嘆息と共に、受け取った書類を簡単に確認する。
「それに関しては、俺の仕事じゃないからな」
「へぇ~、いいんだ」
ま、いいけどね、とアルヴィアナはほくそ笑み、「じゃあ、報告です」と技とらしく顎でしゃくってみせた。
怪訝に思いつつも、促されて、後ろを振り返る。だが、別段変ったことはない。そこには、ただ、この庭園と繋がる外廊が見えるだけだ。
一体何なんだ、とアルヴィアナを見返してみれば、「上よ、う、え」と、今度は指で斜め上を指し示された。
指の先を素直に辿って目線を上に向ける。さっき見た外廊のちょうど真上、三階の渡り廊下からは見慣れた金の髪が流れて覗いた。
東から西へと動いて行く姿を不可解に感じる。なぜなら、西は居住区側。彼女は元々そちら側に居たはずなのだから。
「リシェル?」
なぜ東側に居たのだろう、と理解できぬまま、そう呟けば、「そ」と横から短く答えが返った。正解、と満足げにアルヴィアナは告げる。
「さっき、お姫様が見てたのよ」
伸ばされ、自身の片頬へと触れた冷たさのある掌。瞬きもせずに見据えられた濃い赤。含まれた意味を悟り、げんなりする。
「わざと、か」
「まあねぇ。だって、面白いんだもの」
アルヴィアナの腕を取ってどければ、彼女はそのまま手を口へとあてがってクスクスと笑みを零した。
「まあ、いい」
任せた、と言い残して、踵を返せば、「あれれ、いいの?」と背に少なからず驚きを滲ませた声が掛った。
「ほら、お姫様。追いかけるんじゃないの?」
ぴたりと笑い声を収めた女は、ついついと誰も居なくなった渡り廊下を指差す。そこには、もはや何の名残りさえなかった。
「いちいちアルヴィアナの娯楽に付き合うのも面倒」
「うっわぁ、たっのしくなあい。そんなんだから、駄目なのよ」
「それでも、今の優先順位は考えるまでもなくアトラウス陛下だろ。仮にも俺の主。俺が留まるもう一つの理由。自分の方じゃない。残念だったな」
興冷め、と酷く不服げな声を上げるアルヴィアナに、ひらひらと後ろ手を振って歩を踏み出す。
実質的には恐らく何もすることはできない。なぜなら、初めから、これは俺の仕事ではないのだから。
全て、知れてしまった。
できる仕事は、アトラスに伝えるところまで。
そこから先は管轄外だ。後はどうにかしてもらうしかない。どうせ元より避けられやしなかったことなのだから。
アルヴィアナは、たった一言静かに告げた。
これは一応任務外のことだけど、とわざわざ前置きまでして。
「もう一人のお姫様。黒髪の彼女が崩れた」
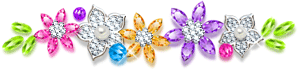

(c)aruhi 2009